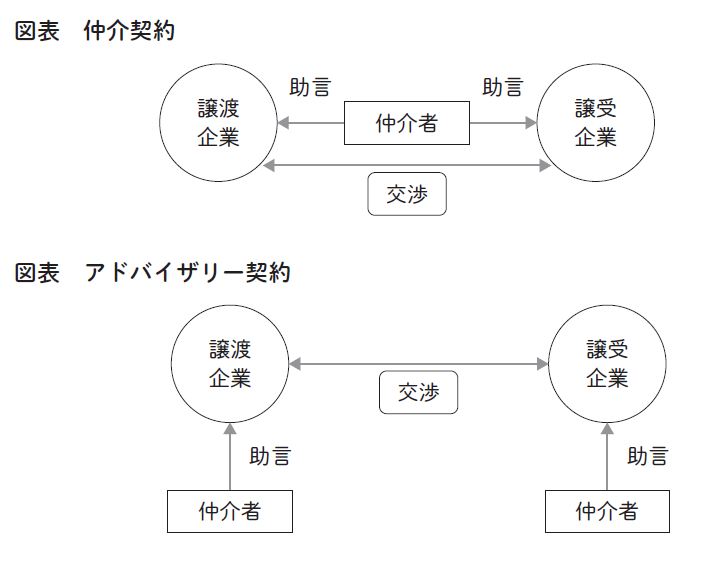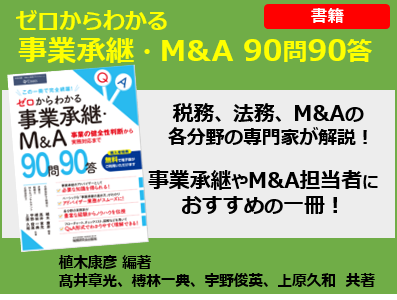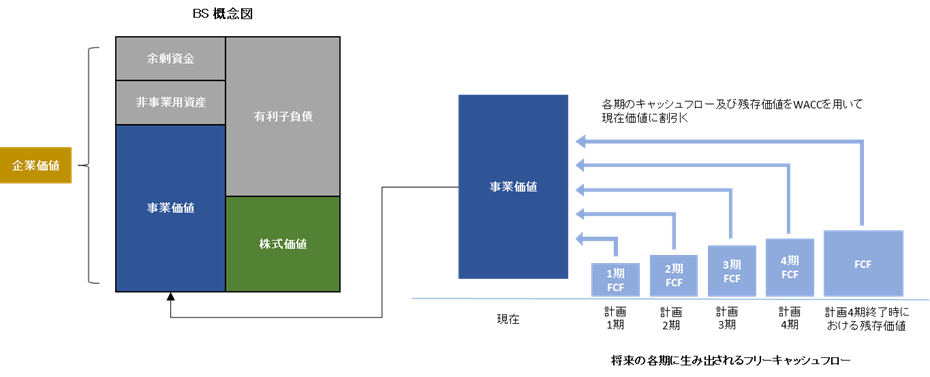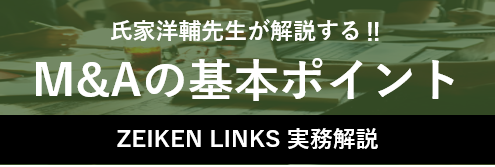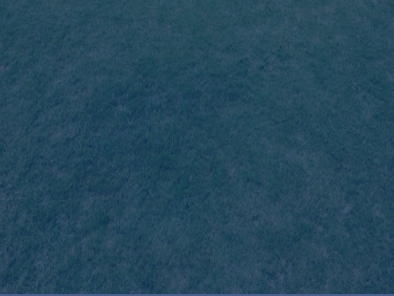[業界別・業種別 M&Aのポイント]
第10回:「アパレル小売業のM&Aの特徴や留意点」とは?
~ブランド・店舗ごとの損益管理は?商品仕入れは?会計処理は?在庫状況・利益率は?~
〈解説〉
Q、アパレル小売業のM&Aを検討していますが、アパレル小売業M&Aの特徴や留意点はありますか?
アパレル小売業の多くは、店舗での販売とECでの販売を併用しています。また、1ブランドのみを運営している企業もありますが、ある程度の規模になると複数のブランドを運営している企業が多くなってきます。複数の店舗や複数のブランドを運営している場合に、重要となってくるのがブランドごとの損益、店舗ごとの損益管理ができているかです。ブランドごとや店舗ごとに損益管理をすることで、実状の正確な把握と今後の適切な打ち手の検討が可能となるからです。M&Aを検討する場合でも、ブランド別や店舗別の損益状況は非常に重要な損益指標となります。
ブランド別や店舗別の損益以外に、KPIとしてされる基本的な指標として、客数・客単価が挙げられます。売上高を購入客数、客単価に分解をして分析を行います。入店客数の把握が可能な場合には、購入率(購入客数/入店客数)もKPIとして設定しましょう。買上点数を把握して、客単価を買上点数×平均商品単価に分解することも可能となります。どのようにKPIを設定するかは企業ごとの判断になりますが、一般的にはこれらの指標は重要であるため、分析している企業も多いです。
また、アパレル業界の特徴として、小売価格を上代(じょうだい)、卸売価格を下代(げだい)と呼ぶので、覚えておきましょう。また、アパレル業界だけではないですが、商品仕入に関して、買取仕入、委託仕入、消化仕入の3つの取引方法があります。
①買取仕入は、仕入れ先から商品を買取る仕入れ方法です。買取るわけですから、売れなかったとしても返品することは出来ません。つまり在庫リスクがあるため、商品の仕入れ内容や数の精度が重要となります。
②委託仕入は、仕入先と販売委託契約を結び、店舗に商品を置き、商品が売れた場合に商品代金ではなく「販売手数料」をもらう方式の仕入方法です。在庫リスクがないことがメリットとなります。
③消化仕入は、商品が売れるまでは仕入先の資産となり、商品が売れた場合に、仕入と売上を計上します。委託仕入と同様に在庫リスクがないことがメリットとなります。
委託仕入や消化仕入は在庫リスクがないことがメリットですが、1商品あたりの利益率は買取仕入よりも低くなります。それぞれの仕入方法を理解した上で、在庫の状況や商品の利益率を正確に把握しましょう。
アパレル業界では一般的に夏と冬の売上・利益が大きくなり、中でも冬の売上・利益の金額が最も大きくなります。これは、夏と冬にバーゲン等が行われること、冬物はコート等を取り扱うことから商品単価が大きくなることためです。夏は暑く、冬は寒い方が売上は大きくなる傾向にあり、バーゲン期間中や売上が大きくなる土日の天気によっても売上は変動します。自社の努力以外の天候の要素等で売上高が変動してしまうというところもアパレル業界の特徴となります。
商品の売上の状況により在庫も増減しますが、アパレル企業の在庫は鮮度が重要であることが多く、1シーズン売れ残ってしまうと価値が一気に下落します。そのため、在庫の状況の把握は非常に重要です。滞留在庫の会計処理や、値引き販売時の会計処理、在庫処分時の会計処理は企業により様々であるため、M&Aを検討している場合は、対象の企業がどのような会計処理を選択しているのかを把握して、実態を掴む必要があります。
小売業の場合は、バイヤーは非常に重要な役割を持っており、アパレル企業におけるバイヤーも例外ではなく、むしろ一般的な小売業よりも重要度は高いかもしれません。ある程度の規模のブランドになるとカリスマ性のあるバイヤーが存在することが多く、M&Aを検討する場合にはキーマンとなります。
アパレル小売業では、ブランド別や店舗別、商品別等の売上・損益、KPI指標等基本的な項目を把握しましょう。さらに、アパレル小売業特有の季節性や仕入方式および会計処理を理解した上で実態を掴み、M&Aを成功に導きましょう。

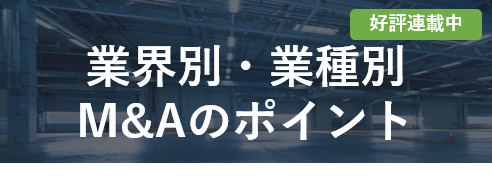


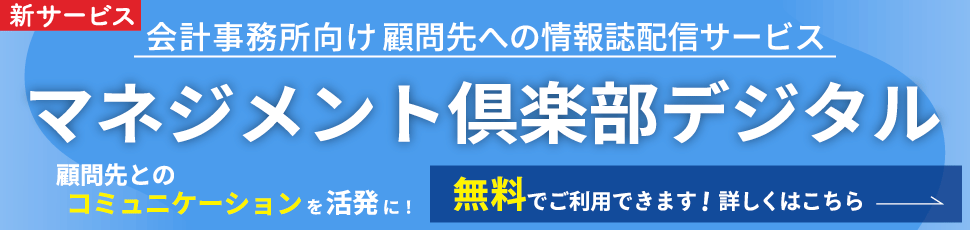


](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/buildings-984195_640.jpg)
![【Q&A】事業譲渡に当たっての適正価額について[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)



.jpg)


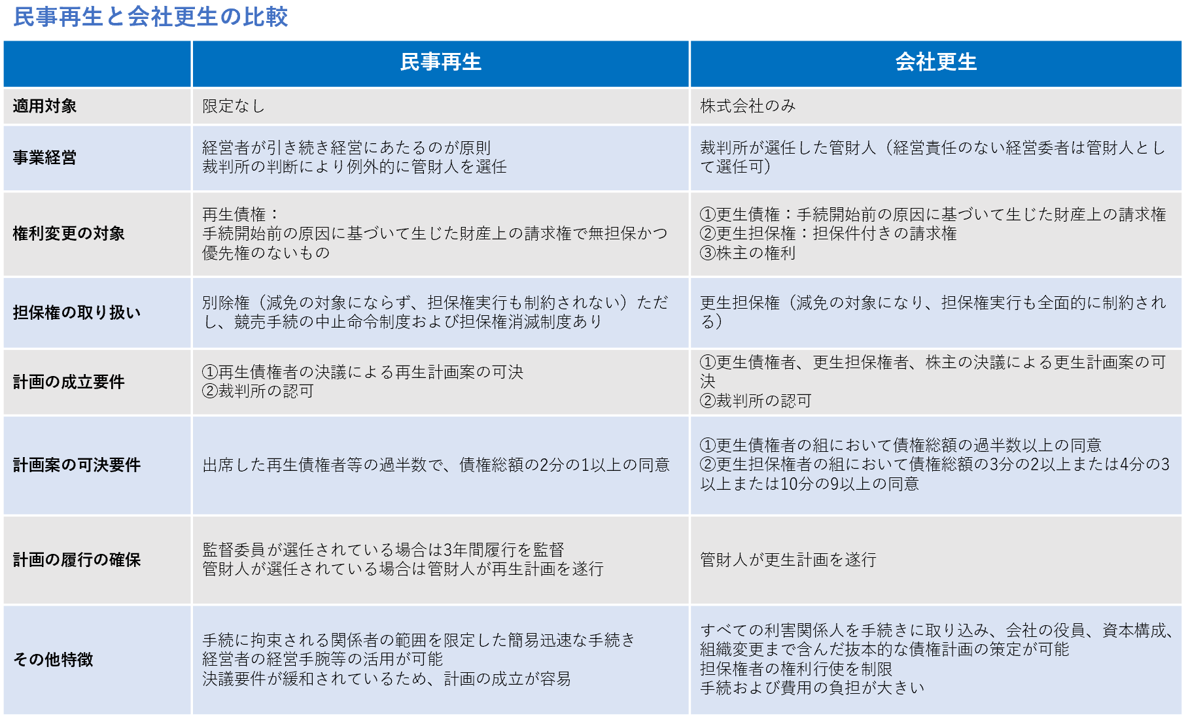
.png)