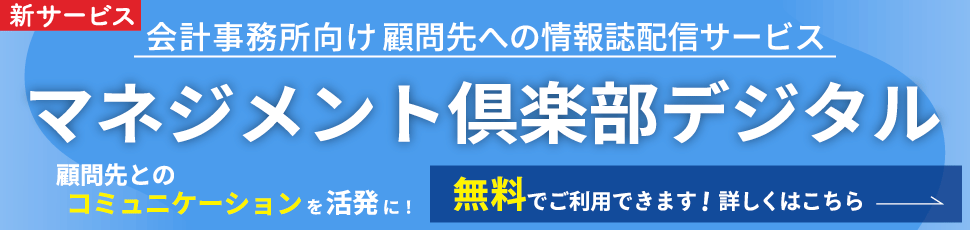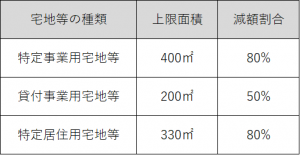[解説ニュース]
評価通達では斟酌できない「特別の事情」による土地評価額の減額のポイント
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)
[関連解説]
■相続時精算課税制度で受贈者が贈与者より先に亡くなってトラブルになった事例
■不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例
1.はじめに
相続で取得した不動産の中には、道路付けの良くない土地や、形状のよくない土地等で、がけ地を含む土地などがみられることもあります。売りに出して売れたとしても、かなり安値になることが不可避な場合、その売却価額でもって相続税評価額として相続税の減額を求めて更正の請求(相続税の申告の減額修正)を税務署長に行う人もいます。しかし、路線価等による評価額よりも売却価額が適正な時価だと認められるのは難しいようです。今回は令和3年5月11日の裁決事例を紹介します。
2.事案の概要
裁決書によると、売却したのは、用途地域が第一種住居地域(建蔽率60%、容積率200 %)と近隣商業地域(建蔽率80%、容積率300%)にまたがっていた借地権で、その形は路地状部分のある旗竿型でした。その借地には貸家が建っておりました。
相続人は相続税の申告において約7,300万円と評価、
した後、この借地権を5,500万円で売却し、すぐに税務署長に対し相続税の申告を直す減額更正の請求をしました。これに対し税務署長は、容積率の異なる2つの地域にまたがっていた点が反映されていなかったことを修正、評価額を約6,780万円に減額しましたが、売却価額を時価とは認めませんでした。そこで、相続人が国税不服審判所(以下、審判所という。)に対して審査請求したものです。
3.審判所の判断
審判所は路線価などに基づく不動産等の評価方法を定めた財産評価基本通達(以下、評価通達という。)について「適正な時価を算定する方法としてー般的な合理性を有するものであり、かつ、当該財産の相続税の課税価格がその評価方法に従って決定された場合には、(中略)評価通達に定める評価方法によって評価するのが相当であり、評価通達に定める評価方法によって評価した価額が当該財産の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができる」との考え方を示しました。
また、この考え方は「評価通達に定める評価方法を画一的に適用することによって、当該財産の「時価」を超えて適正な時価を求めることができない結果となる場合など評価通達に定める評価方法によるべきではない特別の事情がない」ことが前提ということも示し
ました。
そこで審判所は、次のように「特別の事情」があるかどうかを検討しました。
①形状に起因する減価要因が評価通達の定める評価方法では本件借地権の評価に反映されずこれが上記特別の事情に該当するか
評価通達では「土地の形状に起因する減価要因についても、評価する宅地が路線に接している状況、形状等に応ずる評価が行えるよう各種画地調整のための定めを設けることによって考慮している。」ことから本件借地権については、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ定められた補正率を乗じて評価することにより、適切に反映されている
②借地権上の建物の建替えに伴う建築承諾料支払要請や地主からの地代増額要請があることが、評価通達に反映されておらず特別の事情に該当するか
評価通達27の《借地権の評価》では建築承諾料や地代の額も踏まえて決定される借地権の売買実例価額等を基として、一定の地域ごとに適用可能な借地権割合を定めた上、その借地権割合を用いて借地権の価額を算定するとしているため、そのような事情は、評価において考慮されている。
③売却価額が通達評価額を下回ることが特別の事情に該当するか
現実の売却価額は、譲渡時における譲渡当事者間の諸事情を反映して決められるため、そもそも何らの事情補正等を行うことなく、直ちに客観的交換価値を表しているとみることはできない。売却価額が通達評価額を下回っているというのみでは、通達評価額が時価を超えるものということはできない。
上記を踏まえ審判所は、特別の事情はあるとはいえないと判断しています。
4.まとめ
国税当局では、不動産鑑定評価額や売却価額を相続した土地の相続税評価額として申告等するケースを「路線価等によらない事案」と呼んでいます。その場合、前記のとおり路線価など評価通達によって斟酌できない、すなわち適正な時価を算定することができない「特別の事情」があれば、路線価等による評価額以外の価額が認められるとされています。ただ、そうした証拠をそろえることは簡単ではありません。専門家の力を借りることをお勧めします。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/01/26)より転載