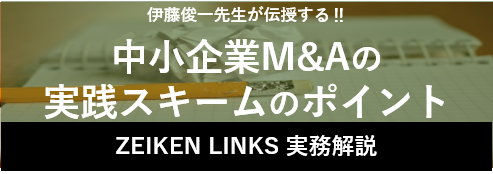[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]
①最終契約書(表明保証条項等)に係る租税法上のアドバイス
〈解説〉
税理士 伊藤俊一
[関連解説]
最終契約書における表明保証条項のドラフティングは通常、弁護士が行います。しかし、全ての弁護士が租税法を詳細まで理解しているとは考えにくいため、以下の事項につき税理士の視点から租税法上のアドバイスをする必要性が生じます。
ただし、現在、中小零細企業のM&Aは売手市場であり、下記のような買主が有利な契約は現実的に合意に至りにくいこと、通常は売主側(の代理人弁護士、FA等)が先に最終契約書のドラフティングを行うこと、また、株式譲渡契約等における租税補償条項を設けることは我が国では未だ一般的ではないこと[注1]等諸事情から、下記ではあくまでも買主における最終契約書の理想像を述べています[注2]。
なお、本稿の対象読者層を想定して、理論的見解や参照裁判例等は極力注釈に記載し、本文中は、筆者の実務家としての現場での所感を示していることをご理解ください。
①補償金の税務上の取扱い
クロージング後、売主に表明保証違反があった場合、買主は損失につき補償条項に係る損害賠償請求をします[注3]。売主は損害賠償請求に係る金額を支払い、買主は当該補償金を受け取ります。売主の支払額は法人税基本通達2-2-16により支払事業年度の損金の額に算入されます[注4]。一方で、補償金を受け取った買主の受取額には、以下の2つの考え方があると言われています[注5]。
(イ)買主が損害賠償金を受け取ったとする考え方
・・・この考え方に立つと、法人税法第22条第2項、法人税基本通達2-1-43により、当該支払いを受けるべきことが確定した日(又は実際に支払いを受けた日)の属する事業年度において益金に算入されることとなります[注6]。
(ロ)買主に当初譲渡代金が(一部)返還されたとする考え方
・・・当初譲渡代金が返還されただけなので課税関係は生じないこととなります。
この点、平成18年9月8日裁決[注7]において、株式譲渡契約書に補償金の支払は譲渡代金の減額である旨を明記していた結果、益金に算入されないと判断された事例があります。この裁決以降、実務では表明保証条項に補償金の支払は減額である旨を明記する事例が増加しています(ただし、これはあくまで裁決であり判例ではないため、当該裁決をもって補償金の返還が譲渡代金の減額と判断する拠り所とはなり得ません[注8])。
買主における予防策として考えられることは、最終契約書(表明保証条項等)に「補償金は譲渡代金の減額」である旨を明記しておくこと、また、上記(イ)の考え方により、仮に当該補償金に益金課税された場合においては、「当該課税相当額も買主における損失」と考え、最終契約書(表明保証条項等)にその旨を明記しておくことです。
なお、売主においては、補償金が損金算入された結果、課税所得が圧縮され法人税額等が減少することになりますが、「当該法人税額等減少額を損失から控除する」と最終契約書(表明保証条項等)に明記した方がよいでしょう。
①~④において共通ですが、表明保証には「存続」という概念があり[注9]、実務では当該条項も当然付しますので、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ませんので留意してください。
②繰越欠損金の減少は買主の損失に該当するか
対象会社においてクロージング日時点、繰越欠損金を有していたとします。クロージング日後、対象会社に税務調査が入り、結果、修正申告対象になったとします。その場合、対象会社の繰越欠損金は修正申告における課税所得増加相当額だけ減少します。
この場合、
(イ)繰越欠損金>課税所得増加相当額
・・・会社からのキャッシュアウトは生じない。
(ロ)繰越欠損金<課税所得増加相当額
・・・会社からのキャッシュアウトが生じる。
となります。
最終契約書(表明保証条項等)において、買主における損失の定義が曖昧のままでは、上記(ロ)のように買主において、「キャッシュアウトが生じて初めて損失」とも捉えることも可能となります。損失の定義が売主と買主間で齟齬が生じる(典型的な)場面となりますから、最終契約書(表明保証条項等)で上記(イ)、(ロ)のどちらを指しているか予め明示しておく必要があります。買主では、上記(イ)が有利となります。
なお、税務調査は定期的にありうるものから、調査状況によっては、将来的には上記(ロ)になり得ますが、上述の通り、存続が終われば補償請求等の対象にはなり得ません。
③源泉徴収不納付又は過少納付は買主の損失に該当するか
対象会社においてクロージング日以降、源泉徴収不納付又は過少納付が発覚したとします。この場合、源泉徴収不納付額又は過少納付額は徴収者(クロージング日後は買主)が受給者(対象会社において源泉徴収不納付額又は過少納付額が生じていた者)に対し求償できる(所法222)ため、買主の損失にあたらないと考えます。ただし、不納付加算税及び延滞税(国通法67、60①五)などの附帯税は求償権の範囲にあたらないため[注10]、買主の損失にあたると考えます。
附帯税はもちろん、実務上極めて稀なケースと想定されますが、受給者の資力喪失等により、求償権が行使できない可能性もあるため、源泉徴収不納付額又は過少納付額についても、最終契約書(表明保証条項等)に損失であることを明記しておくべきです。
①~③に共通して、売主が連結納税制度(本稿脱稿時点、令和2年度税制改正によりグループ通算制度に改正予定)を採用している場合、別の手当が必要となりますが、中小零細企業においては非常に稀なケースと想定されますので、本稿での解説は割愛します。
④第2次納税義務は表明保証条項で担保されない
中小零細企業M&Aにおいては、いわゆる不動産M&Aに限定されると考えられますが、会社分割後に株式譲渡を実行する場合もあります[注11]。当該株式譲渡におけるクロージング日時点においては分割承継会社に第2次納税義務は生じません。第2次納税義務は国税徴収法基本通達32条関係1等による各種要件を満たした後に初めて生じるものであり、クロージング日「時点」の潜在債務が存在しないという表明保証条項では担保できません[注12]。表明保証条項は予測に関して一切担保できないものとされます。
以上、主に買主視点にたった表明保証条項の租税法に係る留意点を列挙しました。しかし、現実的には、中小零細企業において表明保証条項(及び補償条項)は極めて実効力に乏しいため、各種デュー・デリジェンスで発覚する懸念事項のインパクトが大きいと想定される場合は、譲渡代金減額、分割払い(アーンアウトまたはクローバックという意味ではなく、文字通りの意味において、ただし税務上の取扱いに留意が必要です)、エスクロー(信託課税の問題があるため留意が必要です。中小零細企業M&Aにおける利用は皆無と想定されます)で対応するべきです。また、筆者は契約中止(破談)がベストと考えます。
【注釈】
[注1] 一般的でない、という見解は、藤原総一郎=大久保涼=宿利有紀子=笠原康弘=大久保圭「M&Aの契約実務」P201(中央経済社 第2版 2018)を参照しています。この点、森・濱田松本法律事務所=MHM税理士事務所 (編)「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」(商事法務2018)P448~449において、「表明保証違反に基づく補償履行請求権が私法上どのような性質を有すると考えるべきであるかについて、統一的な見解は現時点では存在しない」とあり、租税補償の取扱いについて法曹でも見解が分かれていることが、未だ一般的でない原因と考えます。
[注2] 上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P445~P450、森・濱田松本法律事務所(編)「税務・法務を統合したM&A戦略」P22~P28、P95~P97(中央経済社 第2版 2015)を参照しています。
[注3] 補償については上限額を設定するのが通常です。
[注4] この点につき、佐藤友一郎 (編)「法人税基本通達逐条解説」P292 (税務研究会出版局 九訂版 2019)において「法人税の所得計算における損益の認識は、ひとり民事上の契約関係その他の法的基準のみに依拠するものではなく、むしろ経済的観測に重点を置いて当期で発生した損益の測定を行うことになるのである。このような考え方からすれば、契約解除等に伴う損失を当期の損失として処理することはむしろ当然」とあります。
[注5] 上掲注2「税務・法務を統合したM&A戦略」P25を参照しています。
[注6] 最判昭和43年10月17日判決(集民第92号607頁)、東高平成21年2月18日判決参照のこと。
[注7] 裁決事例集72号325頁(国税不服審判所ホームページ http://www.kfs.go.jp/service/JP/72/19/index.html)参照のこと。
[注8] この点、上掲注1「設例で学ぶオーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務」P449において「法基通7-3-17の2が固定資産について同様の処理を是認していることが参考になる」との見解もあります。
[注9] この点、上掲注1「M&Aの契約実務」P170~P171において存続について「「本契約に基づく表明及び保証は、クロージング日以降3年の間に限って存続する」という規定は「クロージング以降3年間に限り表明保証違反に基づく補償請求等が可能であることを意味している」とあります。
[注10] 最判昭和45年12月24日判決(民集第24巻13号2243頁)参照のこと。
[注11] 平成20年10月1日裁決(裁決事例集76号573頁 国税不服審判所ホームページ http://www.kfs.go.jp/service/JP/76/33/index.html)参照のこと。
[注12] この点につき、第2次納税義務については、別途、特別な条項が必要なことについて、小山浩「企業実務上留意すべき重要租税判決の解説」P318以下(租税研究764号(2013))を参照のこと。また、特別補償を設けることも実務では考えられますが、上掲注1「M&Aの契約実務」P279~P280において「税務の取扱い(・・・筆者中略・・・)などの法令の解釈や事実認定が分かれ得るような論点については、特別補償の規定を定めること自体が対象会社による違法行為を認めるような外見になりかねない」との見解もあり、現実的に設定は困難と考えられます。
![最終契約書(表明保証条項等)に係る租税法上のアドバイス[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/pencil-1891732_640.jpg)