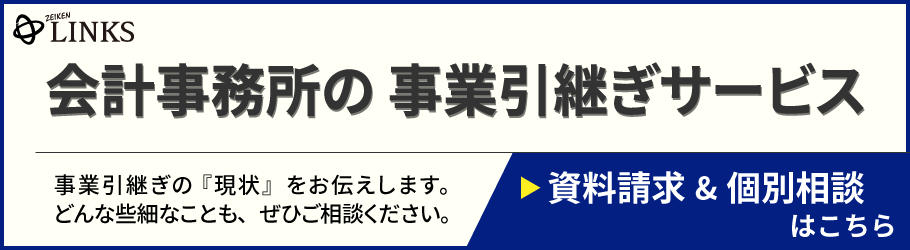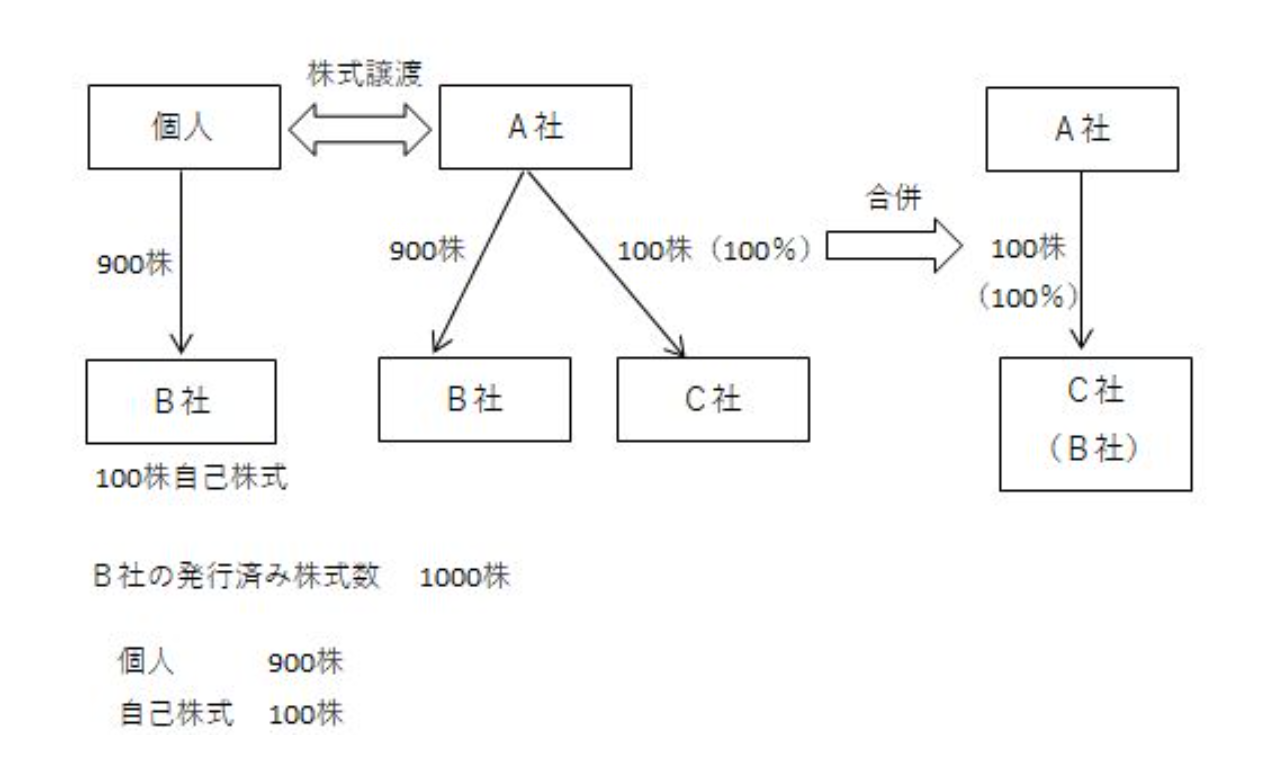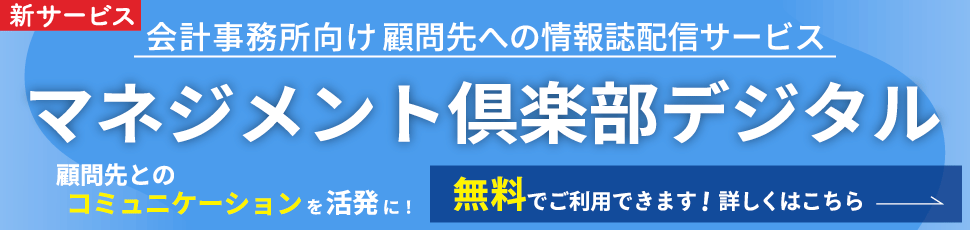[税理士のための税務事例解説]
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「従業員である相続人に退職金を支払った場合の債務控除の可否」についてです。
[関連解説]
■【Q&A】個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係
[質問]
被相続人甲は、2020年2月に死亡しました。
相続人は甲の事業を承継しないこととし、甲が雇用していた全ての従業員を解雇し、退職金を支払います。甲が雇用していた従業員の中には、甲の相続人である乙も含まれています。
被相続人の死亡によって事業を廃止し、従業員を解雇していることから、乙以外の従業員に対して支払う退職金については、甲の相続税申告に当たって債務控除の対象になると考えます。
しかし、乙に対して支払う退職金については、相続税法第13条の規定により債務控除の対象とならないとの認識でよいでしょうか。
[回答]
個人事業者が死亡し、その事業を相続人が承継せず廃業したときに、当該個人事業者が雇用していた従業員に対して退職金を支払った場合、その退職金は相続税の債務控除の対象になる旨の質疑応答事例が国税庁ホームページに掲載されていますが、これはご承知のことかと思います。
この質疑応答事例によると、「その支給された退職金は、被相続人の生前事業を営む期間中の労務の対価であり、被相続人の債務として確実なものであると認められる」との考え方の下、債務控除することが可能との取扱いを明らかにしています。
ところで、ご質問の事例の乙への退職金については、乙が被相続人甲の相続人であることから、相続税法第13条の規定により債務控除の対象とならない、とのご見解のようですが、債務控除の対象になるとする考え方は、上記のとおり、被相続人が事業を営んでいる間の労務の対価であるかどうかがポイントですから、乙が実際に従業員として勤務した事実があれば、相続人(家族従業員)であるか否かは関係しませんし、相続税法第13条の規定をみても、相続人に対する債務を債務控除の対象から除外する規定もありません。
確かに、家族・相続人に対する支払いや債務ということだと、例えば、所得税法第56条のように、生計を一にする親族に労務の対価等を支払った場合は必要経費に算入しないという規定がありますし、民法上、相続人が積極財産と債務を承継した場合、混同により債務が消滅するということもありますので、第三者の場合とは異なるところがあるのではないかという疑問も生じるかも知れませんが、こと相続税の債務控除については、相続人乙に勤務実績があって、他の従業員と同様の基準等により退職金が支払われる限り、債務控除の対象にして差し支えないものと考えます。
税理士懇話会事例データベースより
(2020年6月3日回答)
[ご注意]
掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。
![【Q&A】従業員である相続人に退職金を支払った場合の債務控除の可否[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)




![【Q&A】税理士事務所の事業承継と一時払金の処理 ~のれん(営業権)となるかどうかとその処理について~[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/tree-736888_1280.jpg)