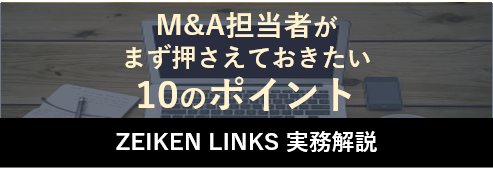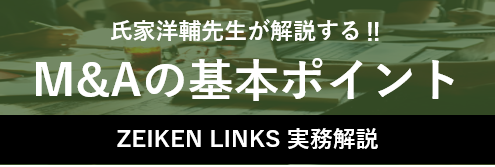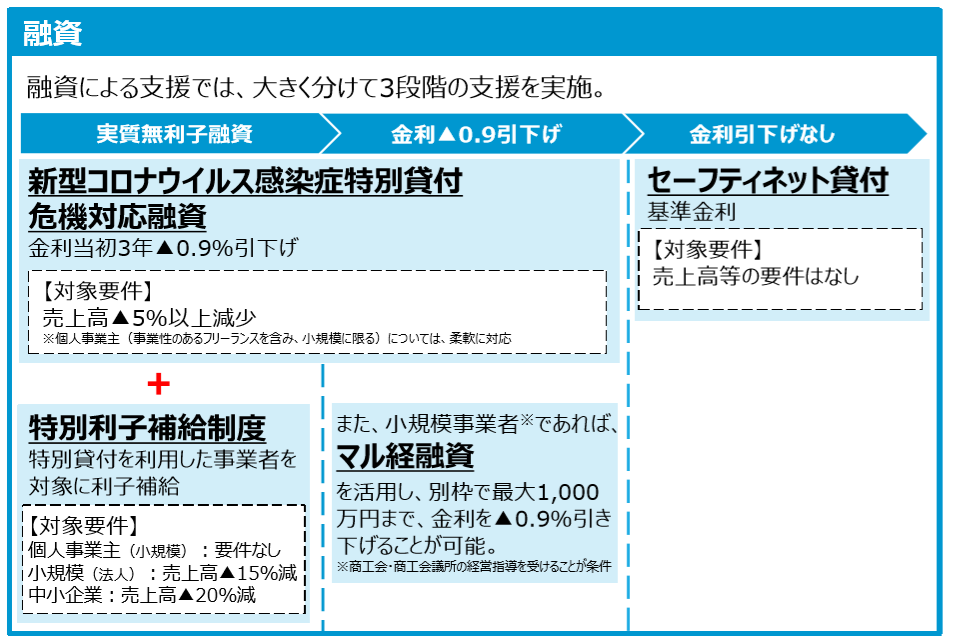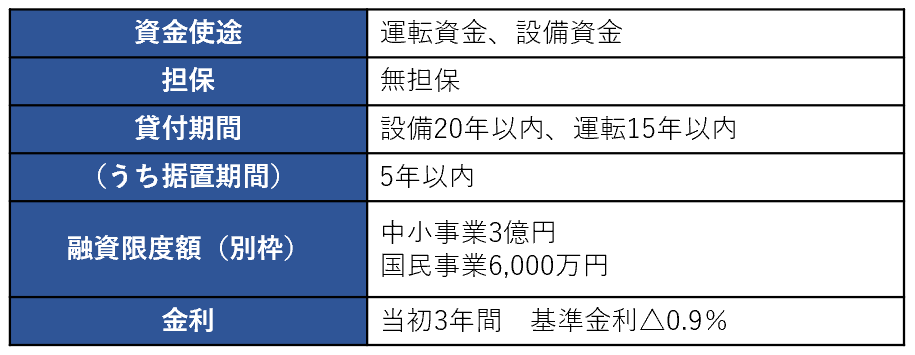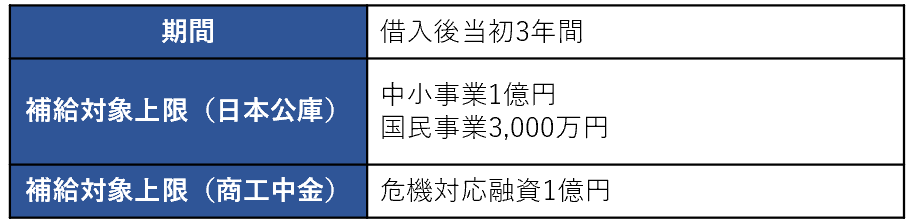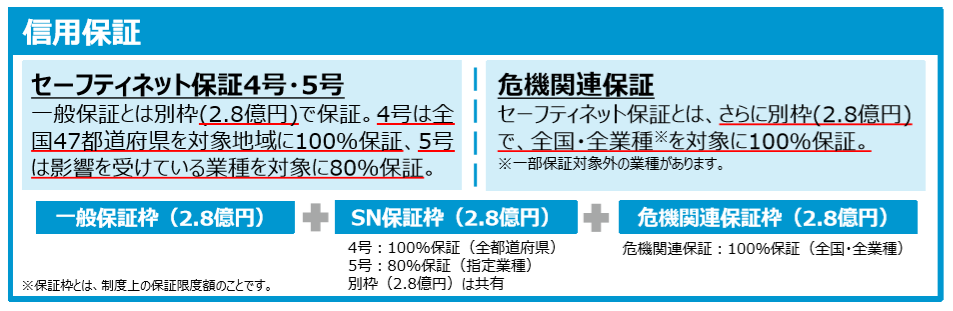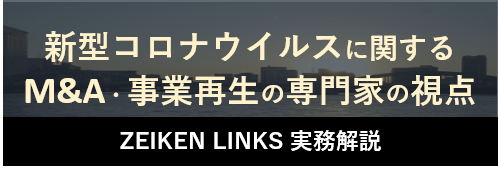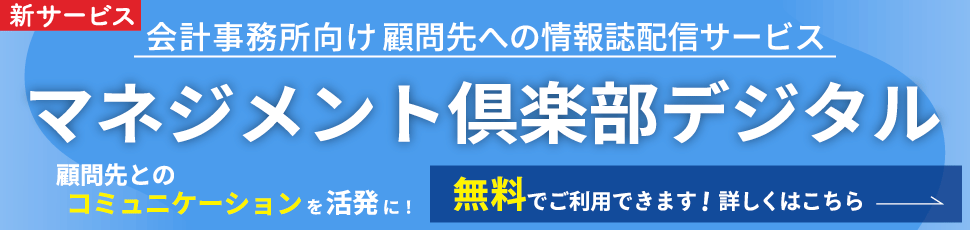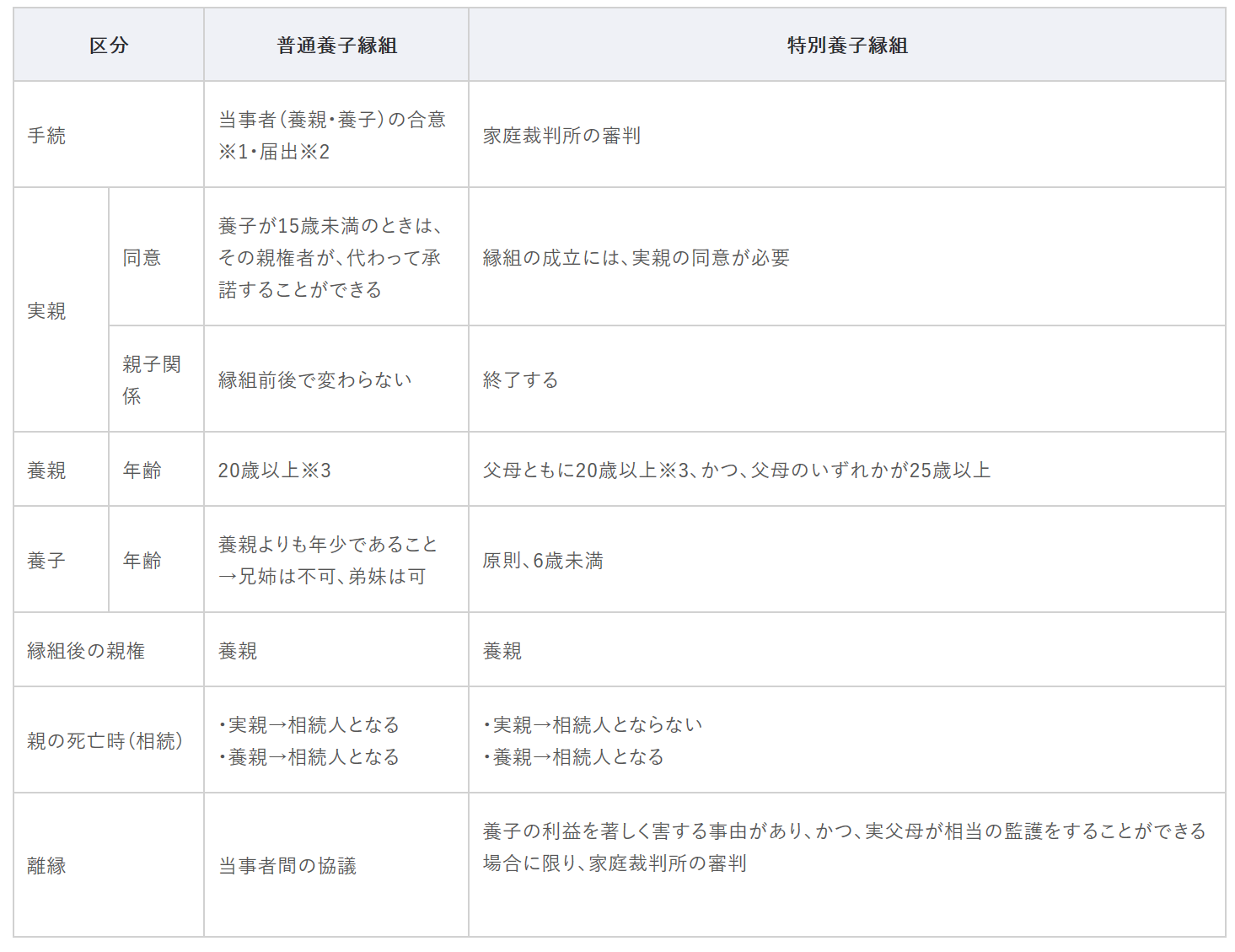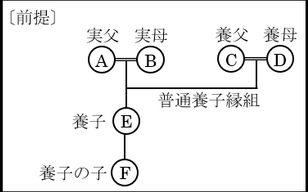[税理士のための税務事例解説]
事業承継やM&Aに関する税務事例について、国税OB税理士が解説する事例研究シリーズです。
今回は、「事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定」についてです。
[関連解説]
■【Q&A】取得した株式の取得価額と時価純資産価額に乖離がある場合
[質問]
法人が他の法人から、太陽光発電設備、当該設備設置土地の前払賃料、電力会社に対するFIT(固定価格買取制度)の権利を含め、『太陽光発電事業の事業譲渡』として譲り受けることになりました。
他の法人側からは機器設置代金や前払賃料が示されていますが事業譲渡総額とはかなりの差異が生じており、当該差額は固定買取単価の高いFITの権利が譲渡に含まれているためと理解しています。
当該権利については営業権として5年償却とすべきか、繰延資産としてFITでの固定買取期間(20年)にわたって償却を行うべきか判断に迷っております。
[回答]
法人が非適格合併等(非適格合併又は非適格分割、非適格現物出資、事業の譲受け(その事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が移転するもの)をいいます)により、その非適格合併等に係る被合併法人等からその資産又は負債の移転を受けた場合において、その法人が非適格合併等により交付した非適格合併等対価額がその移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超えるときは、その超える部分の金額は資産調整勘定とされ、その資産調整勘定の金額は60か月で取り崩しをし、損金の額に算入することとされています(法62の8①④⑤)。なお、この資産調整勘定の金額は税制上の取扱いであることから損金経理要件が課されるものではありません。
ご照会事例における事業譲渡が、譲渡法人の事業譲渡直前において行う事業の譲渡であり、その事業譲渡により主要な資産・負債を一体として移転を受けた場合で、その事業譲渡対価額が経済的合理性のある価額である限りは、法人が交付した事業譲渡対価額が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超える部分の金額は、資産調整勘定の金額(会計上の「のれん」)として税務処理をすることになります。
ところで、営業権とは、一般に超過収益力(その企業が同種他企業の平均収益力を超える場合のその超える収益力)を有する無形の財産価値といわれています。
本件の場合に、法人が承継した事業について超過収益力があり、かつ、営業権の対価としての計算に合理性があるときは、個別の無形固定資産(営業権)として計上することができますが、ご照会文面から推察する限りにおいては、営業権としての個別の資産の移転があったとは言い難いと考えられます。
したがって、本件については、事業譲渡対価額が移転を受けた資産・負債の時価純資産価額を超える部分の金額を資産調整勘定の金額として税務処理するのが相当と考えます。
税理士懇話会事例データベースより
(2020年2月18日回答)
[ご注意]
掲載情報は、解説作成時点の情報です。また、例示された質問のみを前提とした解説となります。類似する全ての事案に当てはまるものではございません。個々の事案につきましては、ご自身の判断と責任のもとで適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い申し上げます。
![【Q&A】事業譲渡により移転を受けた資産等に係る調整勘定[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)





![M&A における株式評価方法と中小企業のM&A における株式評価方法 ~中小企業M&Aで最も用いられている仲介会社方式とは?~ [税理士のための中小企業M&Aコンサルティング実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/business-2173147_640.jpg)
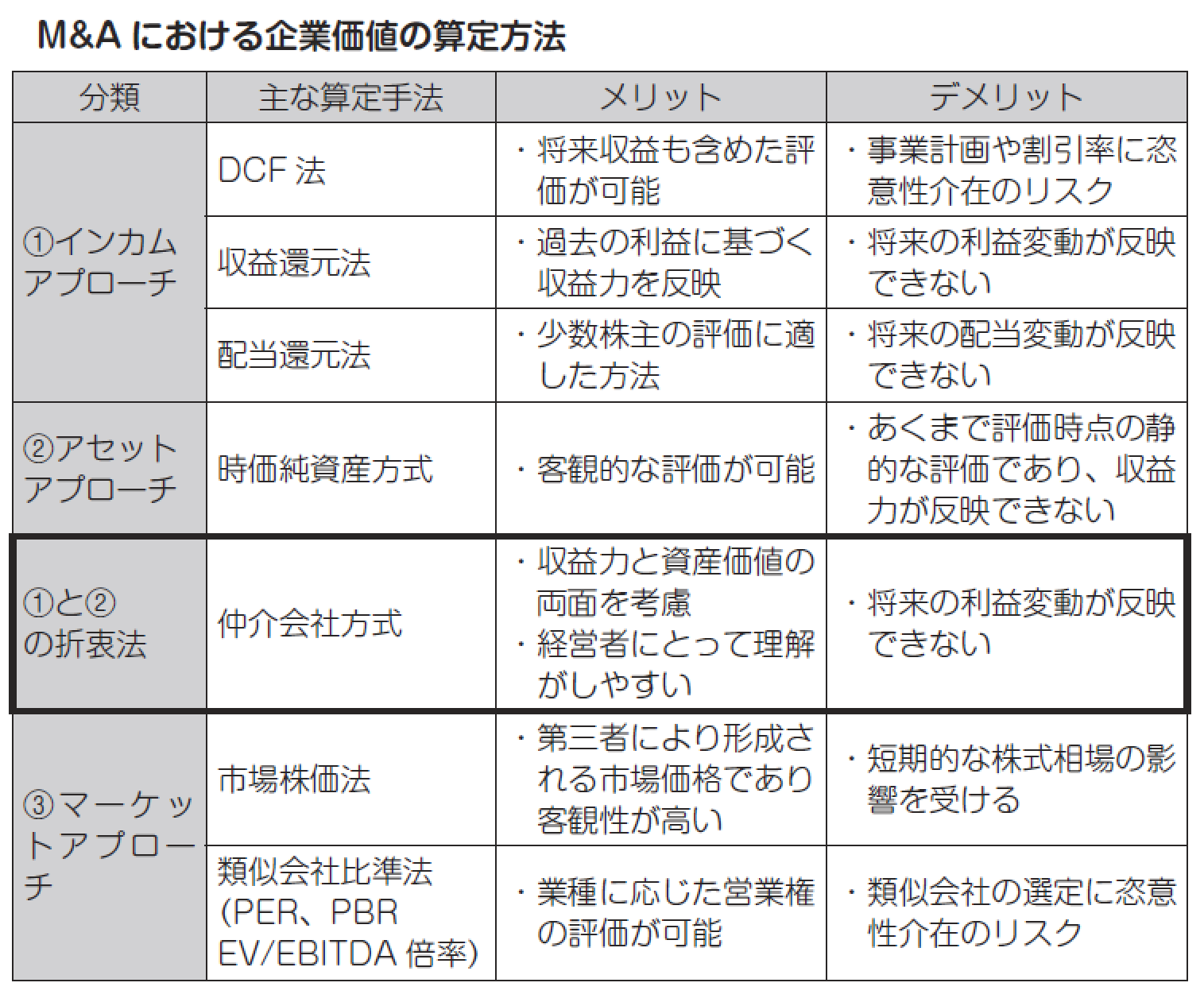
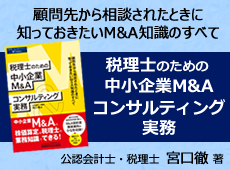


![M&A関連費用の取扱い[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/pencil-1891732_640.jpg)
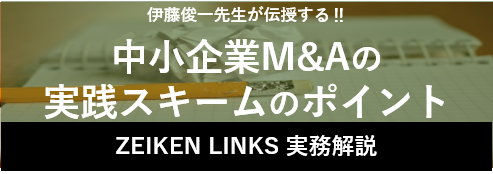
![PPAにおける無形資産の認識プロセスとは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/business-1477601_640.jpg)






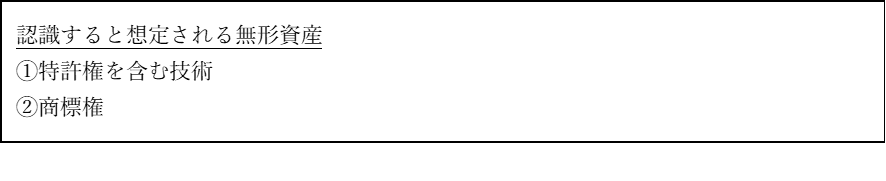

![デューデリジェンスとは?-各種DDと中小企業特有の論点-[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/home-office-336378_640.jpg)