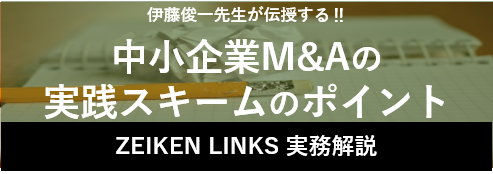プレM&Aにおける株式譲渡スキームを採用した場合の、売主株主における少数株主からの株式買取(スクイーズアウト)に係るみなし贈与[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]

- 解説コラム
- 連載
[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]
③プレM&Aにおける株式譲渡スキームを採用した場合の、売主株主における少数株主からの株式買取(スクイーズアウト)に係るみなし贈与
〈解説〉
税理士 伊藤俊一
[関連解説]
中小零細企業M&Aにおいては、株式譲渡スキームを採用する際、ほとんどのケースで、買主は売主の株式を100%取得します。公開企業M&Aのような段階取得、支配権を維持するだけの取得等はありません(仮に売主株式を100%取得しなかった場合、クロージング日以後も、旧売主株主として残存している者から、会社法上の少数株主で認められる各種権利を行使して、いわゆる嫌がらせを受ける可能性があるため)。
このため、プレM&Aの段階で下記のように少数株主から株式を集約する必要があります。なお、筆者は会社法上規定されている各種スクイーズアウトは中小零細企業実務においては機能しないという所感があるため、下記では相対取引での株式集約を指していることをご理解ください。
売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的です。親会社においては配当、または、自己株式取得に係るみなし配当のいずれであっても、受取配当の益金不算入がありますので(所有割合によって変わりますが、原則として)課税は生じません。したがって、当該配当後の分配可能限度額を超過した残りの部分を売却します。
なお、売主株主が個人の場合は、当該配当が配当所得として総合課税の洗礼を受けることになり、税負担が重くなるため実行しません。
上記における自己株式取得において既存子会社における少数株主からの買取に関して、論者によっては相続税基本通達9-2が適用される、との見解も散見されます。すなわち、少数株主からの買取金額(こちらを1,000円とする、税務上適正評価額)とM&A時の譲渡対価の額(こちらを10,000円とする)に差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解です。
筆者はみなし贈与は適用されない見解をとっています。上記は一連の取引ではないからです。少数株主からの買取を行う場合、上記では税務上適正評価額を採用しています。取引はそこで分断されます。その後、全く別の取引として、第三者に対してM&Aを行っています。M&Aにおける株式譲渡対価について租税法上の法文等が適用される余地はありません[注1]。
売主株主が個人の場合でも上記と同様です。売主会社(対象会社)の少数株主からの買取に関して、上記でいうところの差額(10,000円-1,000円=9,000円)があれば、その差額相当額はみなし贈与ではないか、という見解ですが、上記と同様のロジックで、みなし贈与にはあたりません。
上記2つとも、少数株主からの買取価格は税務上適正評価額で行っていると前提においています。この評価額の算定根拠は通常取引(親族間での相対取引等)の株価算定と同様に必要です。
なお、上記論点が実務で当局から指摘されたという事例は、筆者自身も経験がありませんし、これまで周囲からも聞いたことがありません。
なお、「売主株主が法人である場合、子会社を株式譲渡スキームでM&Aをする際には、譲渡対価の一部を子会社から親会社へ配当、もしくは、自己株式取得をさせる場合が一般的」については今後、下記の点に留意が必要です。
令和元年12月12日に発表された「令和2年度税制改正大綱」87頁以降において「五 国際課税 1 子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避への対応 (1)法人が、特定関係子法人から受ける配当等の額(その事業年度開始の日からその受ける直前までにその特定関係子法人から受ける配当等の額を含む。以下「対象配当金額」という。)が株式等の帳簿価額の10%相当額を超える場合には、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を、その株式等の帳簿価額から引き下げることとする。」とあります。
【注釈】
[注1] この点につき、代表的な文献として、佐藤友一郎 (編著)「法人税基本通達逐条解説」798頁(九訂版 税務研究会出版局 2019)(法人税基本通達9-1-14(いわゆる小会社方式)の解説において)「ただし、純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額は、たとえ上記したところと異なる価額であっても、一般に常に合理的なものとして是認されることとなろう」とあります。第三者M&Aにおける譲渡価額は典型的な「純然たる第三者間において種々の経済的合理性を考慮して定められた取引価額」に該当します。そもそもこの考え方は、当局が納税者が私的自治の原則に基づき選択した取引に対して、いかなる場合にもおいても租税法上の評価(取引相場のない株式であれば財産評価基本通達)に引き直すのは、取引自体に干渉していることになることから、経済的中立を逸脱することとなり許されないとの指摘もあります。この点につき、茂腹敏明「非上場株式鑑定ハンドブック」460頁(中央経済社 2009年)参照のこと。