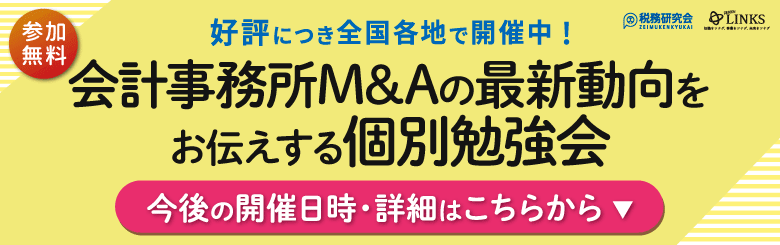[M&A案件情報(譲渡案件)](2024年5月8日)
-以下のM&A案件(9件)を掲載しております-
●【中国地方】地域トップクラスの売上・実績を誇る総合広告代理店
[業種:広告代理店業/所在地:中国地方]
●日常・定期清掃を中心とするビルメンテナンス会社
[業種:ビルメンテナンス/所在地:関東地方]
●【大手製造業メーカーなどに実績あり】関東エリア中心の人材派遣業者
[業種:労働者派遣業/所在地:関東地方]
●当該地域においてトップクラスの業歴と顧客基盤を有する食品卸業者
[業種:食品卸業/所在地:四国地方]
●【財務良好】クリニックと介護サービスを展開
[業種:無床診療所/所在地:関西地方]
●スクリーン印刷用資機材販売・製版、サインディスプレイ企画・制作業を行う。
[業種:スクリーン印刷用資機材販売・製版業/所在地:関東地方]
●【老舗企業】家電のEC販売、好立地に不動産保有。
[業種:電気機械器具小売業/所在地:関西地方]
●大規模工場を有し、研磨・めっき加工業を展開する老舗企業
[業種:自動車部分品・付属品製造業/所在地:中部地方]
●大手優良顧客を有し、電子部品加工業を展開する老舗企業
[業種:電子回路基板製造業/所在地:中部地方]
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
(お問い合せ・ご相談は「無料会員登録」が必要です)
案件No.SS016085
【中国地方】地域トップクラスの売上・実績を誇る総合広告代理店
(業種分類)出版・印刷・広告
(業種)広告代理店業
(所在地)中国地方
(直近売上高)10~50億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)独立系広告代理店として地域でトップクラスの売上・実績。
[特徴・強み]
◇長年の業歴を有し、無借金経営を継続し、毎期利益蓄積ができている。
◇WEB事業が成長しており、ソーシャルメディア運用も実施。・対象会社のみ取扱可能な媒体が多数あり、顧客からの信頼を獲得。
◇取引先に地場大手優良企業が多数あり。
◇事業セグメントはマスメディア関連約30%、交通・看板系広告約40%、WEB広告約20%、その他約10%。
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.No.SS015929
日常・定期清掃を中心とするビルメンテナンス会社
(業種分類)ビルメンテナンス
(業種)ビルメンテナンス
(所在地)関東地方
(直近売上高)1~5億円
(従業員数)50~100名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)日常清掃と定期清掃を中心としたビル管理業務および産業廃棄物処理業務(収集運搬)を主事業とし、マンション管理、汚水槽・貯水槽清掃業務、排水管洗浄業なども併営。
[特徴・強み]
◇無借金経営であり、業歴長く内部留保が厚い
◇既往の主要取引先との取引歴も長く、受注安定
◇収益性についても毎期安定して黒字を計上している
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS015664
【大手製造業メーカーなどに実績あり】関東エリア中心の人材派遣業者
(業種分類)人材派遣・アウトソーシング
(業種)労働者派遣業
(所在地)関東地方
(直近売上高)1~5億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)大手電子機器メーカーなどと取引ある製造業向け人材派遣会社
[特徴・強み]
◇取引先に電子機器メーカーや食品メーカーを有する。高い従業員定着率を誇る。
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS014778
当該地域においてトップクラスの業歴と顧客基盤を有する食品卸業者
(業種分類)外食・食品関連
(業種)食品卸業
(所在地)四国地方
(直近売上高)50~100億円
(従業員数)50~100名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)四国地を中心に、食品卸業を展開。
[特徴・強み]
◇小麦粉、砂糖、食油をはじめとする総合食品卸売業者。
◇特約メーカーを豊富に取り揃え、顧客のニーズに応じた商品提案が可能。
◇四国を中心に、強固な取引基盤を構築。
◇三温度帯(冷蔵、冷凍、常温)での配送体制を有する。
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS013818
【財務良好】クリニックと介護サービスを展開
(業種分類)介護・医療
(業種)無床診療所
(所在地)関西地方
(直近売上高)5~10億円
(従業員数)100名超
(譲渡スキーム)出資持分譲渡
(事業概要)クリニックと介護サービスを運営。
[特徴・強み]
◇好立地
◇医療/介護の連携を行い利用者様に喜ばれている
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS012665
スクリーン印刷用資機材販売・製版、サインディスプレイ企画・制作業を行う。
(業種分類)出版・印刷・広告
(業種)スクリーン印刷用資機材販売・製版業
(所在地)関東地方
(直近売上高)10~50億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)スクリーン印刷用資機材販売・製版、サインディスプレイ企画・制作・施工業を行う。
[特徴・強み]
◇スクリーン印刷業界では老舗であり、高いネームバリューを誇る
◇同業が多く廃業しており、残存者利益を獲得
◇足元も順調であり、仕事は増えている状況
◇後継者不在により譲渡を希望
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS012461
【老舗企業】家電のEC販売、好立地に不動産保有。
(業種分類)小売業
(業種)電気機械器具小売業
(所在地)関西地方
(直近売上高)10~50億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)家電商品のEC販売を運営。
[特徴・強み]
◇業歴長く安定した経営
◇商品の仕入に強みを持つ
◇好立地の不動産保有
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS010683
大規模工場を有し、研磨・めっき加工業を展開する老舗企業
(業種分類)製造業
(業種)自動車部分品・付属品製造業
(所在地)中部地方
(直近売上高)1~5億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)自動車及び二輪部品をメインとして研磨・めっき加工を行う老舗企業
[特徴・強み]
◇大規模な工場を所有するとともに長年の歴史で培った高い技術力を強みとしている。
◇取引先からの評判は高く、取引先も多岐にわたっている。
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
案件No.SS008725
大手優良顧客を有し、電子部品加工業を展開する老舗企業
(業種分類)製造業
(業種)電子回路基板製造業
(所在地)中部地方
(直近売上高)1~5億円
(従業員数)10~50名
(譲渡スキーム)株式譲渡
(事業概要)電子部品の基盤実装や組立、検品作業を手掛ける老舗企業
[特徴・強み]
◇主力取引先は大手優良企業。
◇豊富な設備と技術力のある職人が社内に多数在籍していることが強み。
-案件に関するお問合せ・ご相談は、このページ文末の「お問合せ・ご相談」ボタンより-
情報提供会社:株式会社ストライク

【免責事項】
・掲載情報は、内容及び正確さに細心の注意をはらい、万全を期しておりますが、人為的なミスや機械的なミス、調査過程におけるミスなどで誤りがある可能性があります。税務研究会及び情報提供会社は、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負うものではありません。
・掲載情報は公開日時点の情報になります。既に案件が特定の対象会社と交渉に入っている場合や成約している場合もございます。
お気軽にお問合せください
](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/202602_jigyoukaisyama_ai-1200x797.png)



![【Q&A】M&A後の会社に従業員として勤務する元役員に係る給与[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)
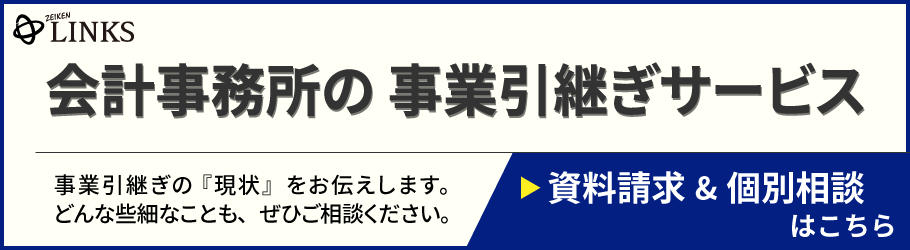



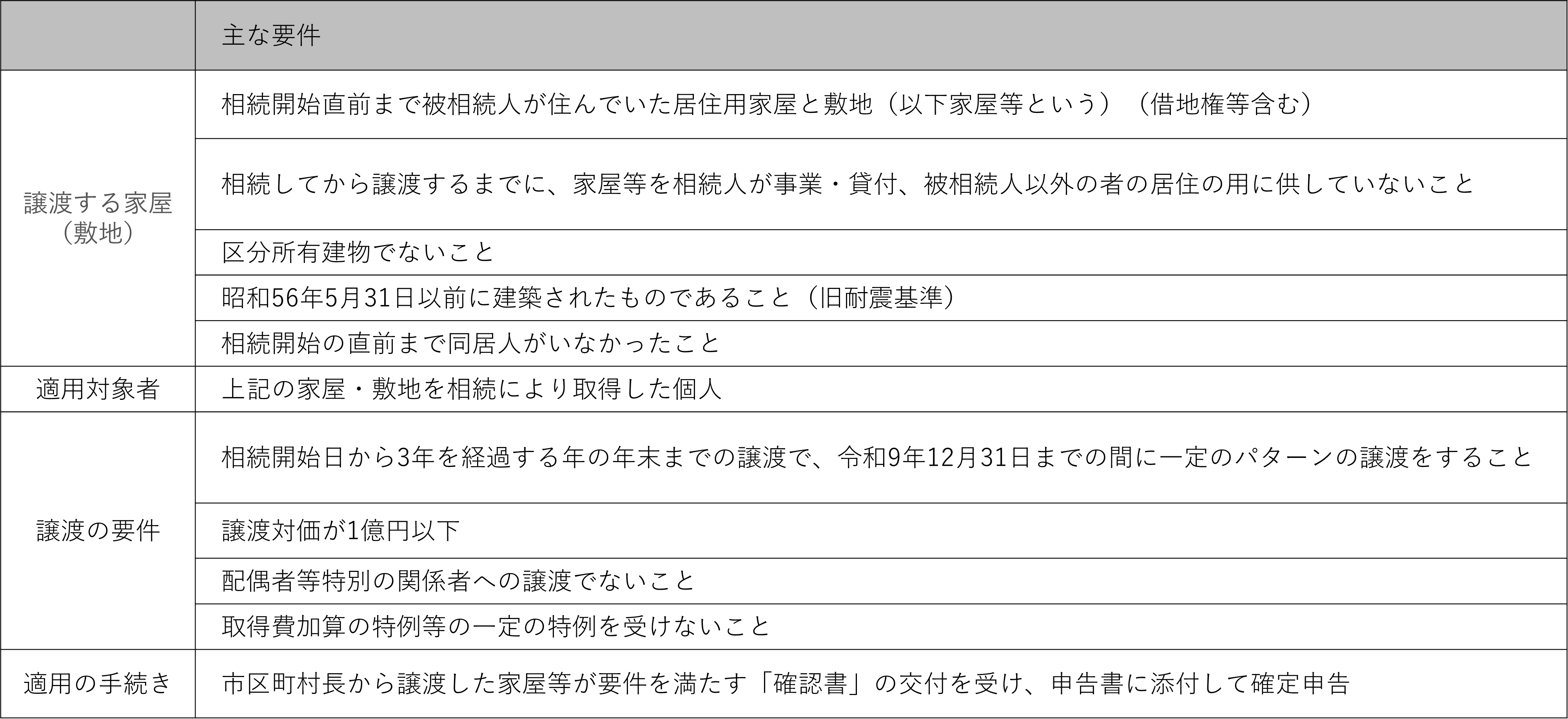
![どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/smallma-1.png)