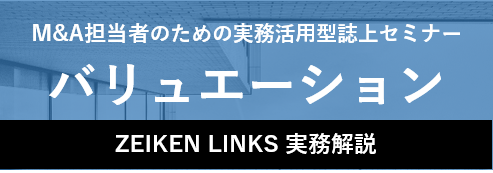[業界別・業種別 M&Aのポイント]
第9回:「民泊運営事業者のM&Aの特徴や留意点」とは?
~どの法律に基づいて運営しているか?物件は所有か賃貸か?物件オーナーとの契約内容は?~
〈解説〉
▷関連記事:「産業廃棄物処理業のM&Aの特徴や留意点」とは?
Q、民泊運営事業者のM&Aを検討していますが、民泊運営事業者M&Aの特徴や留意点はありますか?
民泊運営事業者が民泊事業を行うには、旅館業法簡易宿泊営業、特区民泊、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)のいずれかに従う必要があります。2018年6月に住宅宿泊業法(民泊新法)が施行されたことにより、これまで民泊運営を行ってきた事業者の多くが事業を見直すきっかけとなりました。住宅宿泊業法(民泊新法)では、年間営業日数が180日以内という制限が課されたため、180日の営業では利益が出しづらく事業としては成り立たないケースがほとんどとなったためです。
事業として行うには、旅館業法簡易宿泊営業又は特区民泊のどちらかにて営業を行うことが考えられます。旅館業法簡易宿泊営業および特区民泊では住宅宿泊事業法(民泊新法)に比べ遵守事項が多く、特に通常の住宅設備では消防法の遵守事項を達成できないケースが多く民泊事業を続けることを断念した事業者も多くいました。

そのため、まずはM&Aを検討している会社がどの法律に基づいて運営しているのかを把握する必要があります。そして、物件を所有しているのか、賃借しているのか、或いはオーナーから民泊運営のみの委託を受けているのかについて把握しましょう。これにより固定資産の有無や、損益分岐点が大きく異なってきます。また、運営委託を受けている場合は、物件のオーナーとの契約関係が非常に重要な事項であるため、契約書は必ず確認しましょう。
民泊事業者の主な収入はインターネットの旅行サイト等からの収入であり、その収入に応じて支払手数料を支払っています。主な費用はこの支払手数料と、物件の清掃費、人件費、その他外注部分があればその外注費等です。
コロナ禍で、外国人観光客の減少によりインバウンドの産業が厳しい状況の中、民泊事業も厳しい状況となっており、今後M&A案件が増加する可能性もあるため、民泊事業の特徴や留意点を把握しておきましょう。

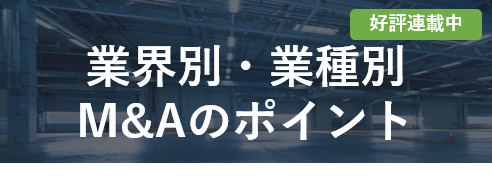


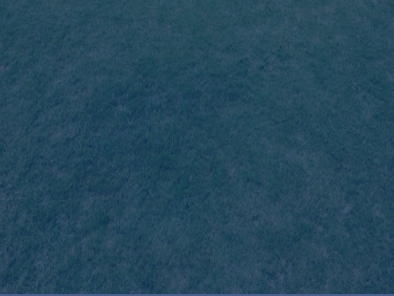





![M&Aの譲渡対価とその後の処遇 ~譲渡対価の計算方法は?~[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/会計事務所-事業承継MA.png)
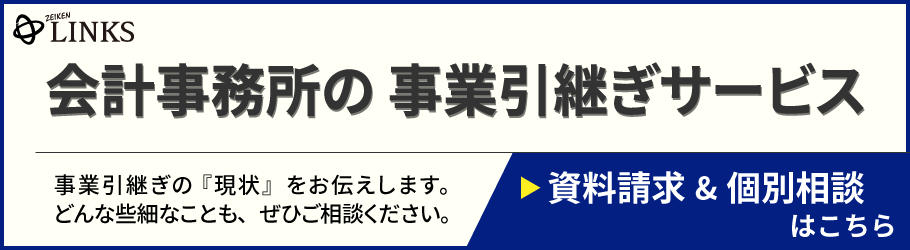
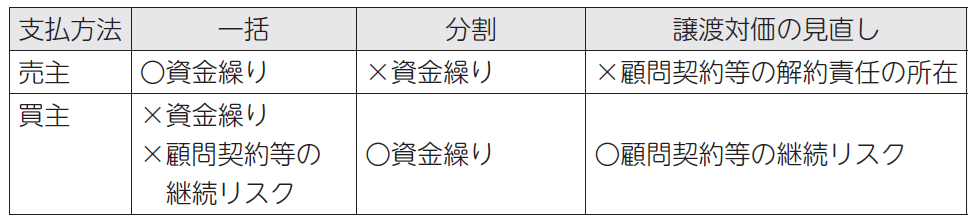
.png)
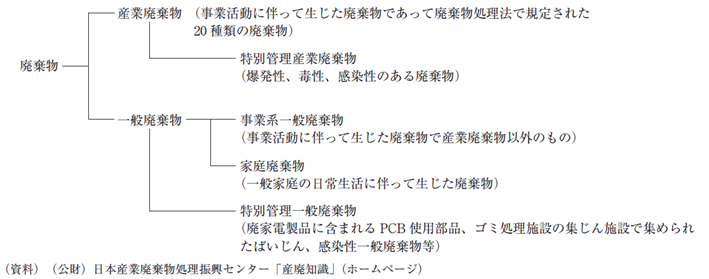
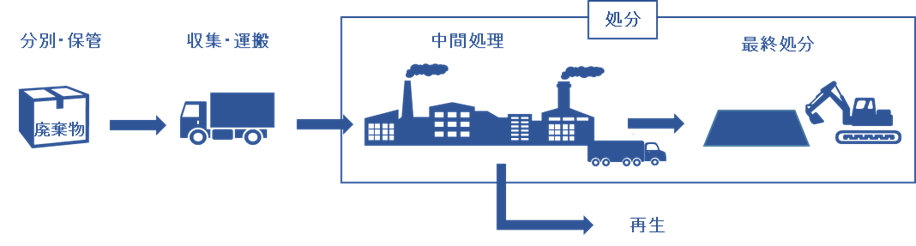
①.png)
②.png)
③.png)
④.png)
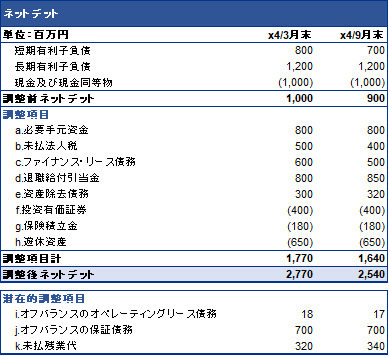
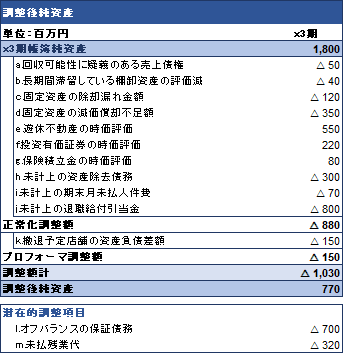
.png)

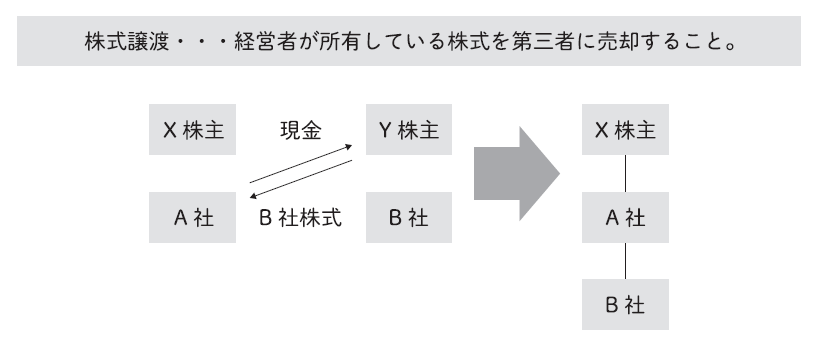
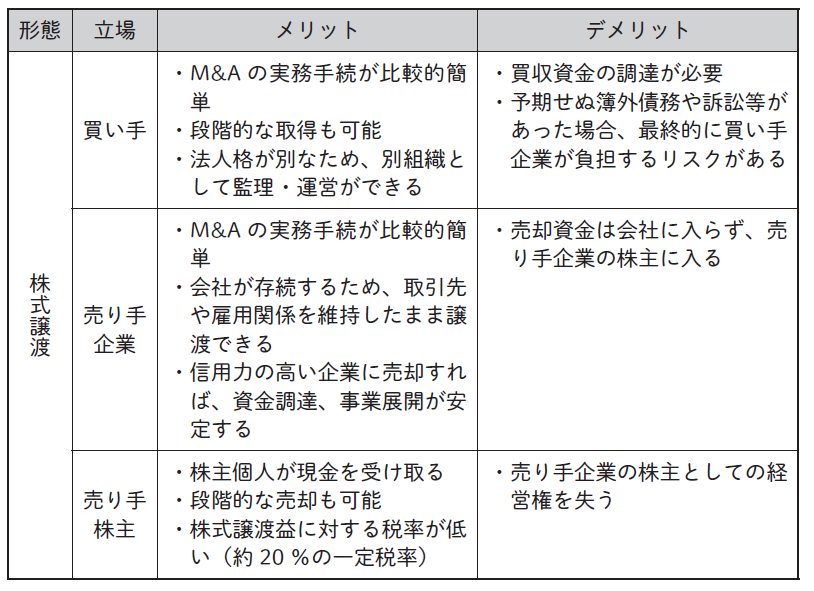
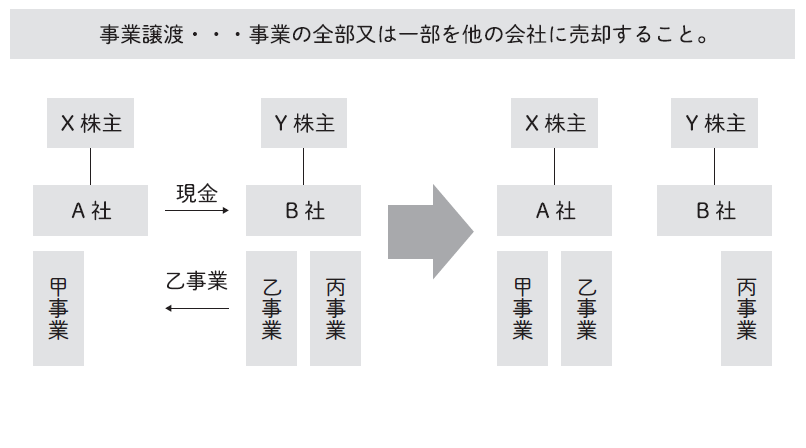
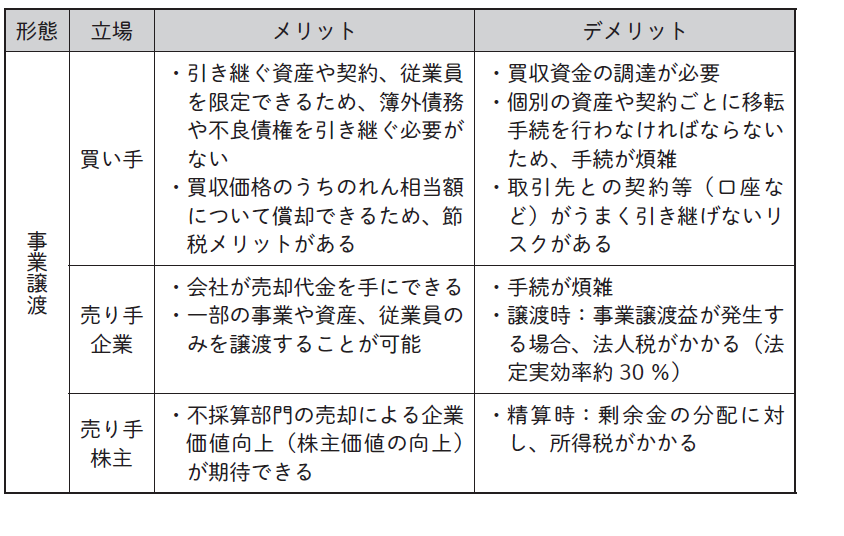
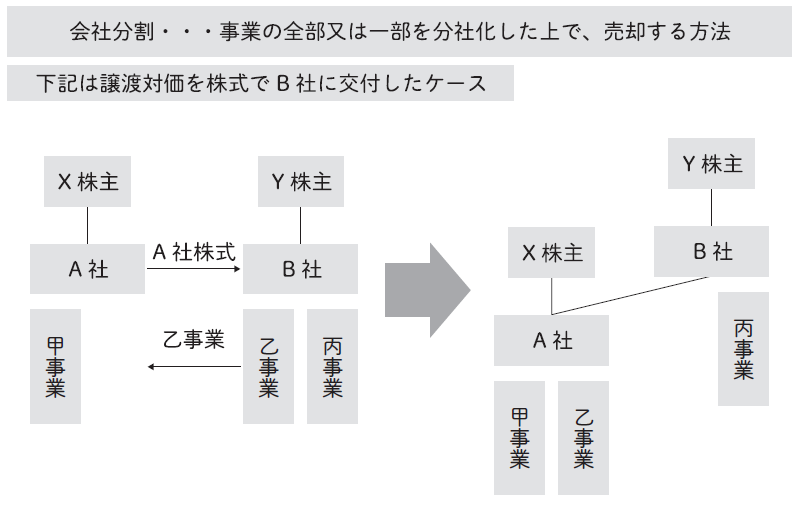
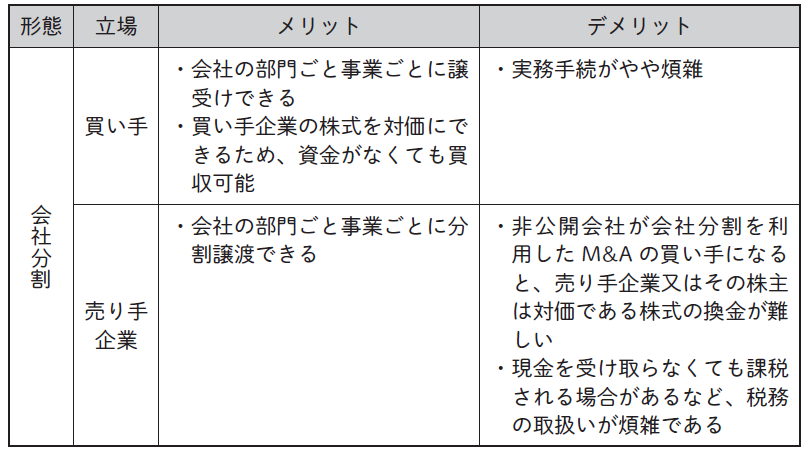
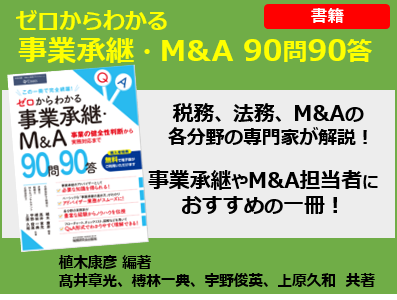

.jpg)
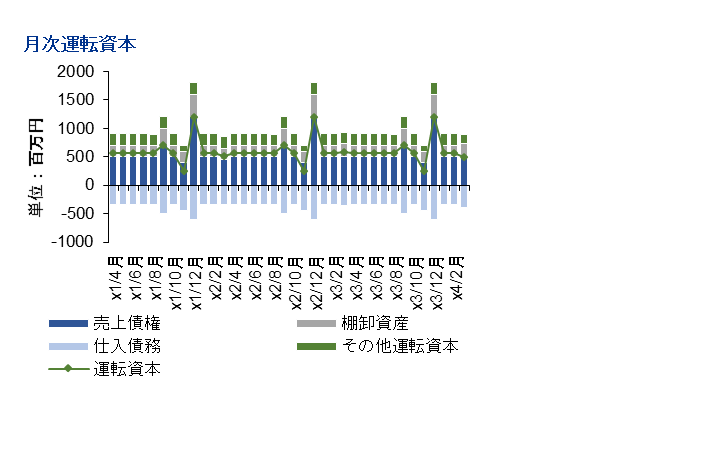
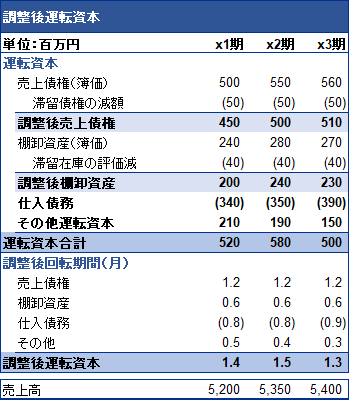
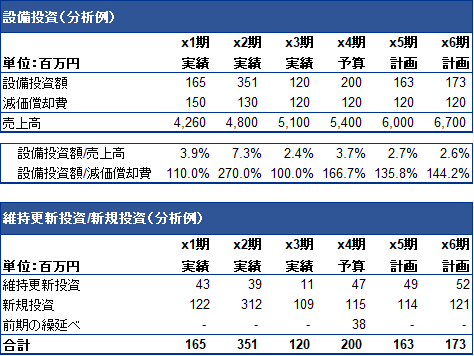
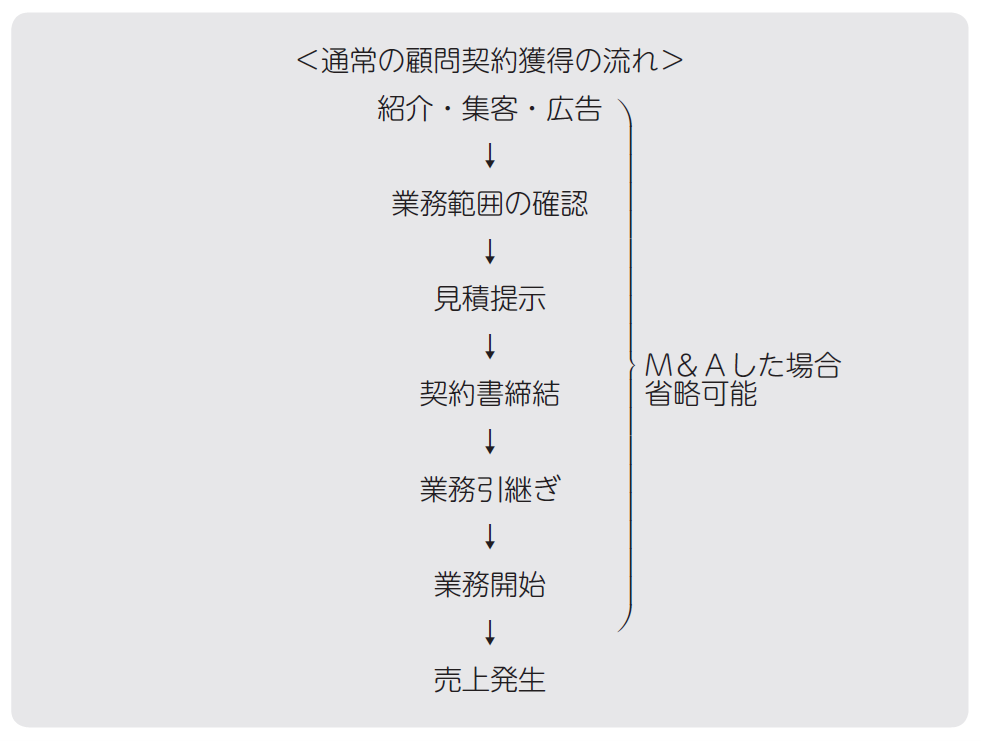
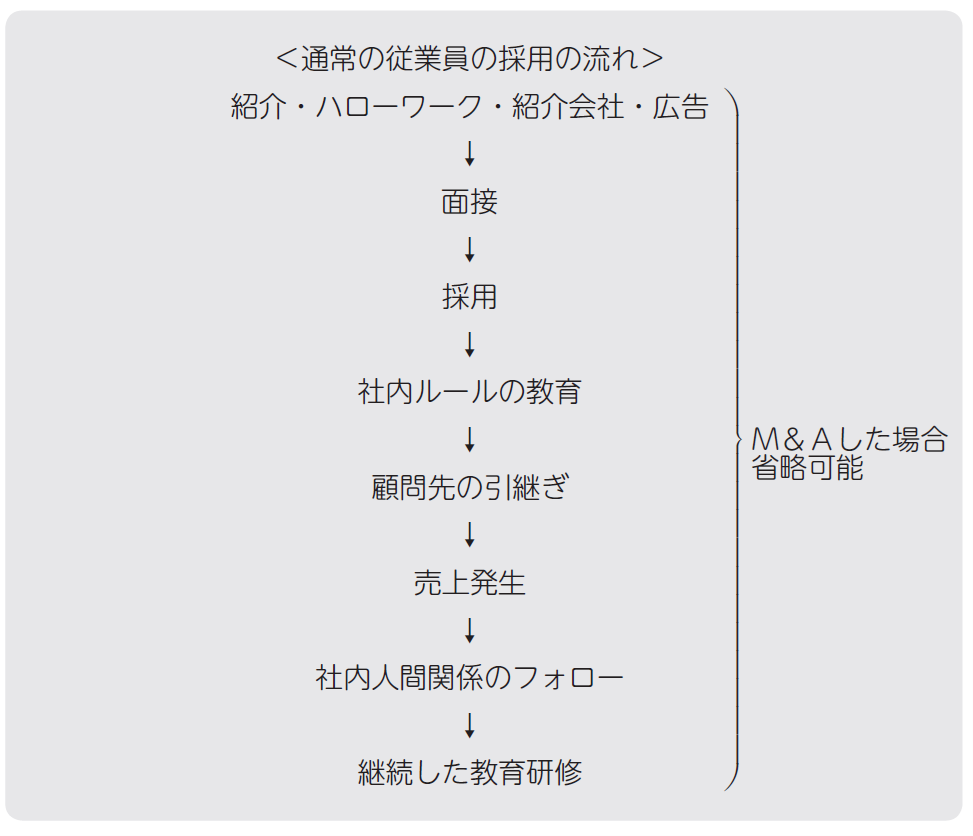
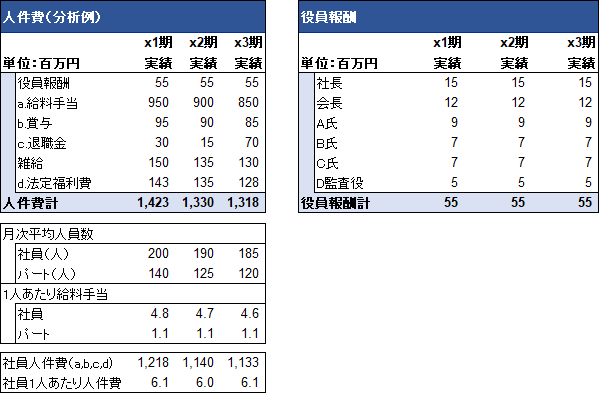
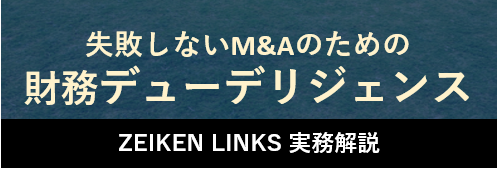
①.png)
②.png)
③.png)
④.png)