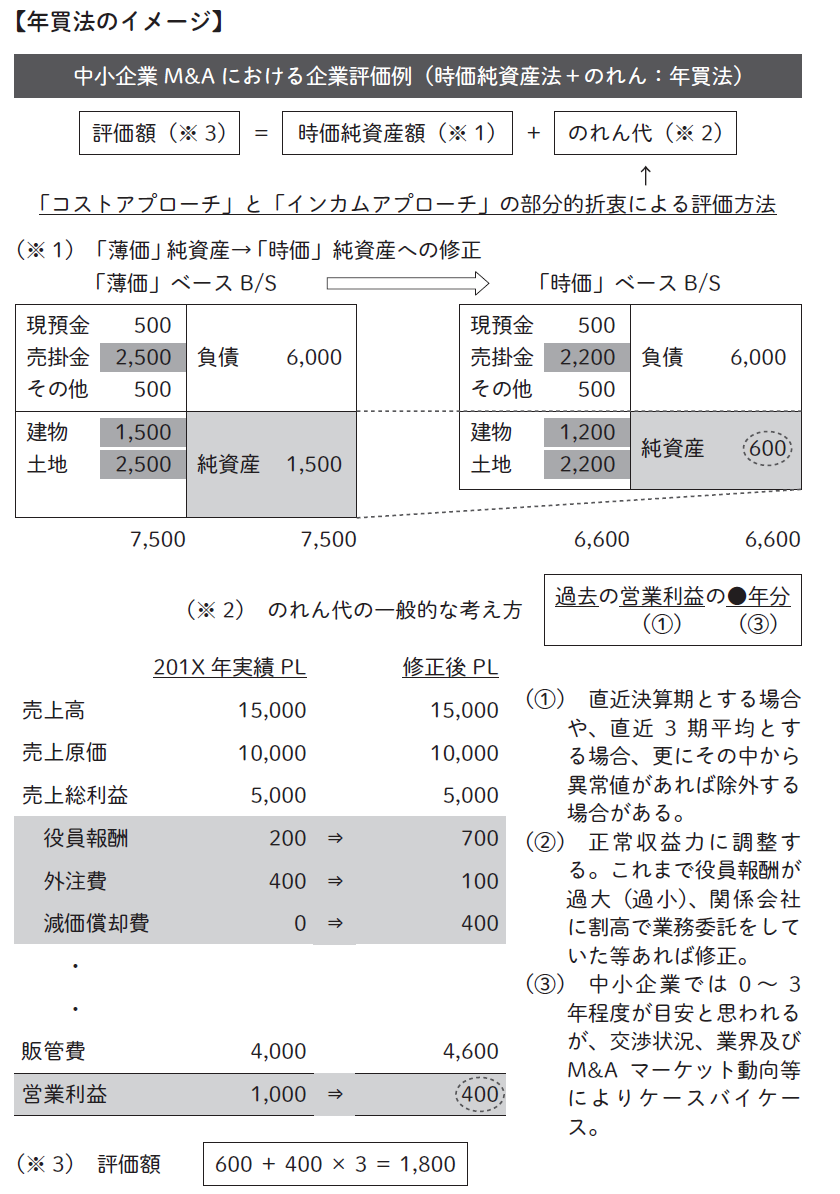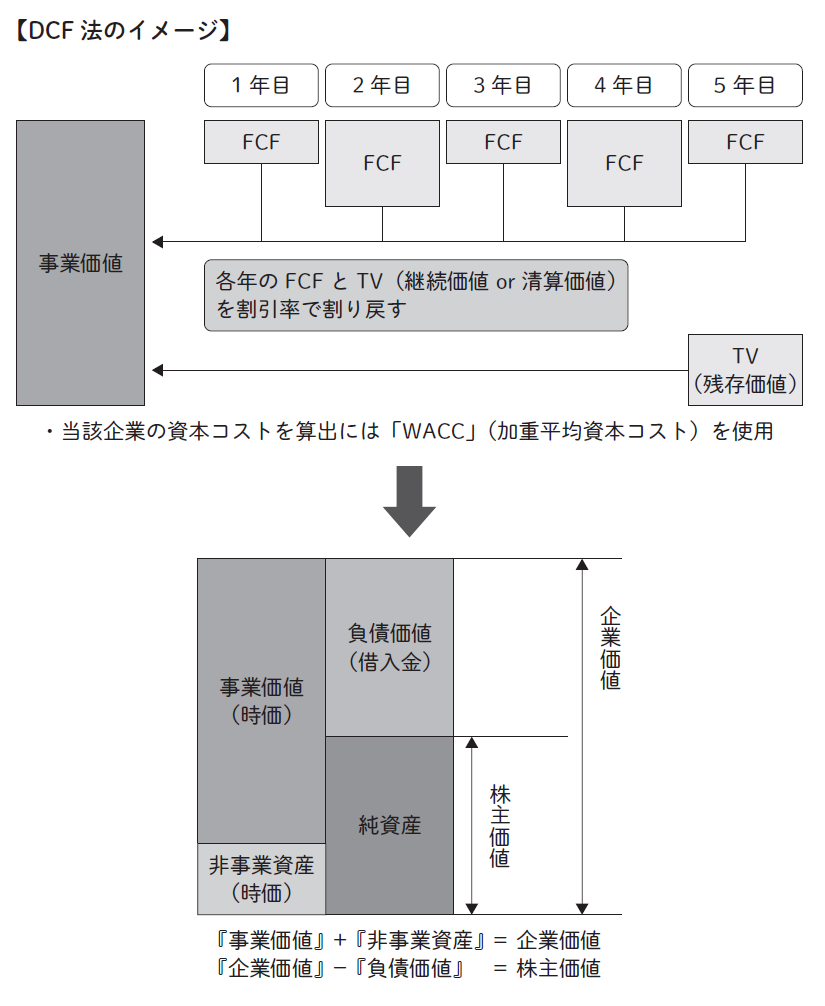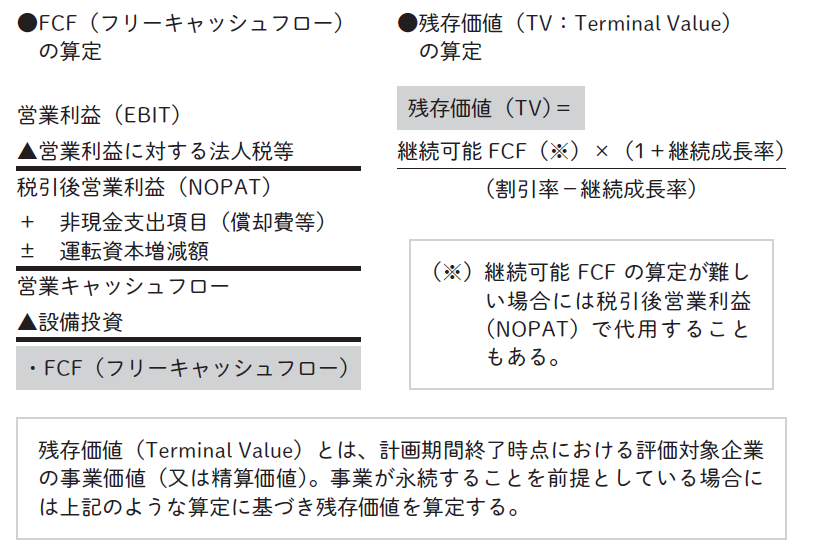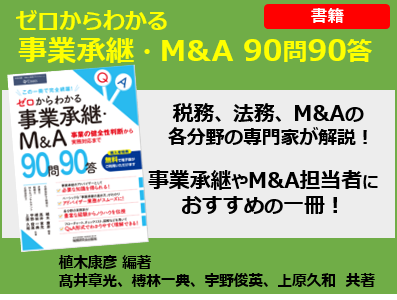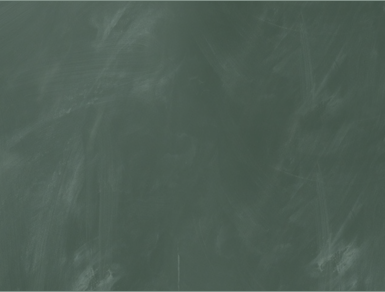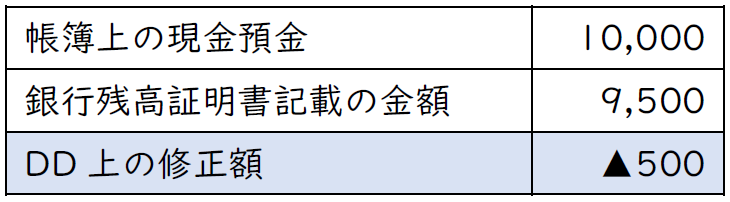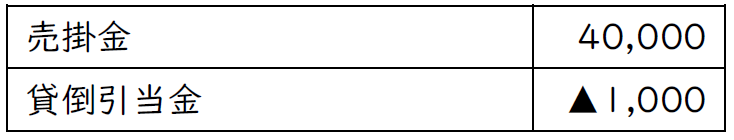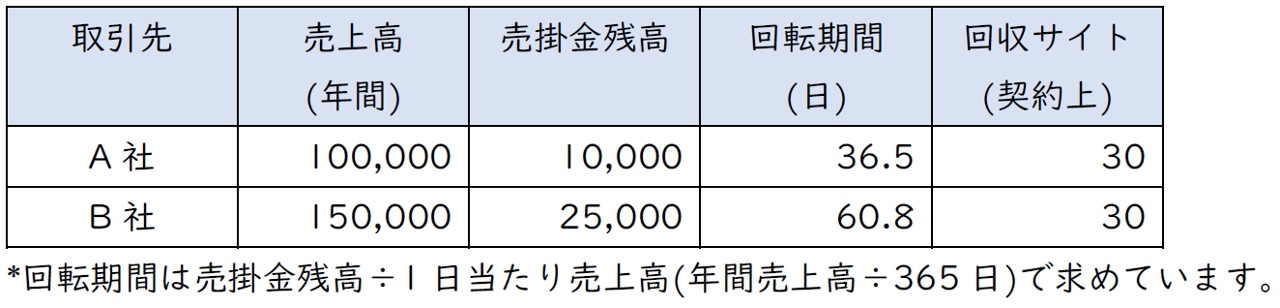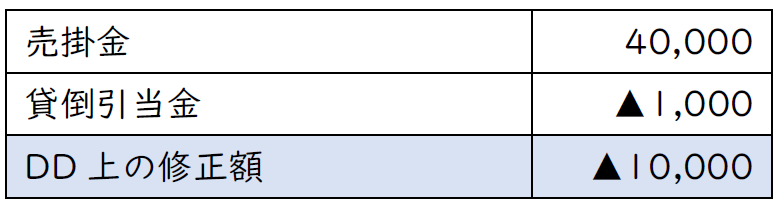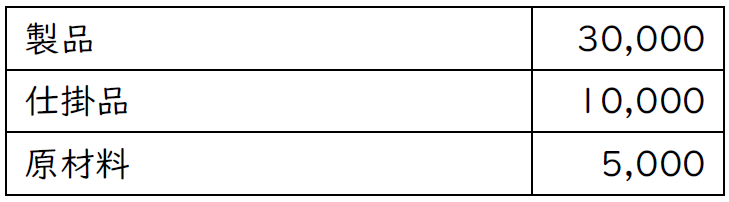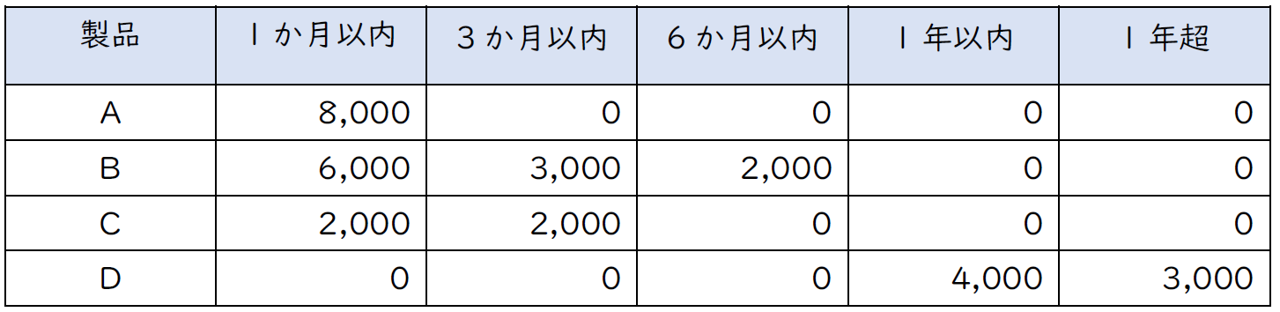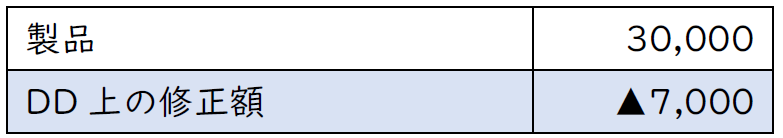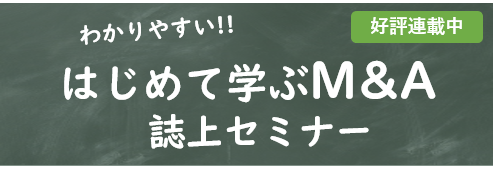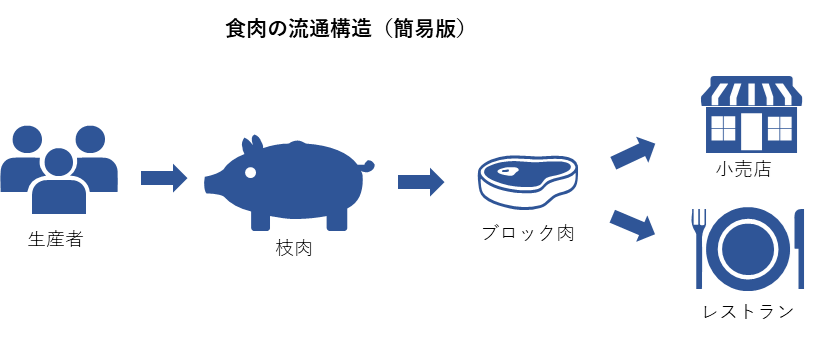[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]
第4回:M&A後の所長税理士の関与方法
~M&A後の所長税理士の関与方法はどのようになりますか?~
[解説]
辻・本郷税理士法人 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社
黒仁田健 土橋道章
▷関連記事:失敗例から学ぶM&A ~従業員の大半が退職したケース 、所長税理士と新所長の引継ぎがうまくいかなかったケース ~
▷関連記事:「会計事務所・税理士事務所のM&Aの特徴や留意点」とは?
Q、M&A後の所長税理士の関与方法はどのようになりますか?
A、M&A後の所長税理士(「所長税理士」は、売主側の個人事務所の所長をいいます。以下同様。)の関与度合いは、契約の中で待遇面も含めて決めることが重要です。M&A後の所長税理士の関与度合いには、大きく分けて四つのケースが考えられます。
①M&Aと同時に退職する
②M&A後一定期間は、所長として従来通りの業務をし、一定期間経過後退職する
③M&A後顧問などの相談役となり、一定期間経過後退職する
④期間は設けず、所長を継続する
①のM&Aと同時に退職するケースでは、業務の引継ぎに時間をかけることができず、瞬間的な引継ぎとなってしまいますので、引継ぎを受ける方の負担が大きくなり、また、従業員や顧問先も所長税理士が急に変わることによる不安感が大きいので、買主側としてはできるだけ避けます。
ただし、売主側である所長税理士は健康問題や個人的な事情があり、やむなく選択するケースがあります。この場合には、新しい所長をみつけて手配する必要があり、他のケースに比べて対応すべきことのスピードを速める必要が出てきます。
会計事務所の場合、高齢化や健康問題を要因とした事業承継型のM&Aをするケースが多いので、②又は③のように一定期間残って、引継ぎを進めていくケースが大半です。
なお、一定期間をどのくらいにするかは、その後の所長税理士のライフプランもあるので、契約段階での調整となりますが、1 年~ 5 年程度が目安となります。
特に③のケースのように、顧問などの相談役として関与する場合の出社頻度は、業務の引継ぎ状況に応じて決めていくケースが大半であり、毎日の場合もあれば、徐々に日数を減らす場合、当初から週何日と決める場合があります。
④の期間を設けず所長を継続するケースは、相当長い期間を見据えてM&Aをした場合が考えられますが、あまり多くありません。期間を設けず、そのまま継続するのであれば、個人事務所で事業をしているのと変わらないため、M&Aになるケースが少ないからです。
いずれにしろ従業員・顧問先に対して安心してもらうためにも、長年にわたり牽引してきた所長税理士が残ってくれることが重要です。
▷参考URL:M&A各種契約書等のひな形(書籍『会計事務所の事業承継・M&Aの実務』掲載資料データ)
![M&A後の所長税理士の関与方法 ~M&A後の所長税理士の関与方法はどのようになりますか?~[会計事務所の事業承継・M&Aの実務]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/会計事務所-事業承継MA.png)
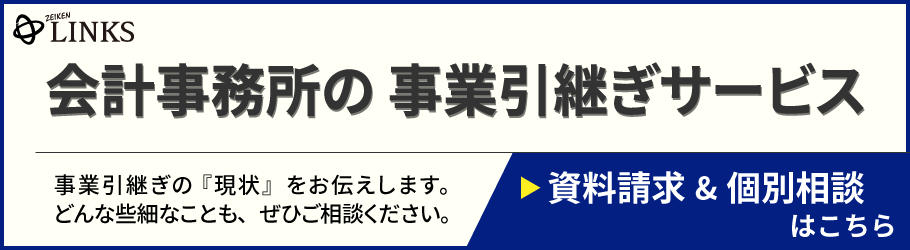
.png)
![【Q&A】法人が解散した場合の欠損金の控除[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)
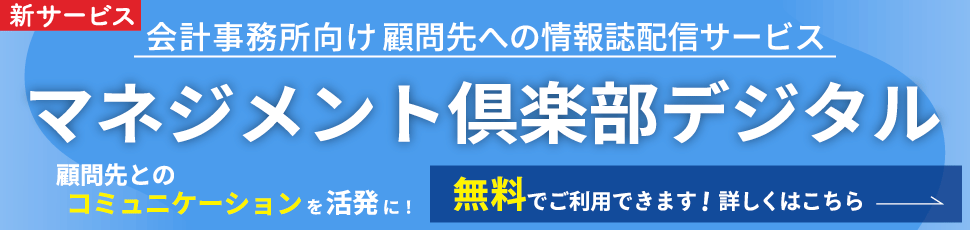



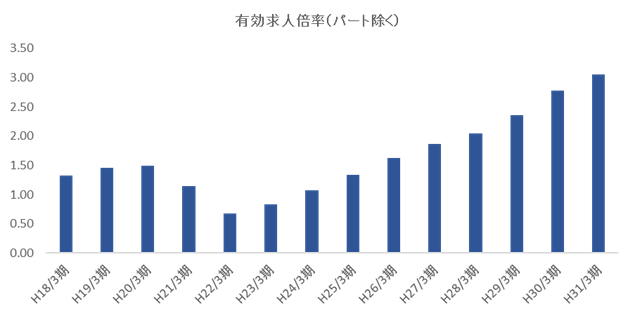
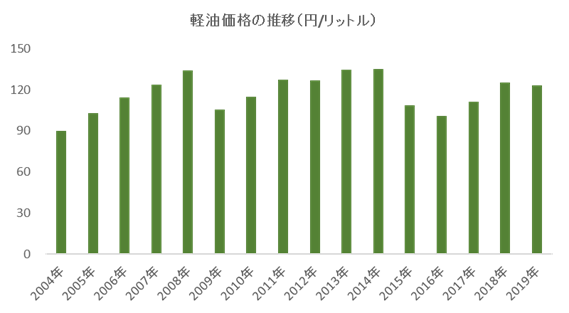
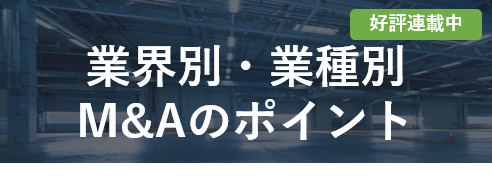


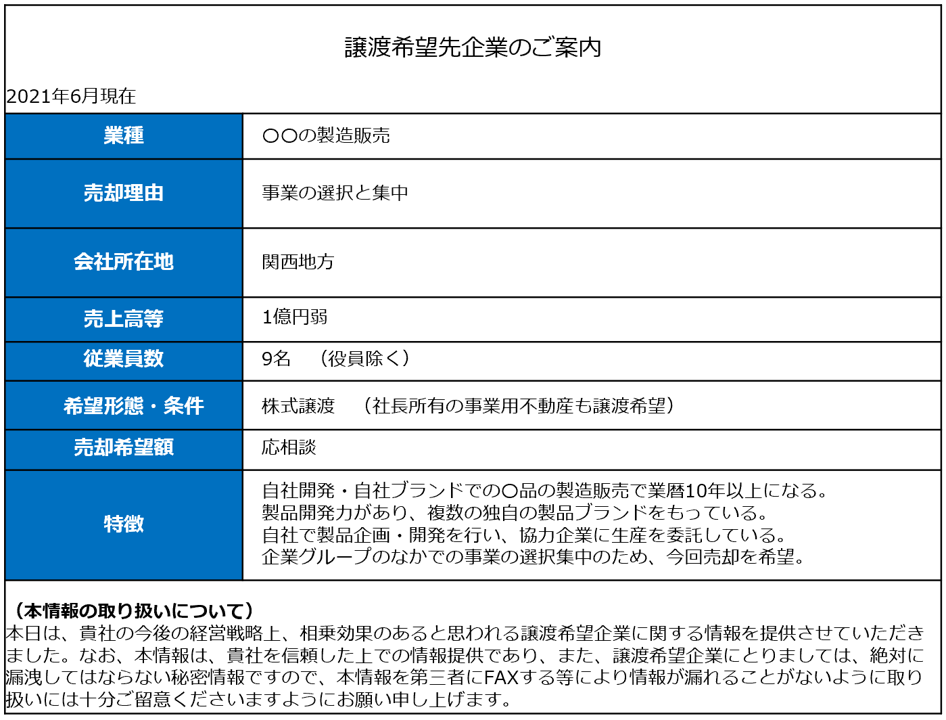
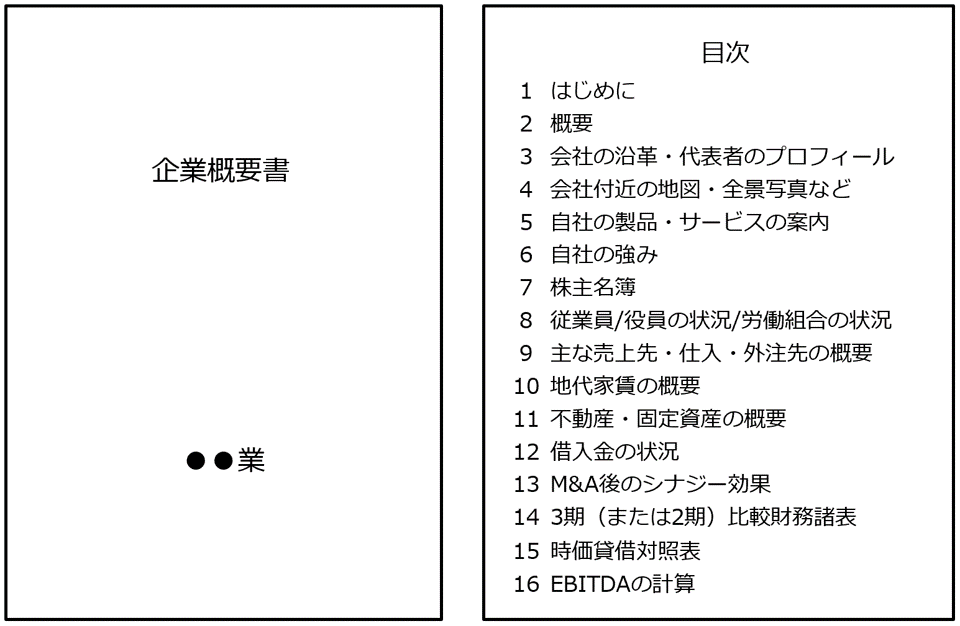
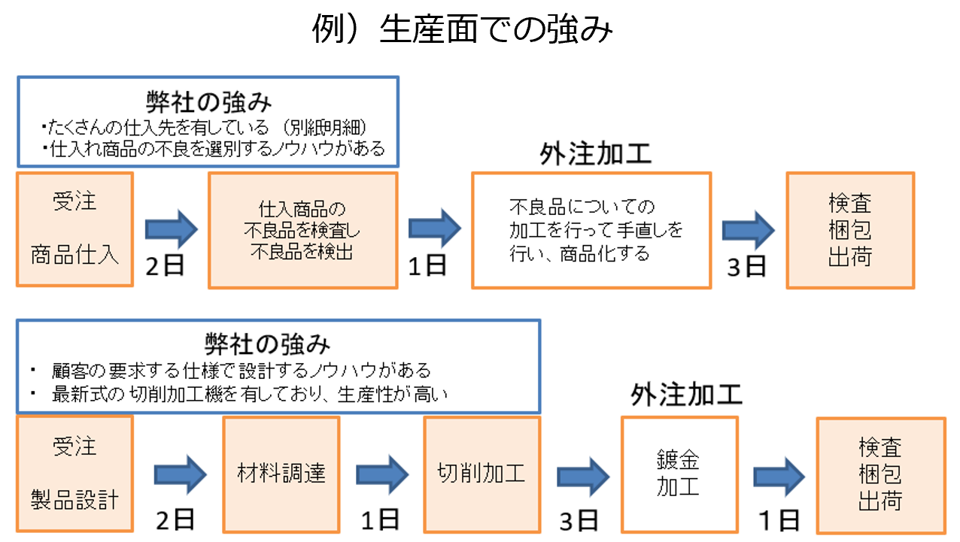
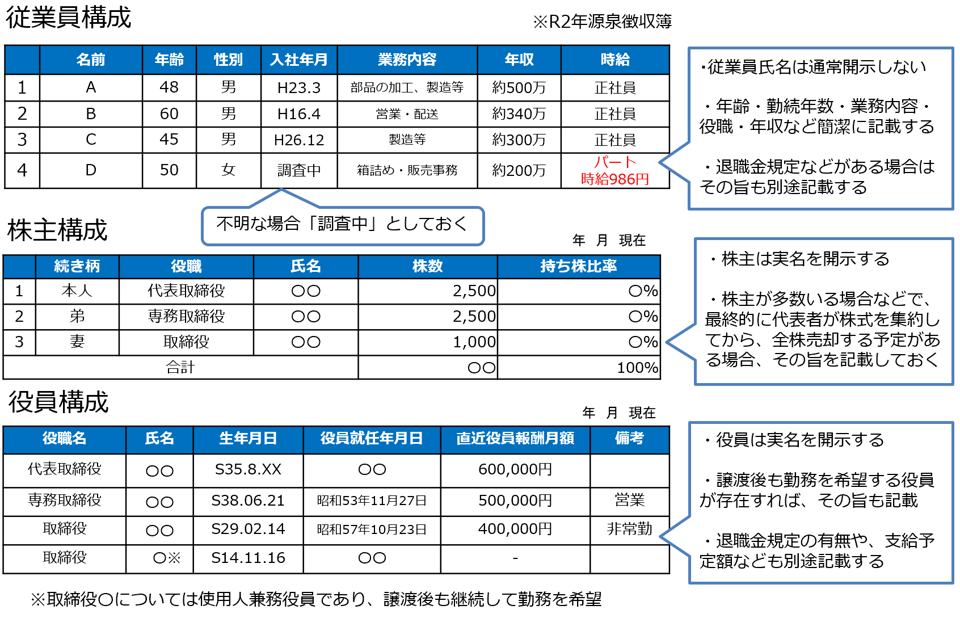
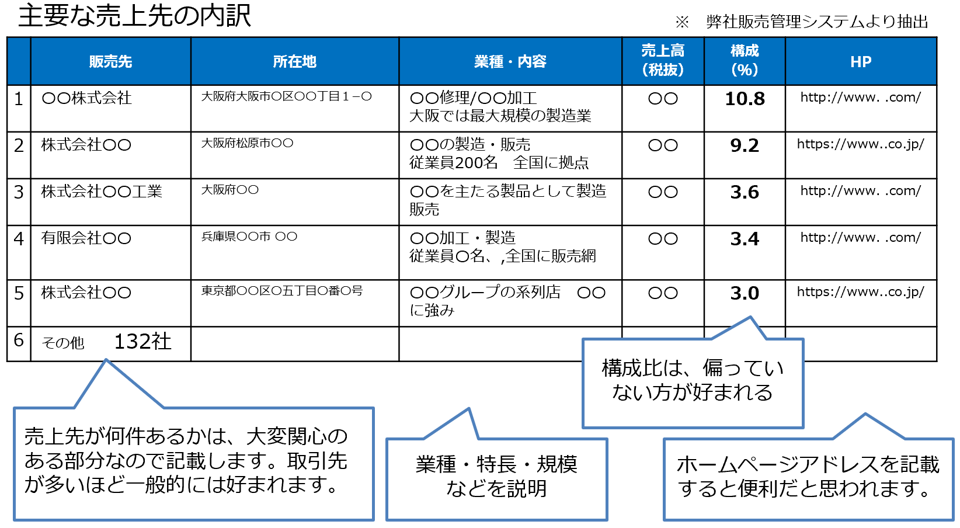
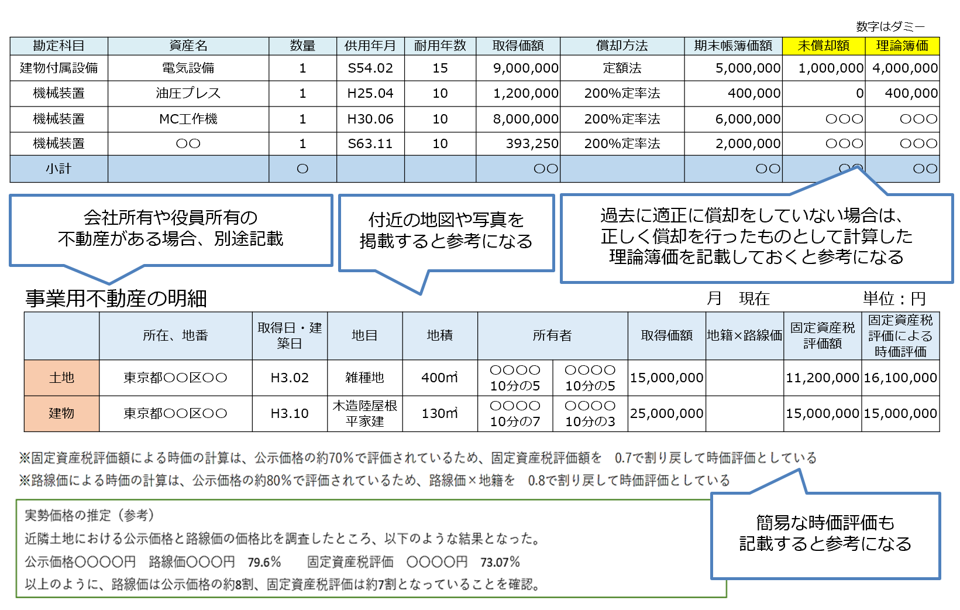
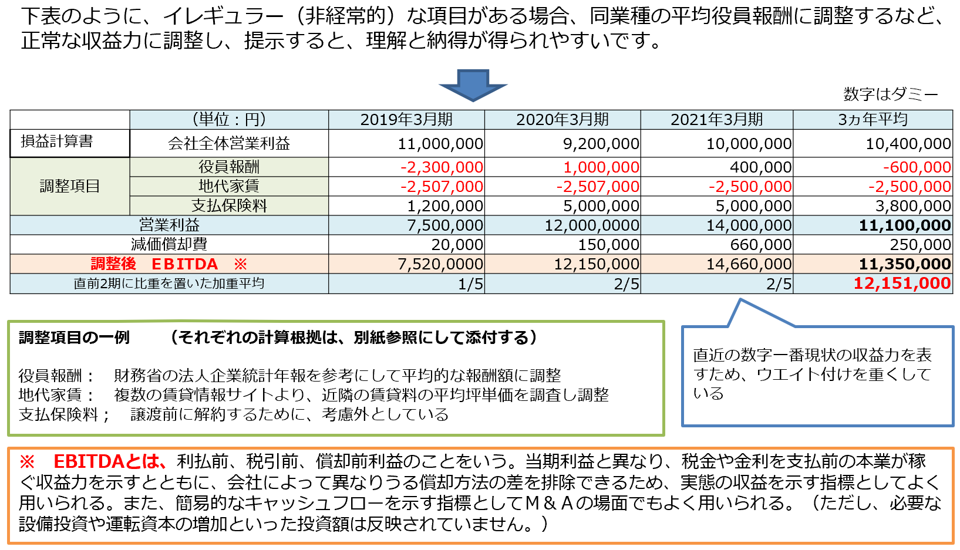
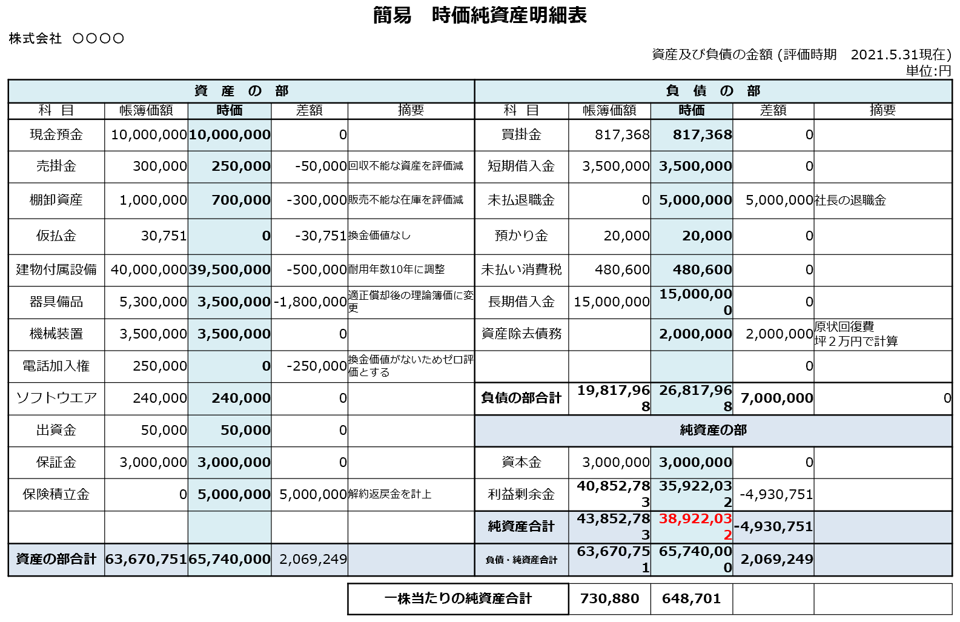

.jpg)

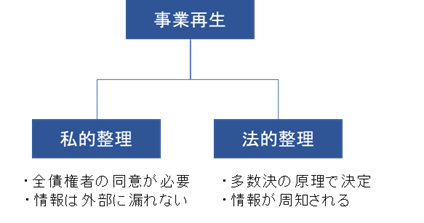
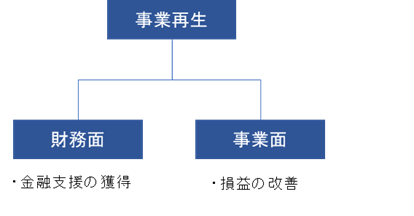
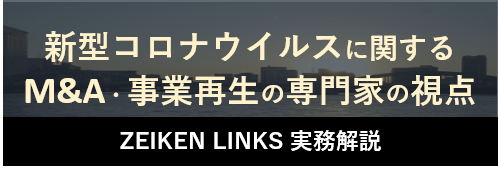


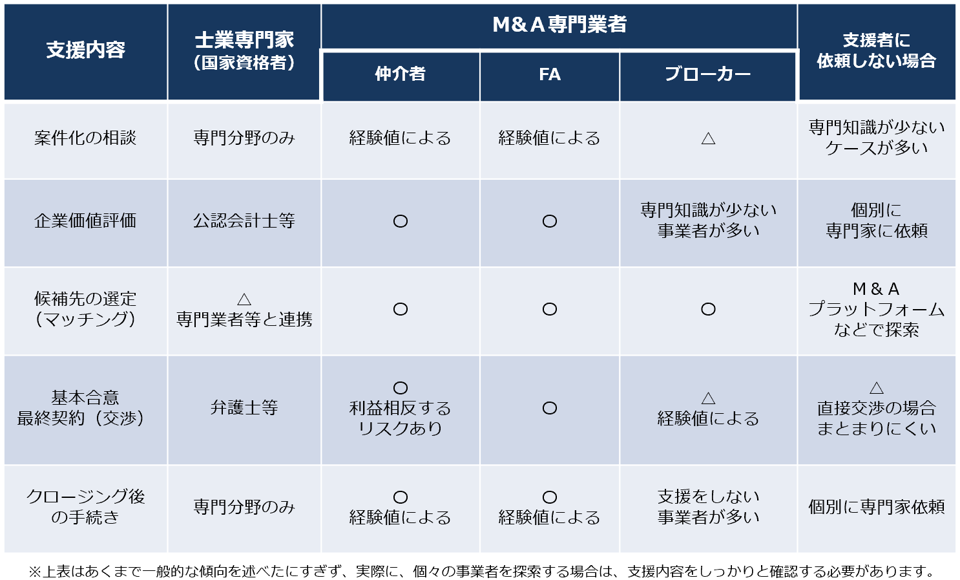

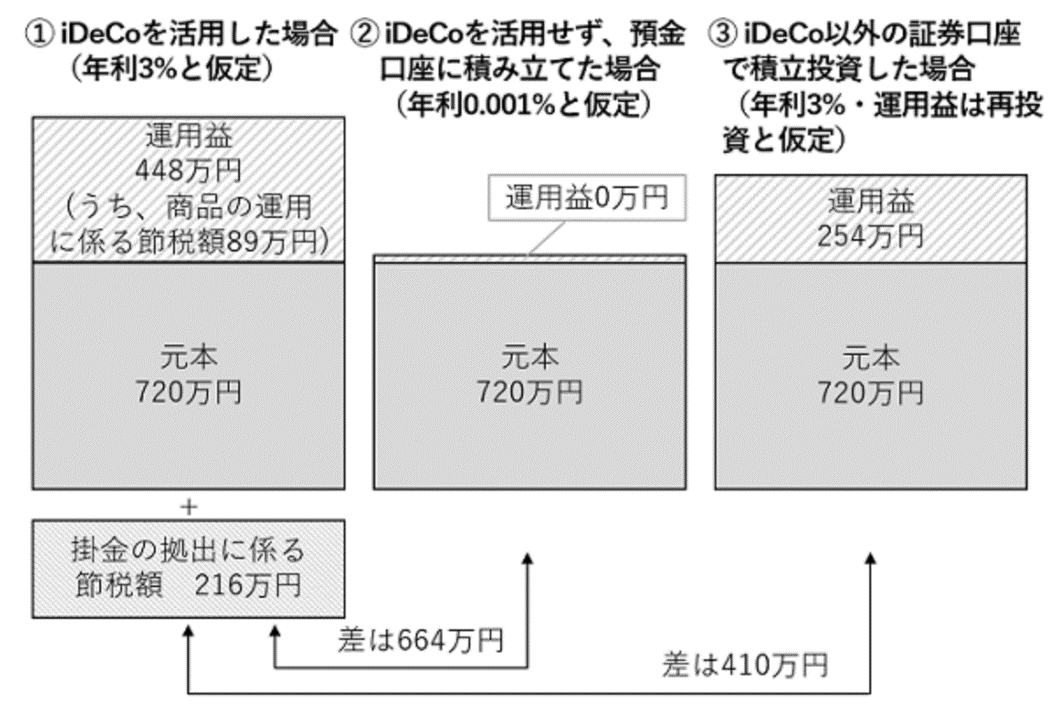
.png)