Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?|3分でわかる!M&Aのこと【解説コラム】
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
□■―――――――――
今後、ますます活用が進んでいくであろうM&Aについて、できるだけわかりやすくQ&A形式で解説するコラムを掲載することにしました。ぜひご一読ください!
―――――――――■□
Q-8 どうやってM&A先を探すのですか?
A
M&Aの件数は年々増加する傾向となっており、M&A先の探し方も様々な方法がありますが、現時点では次のような探し方が存在します。
|
以下、具体的にみていきます。
・取引先や知人に相談する
取引先や知人は、企業やオーナーにとってもいつも身近で事業内容などの理解も進んでいることが多いため、会社の実情を把握した上でM&A先の紹介を受けることが可能であること、仲介料などの関連する費用が抑えやすいことなどがメリットです。
ただし、M&Aを専門に行っているわけではないためタイミングがよければM&A先が見つかる可能性もありますが、見つからない可能性もあります。また、売却を希望しているなどの情報漏洩のリスクもあるため相談も慎重に行う必要があります。
・税理士、公認会計士、弁護士へ相談する
自社の顧問を担当しているなど関わりある各種士業へ相談する方法です。M&Aを専門としているわけではありませんが、様々な顧問先を持ち、取引先や知人とは違ったネットワークがありますし、M&Aは会計・税務・法律での知識が必要となるためそれぞれの専門分野における相談も可能です。
こちらもタイミングによりM&A先が見つかる可能性はありますが、見つからない可能性もあります。
・M&A仲介会社に相談する
M&Aを希望する売り手と買い手の交渉を仲介し、成約させる業務を専門にしている会社であるM&A仲介会社へ相談する方法です。M&Aを専門としているため、売却先の選択肢は多く、またM&A全体を通してアドバイス・サポートを受けることができます。
一方で各種手数料は高くなる傾向にあり、また、買い手側へも同様のアドバイス・サポートを行っているため、利益相反(注)の問題があります。そのあたりの状況も理解した上で、サポートを受ける必要があります。
(注)利益相反とは、ある行為が一方にとっては利益になるが、他方にとっては不利益になってしまう行為をいいます。例えば、M&A仲介会社では、買い手と売り手の双方と仲介契約を契約し双方に助言を行いますが、安く買いたい買い手と、高く売りたい売り手双方に有利になるような助言は一般的には困難とされています。
・商工会議所等の公的な機関に相談する
商工会議所や事業引継ぎ支援センターなどの公的な機関に無料で相談が行えることはメリットです。また、公的な機関であるため安心感もあります。
しかし、M&A全体を通しての専門的なサポートを受けられるわけではないため、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになるため、留意が必要です。
・銀行等の金融機関に相談する
取引のある金融機関へ相談する方法です。金融機関は様々な顧客との取引があるため案件数としては多く、また、金融機関と取引のある先の紹介であれば一定の信頼感があります。一方で、金融機関側の利益(買い手側への融資など)を考えての案件紹介の可能性もあるため留意が必要です。
・マッチングサイトを利用する
M&Aの売り手と買い手をマッチングさせるインターネットサービスを利用する方法です。
自身でマッチングサイトから検索することになるため、求める条件を自身で探せることや手数料が抑えられる点がメリットです。
ただしM&A仲介業者に比べると、M&A全体を通してのサポートは受けにくくなります。また、必要に応じて各種専門家等への相談を別途行う必要があり、その場合には別途費用が発生することになります。
参考として以上の情報を表に整理してみました。
それぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、まずは無料相談などを活用しつつ、自身のケースにあう探し方を検討するのもよいでしょう。
(編注:Q-5でも相談先を選ぶ際のポイントを解説していますので、併せてご参照ください。)
| 探し方 | メリット | デメリット |
| 取引先や知人に相談する | 費用が抑えられる | 案件が見つからない可能性あり、情報漏洩リスクが高い |
| 身近な税理士、公認会計士、弁護士等の専門家へ相談する | M&A関連の専門相談も可能 | 案件が見つからない可能性あり |
| M&A仲介会社に相談する | M&A全体のアドバイス・サポートを受けられる | 費用が高い、利益相反問題あり |
| 銀行等の金融機関に相談する | 案件数多い、一定の信頼感 | 案件紹介の可能性あり |
| M&Aのマッチングサイトを利用する | 自身で検索可能、費用が抑えられる | M&A全体のサポートは受けにくい |
(執筆:税理士・公認会計士 風間啓哉)

このコラムでは読者の方からのご質問も募集しています。M&Aに関することで疑問に思っていること、コラムの内容に関してもっと詳しく知りたいこと、○○について取り上げてほしい、などありましたら、こちらのアドレス(links@zeiken.co.jp)までお知らせください
(注意)回答・解説は原則このコラム内で行い、個別の回答はできません。個別事例についてのご相談には対応できませんのであらかじめご承知おきください。
風間啓哉(かざま けいや)
税理士・公認会計士(風間会計事務所 代表)
2005年公認会計士登録、2010年税理士登録。
監査法人にて監査業務を経験後、上場会社オーナー及び富裕層向けの各種税務会計コンサル業務及びM&Aアドバイザリー業務等に従事。その後、事業会社㈱デジタルハーツ(現 ㈱デジタルハーツホールディングス:東証プライム)へ参画し、同社取締役CFOを経て、同社非常勤監査役(現任)を経験。2018年から会計事務所を本格的に立ち上げ、現在に至る。
(著書等)『PB・FPのための上場会社オーナーの資産管理実務(三訂版)』『資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル』(共著、税務研究会)、『ケーススタディ M&A会計・税務戦略』(共著、金融財政事情研究会)
↓ 会計事務所の所長様向け ↓
↓ M&Aの解説をもっと読む ↓
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
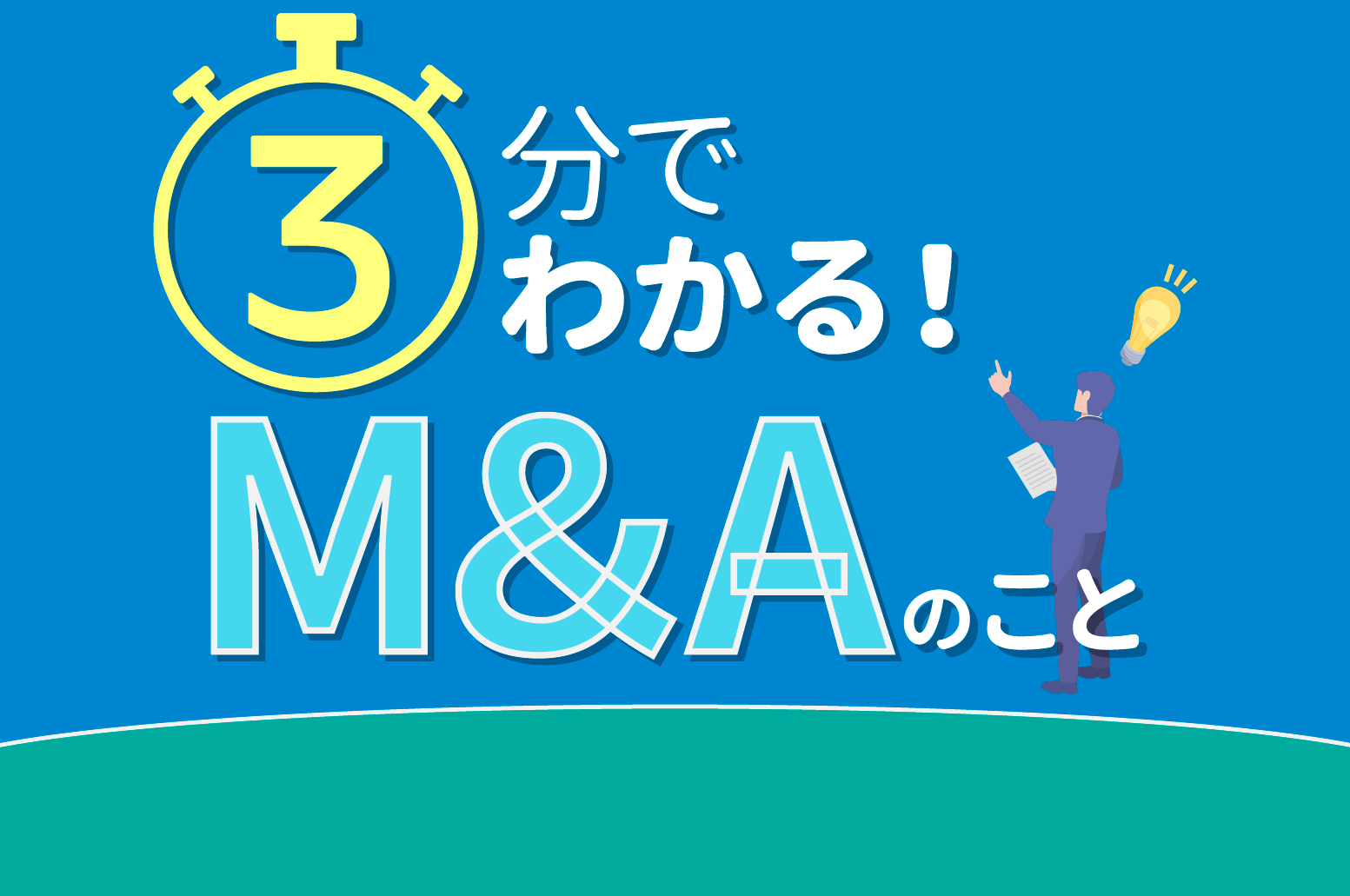
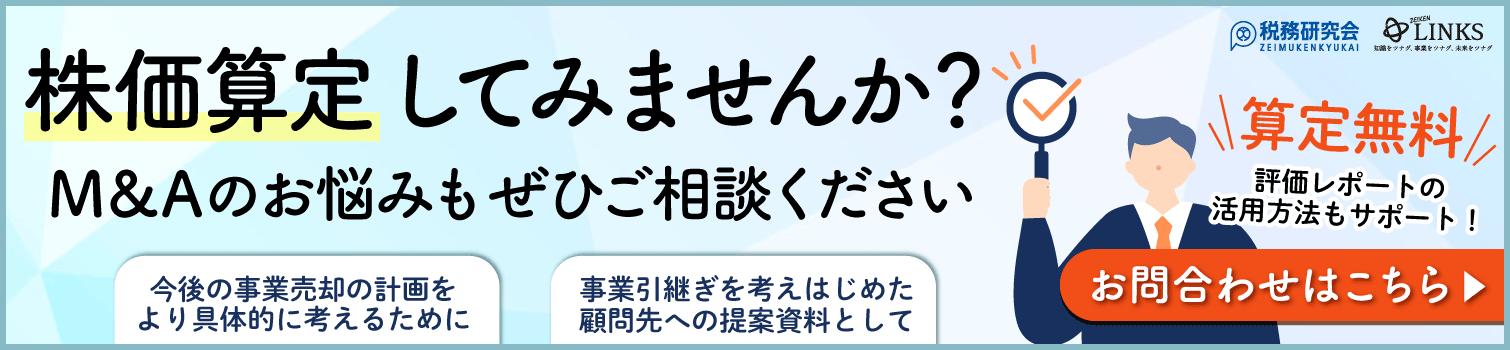
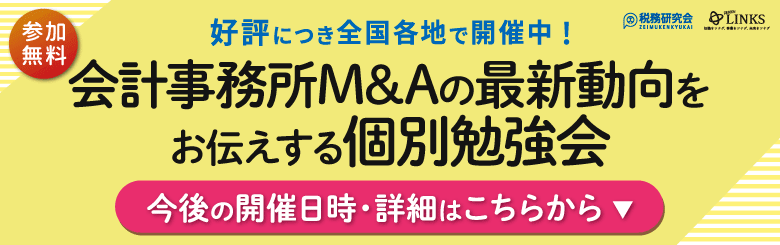

![どのような会計事務所が買手となるのでしょうか? また、買手はどのような理由でM&A をするのでしょうか? 具体的な事例を教えていただきたいです。[会計事務所M&Aの疑問(譲渡/入門編)]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/kaikeijimusyoMAnogimon.illver-1200x797.png)
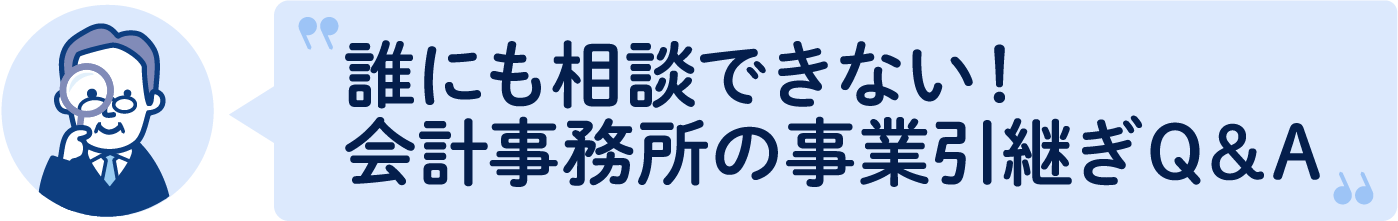

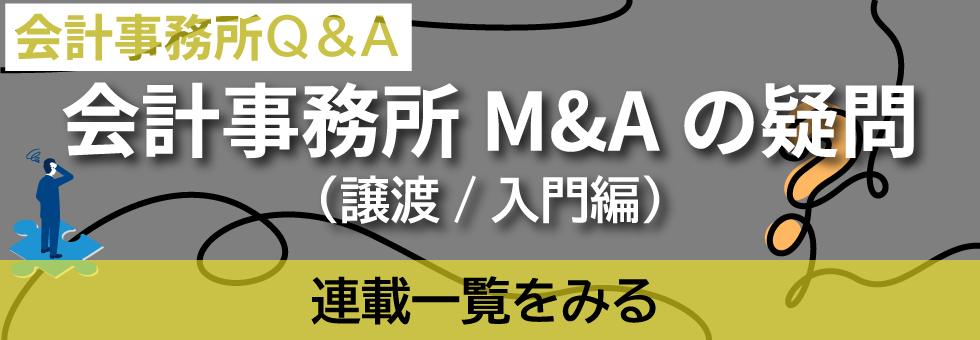
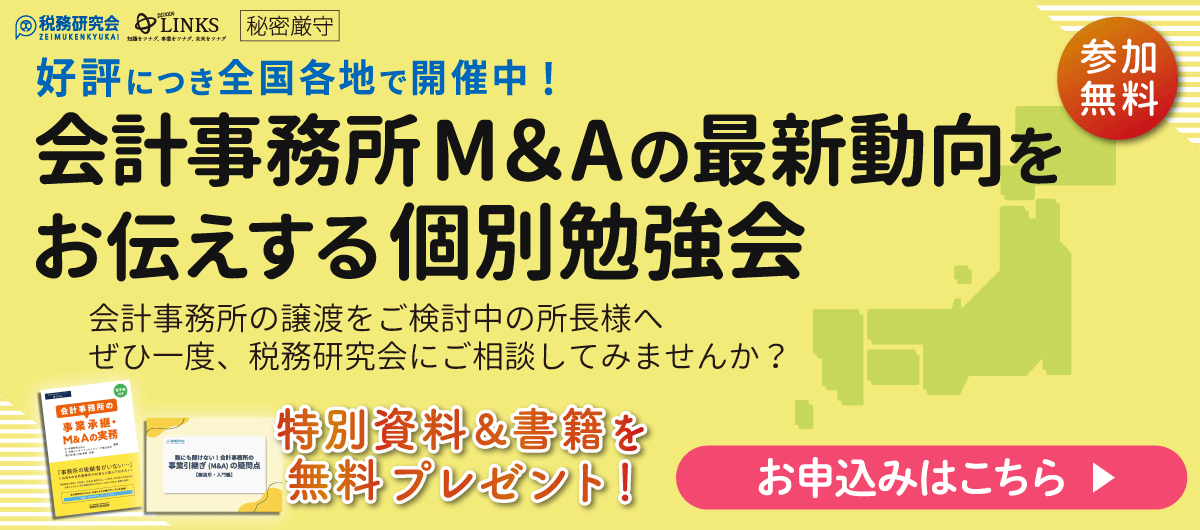
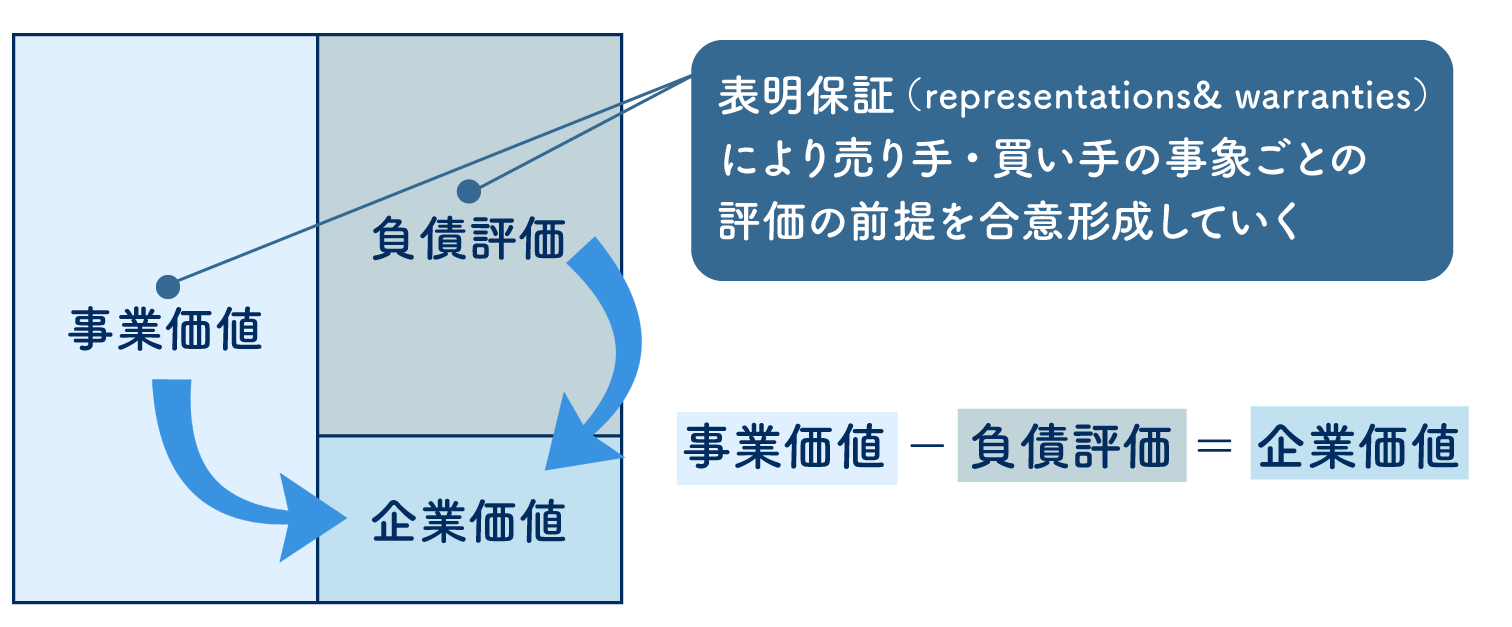
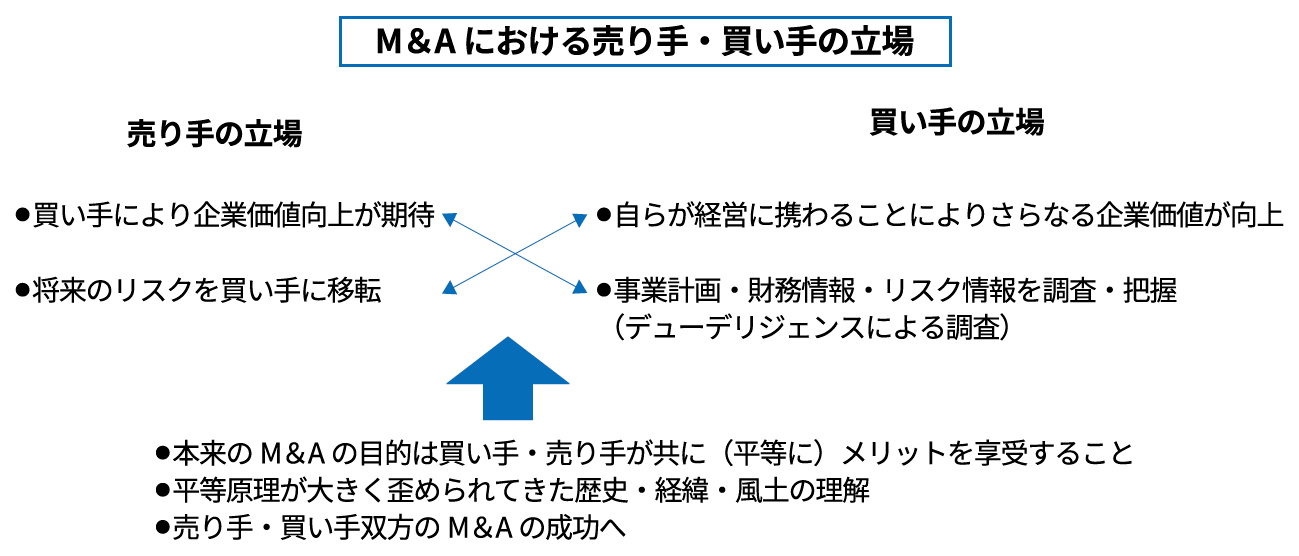
![どのような会計事務所が買手となるのでしょうか?[税理士事務所の事業引継ぎ(M&A)や後継者不足に悩んだら]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/smallma-1.png)
