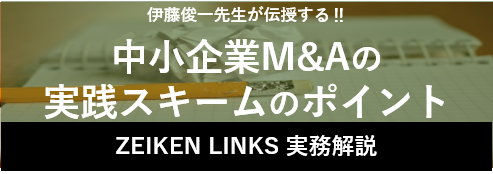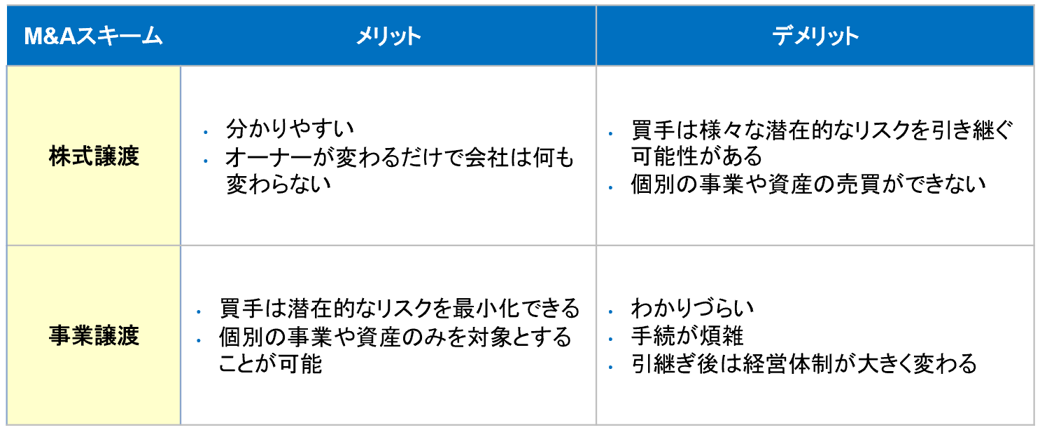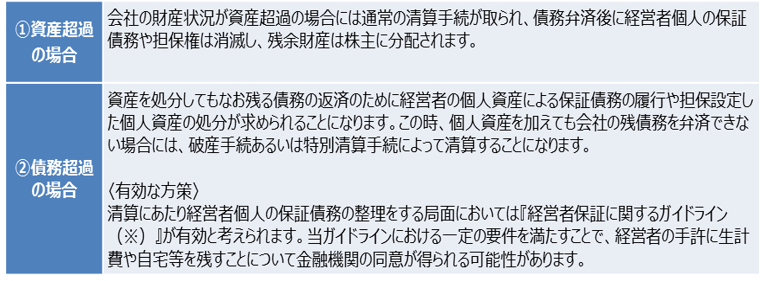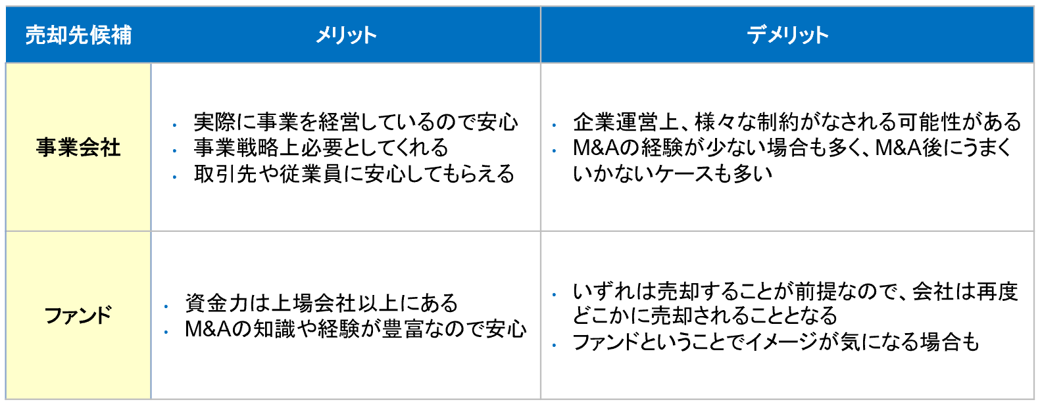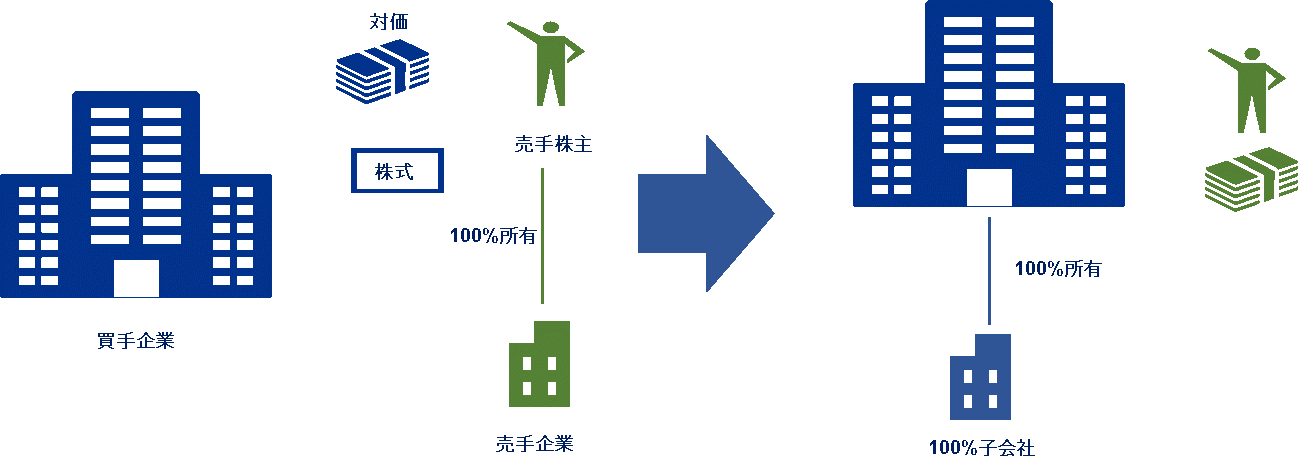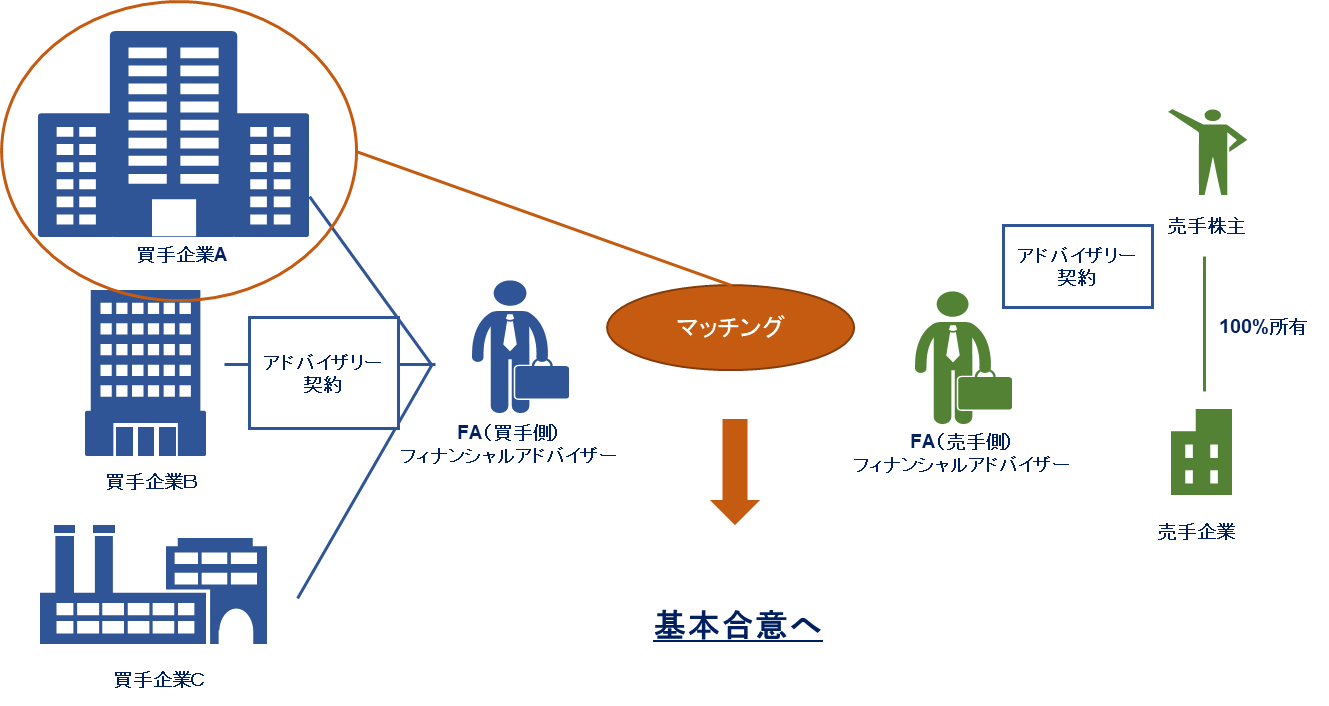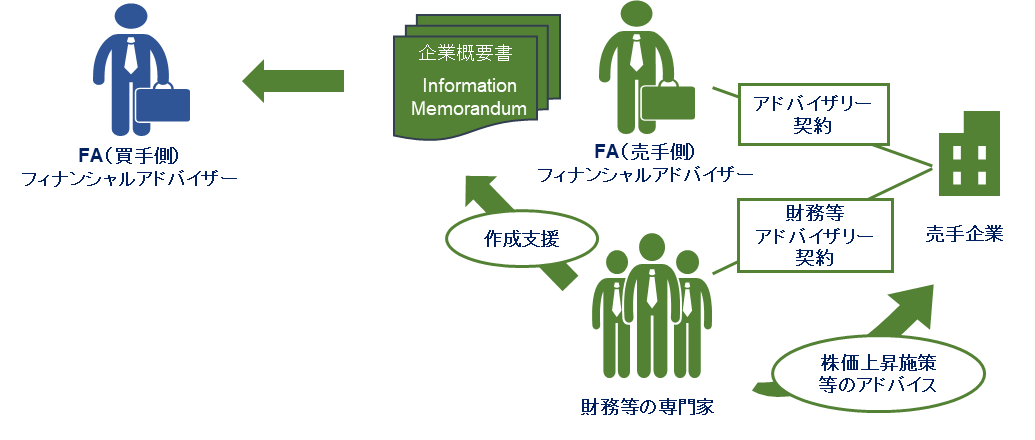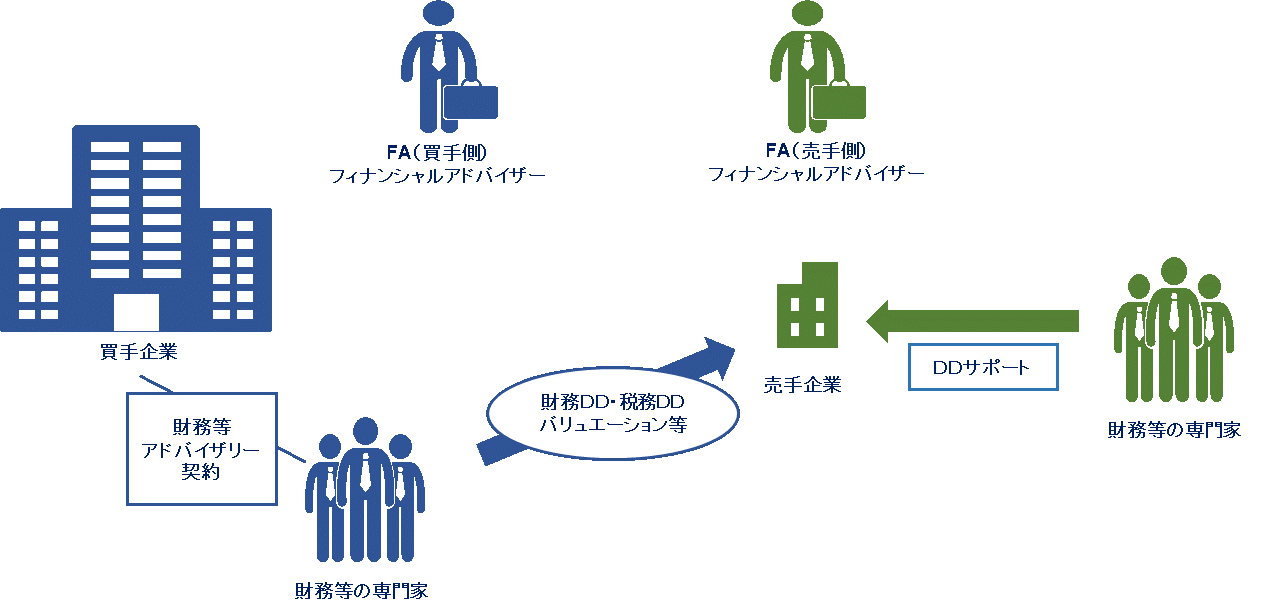[解説ニュース]
住宅の譲渡所得の特例では、本当に居住していたか見られています
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)
1.はじめに
マイホームを売った場合には、新たな住宅を取得するのが通常であるなど、一般の資産の譲渡に比べて特殊な事情があり、その担税力が弱いという理由から、税制上、特例が設けられています。その最もポピュラーな特例が居住用財産の譲渡所得の特別控除、いわゆる3,000万円特別控除です(措法35①)。
こうした居住用財産に係る譲渡所得の特例では、譲渡の対象財産が「その居住の用に供している家屋の譲渡若しくはその家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等」を譲渡した場合であること、又は住まなくなってから3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡した場合であることが、大きなポイントになっています。
居住の用に供しているということについては、「生活の拠点として利用している家屋をいい、これに該当するかどうかは、その者の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定するのが相当であり、また、本件特例の適用を受けるためには、譲渡資産に短期間臨時にあるいは仮住まいとして起居していたというのみでは足りず、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して譲渡資産を生活の拠点としていたことを要するもの」と考えられています(国税不服審判所平成31年2月6日)。
しかし、しばしば対象財産が「居住用」であるかどうかを巡って、納税者と税務署との間で争いが起こります。今回は、最近の裁決事例から、居住の用に供している実態がどのように確認されているかをチェックします。
2.電気・水道等の利用、源泉徴収票の住所…
先の国税不服審判所平成31年2月6日の裁決事例は、納税者Aさん(請求人)が父親から相続した住宅に相続後に住民票を移してから、その住宅を売却し3,000万円特別控除を適用して申告したところ、税務署からその住宅に本当に住んでいたとは認められないとして否認、争いとなったものです。
ここで、Aさんがその住宅に住んでいた証拠としてチェックを受けたのは次の事項です。
①住民票、運転免許証、源泉徴収票の住所
②職場に届出る住所地やその変更手続き
③郵便局への転居届
④電気、ガス、水道の使用量
⑤近隣住民の証言
これらがチェックされるのは、「請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたのであれば、その事実を示す何らかの形跡(例えば、引っ越し、通勤、郵便物、近隣商店の使用に係る領収証、町内会費の支払など)が残るのが通常である」(同裁決)という考えからです。
また、この事案では、売却に際して不動産仲介会社に依頼をしており、譲渡対象の住宅のカギを引き渡していた点や、不動産の広告に現況についての記載が「空き家」だった点がチェックされていました。
同裁決では、①住民票、運転免許証は対象の住宅の住所地だったが、源泉徴収票の住所は転居前のまま、②職場へ住所変更の手続きの書面を出したが、引っ越し完了連絡がなかったためいったん預かりとなっていたこと、③郵便局への転居届はなく、④電気水道ガスの使用料はほぼなかったこと、⑤近隣住民からは「請求人が本件家屋で生活していたのを見かけたことはない」旨申述があったことから、「生活の拠点として利用していたとは認められない」として3,000万円特別控除の適用を否認した税務署の処分を支持しています。
3.介護施設への入所と居住地
ケガなどにより介護を必要とする生活となったため、自宅にいられなくなった人が、相続開始直前、その住宅を売却したケースで、3,000万円特別控除の適否が争われた事例があります(国税不服審判所平成31年1月18日)。
「居住用家屋」の範囲については、転勤、転地療養等の事情のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、その事情が解消したときはその配偶者等と起居を共にすることとなると認められるときは、その配偶者等が居住の用に供している家屋(措法通31の3-2⑴)も含まれるとされています。
これを下敷きにしたと見られる相続人(請求人)が住宅を売却した平成26年の前、平成17年から被相続人が施設へ入居していたが、その住宅に戻る意思があったから「居住用」と主張しました。しかし国税不服審判所はこの事例でも電気、ガス、水道の使用量、自治会費の支払い等もチェックし、生活の実態が認められないことから「居住用家屋とは、真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていた家屋をいうのであり、治療終了後に家屋に戻る意思の有無のみによって判断されるものではない」とし請求を棄却しています。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/02/03)より転載


![実際に売却するときの留意点は?-DDの受入れや価格交渉-[M&A担当者がまず押さえておきたい10のポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/home-office-336378_640.jpg)
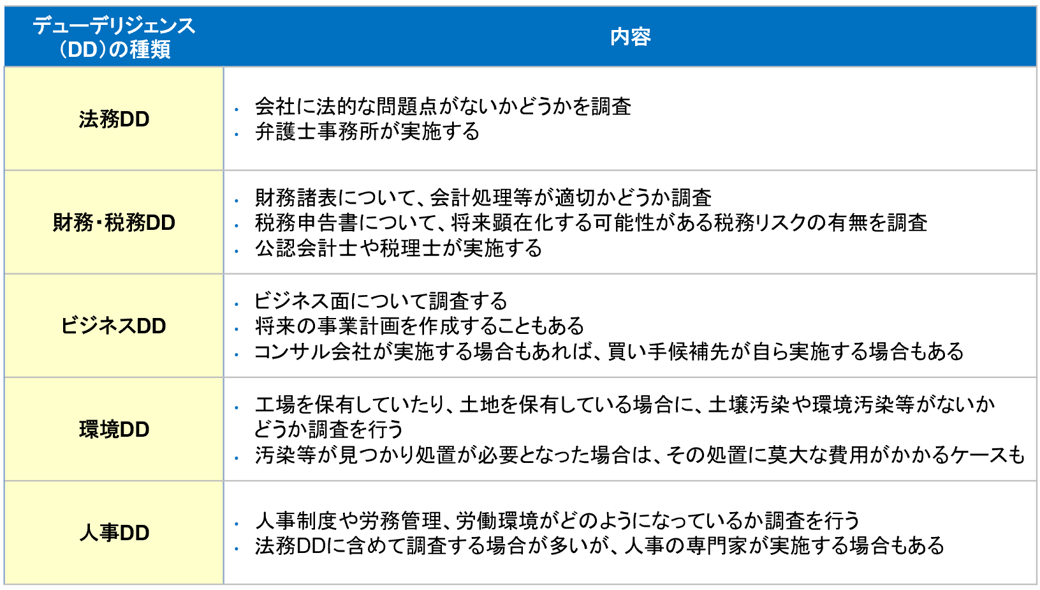
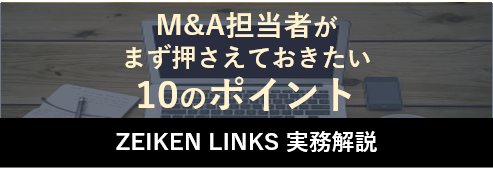

![【Q&A】個人事業者が事業を廃止した場合の事業用資産に係る課税関係[税理士のための税務事例解説]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/tree-736888_1280.jpg)


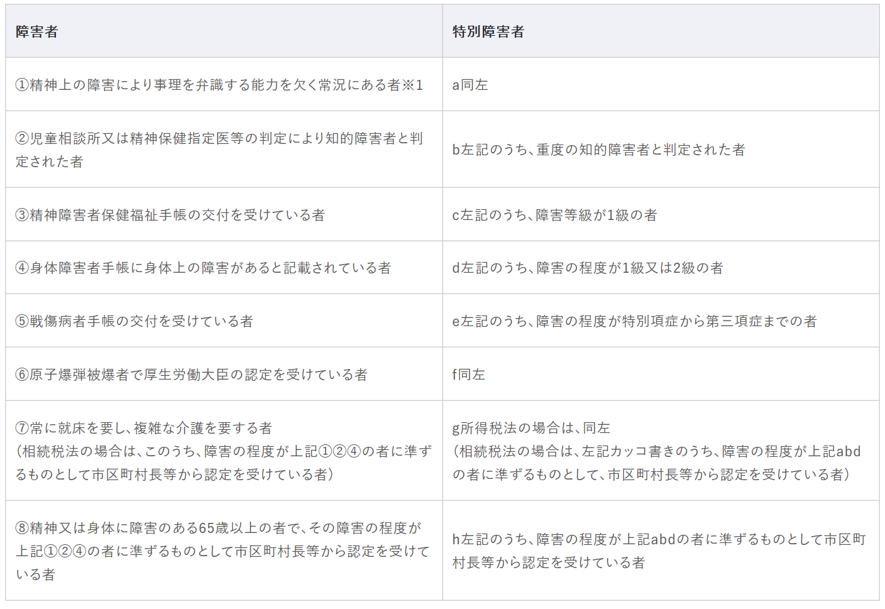
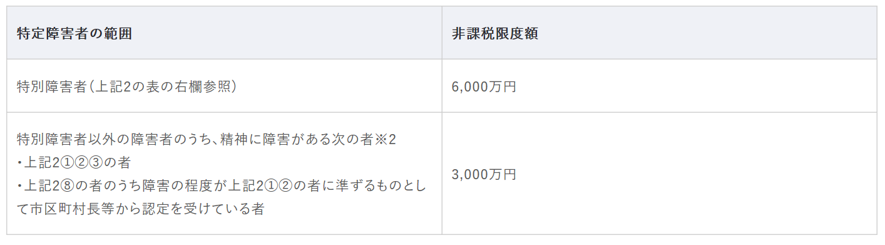

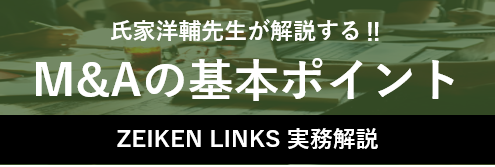

![PPA(Purchase Price Allocation)の基本的な考え方とは?[経営企画部門、経理部門のためのPPA誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2020/01/business-1477601_640.jpg)



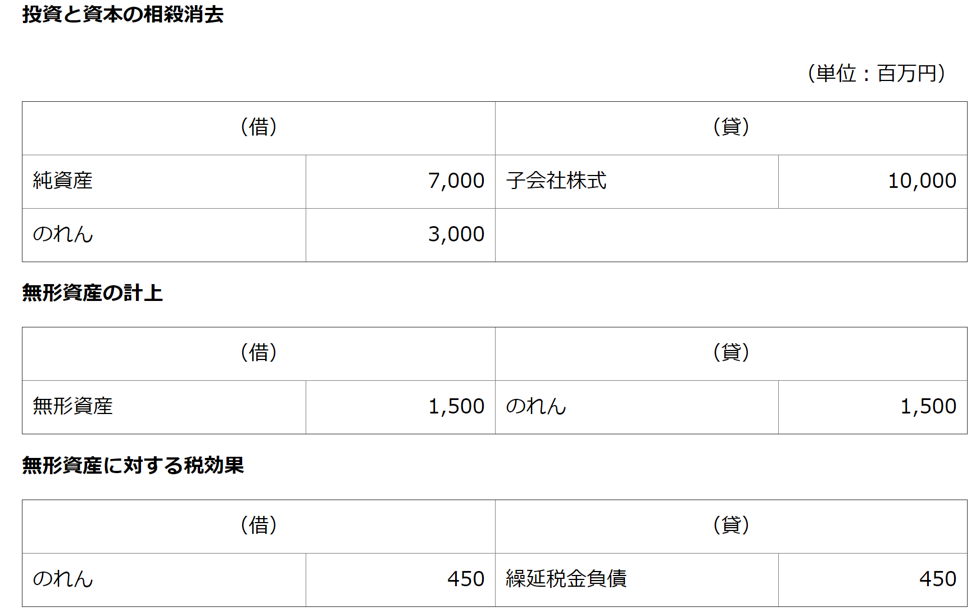


![会社や事業を売る準備 ~売るために準備しておく、財務上、労務上、法務上のポイントとは?~[小規模M&A(マイクロM&A)を成功させるための「M&A戦略」誌上セミナー]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/files-1614223_640.jpg)
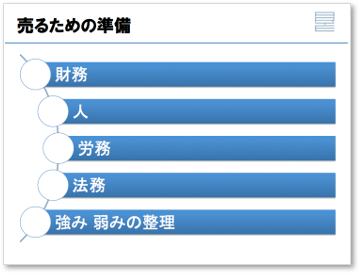
.png)
.png)
.png)
.png)
![株式譲渡スキームにおける役員慰労退職金支給 ~現金支給・現物支給の有利不利判定~[伊藤俊一先生が伝授する!税理士のための中小企業M&Aの実践スキームのポイント]](https://links.zeiken.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/pencil-1891732_640.jpg)