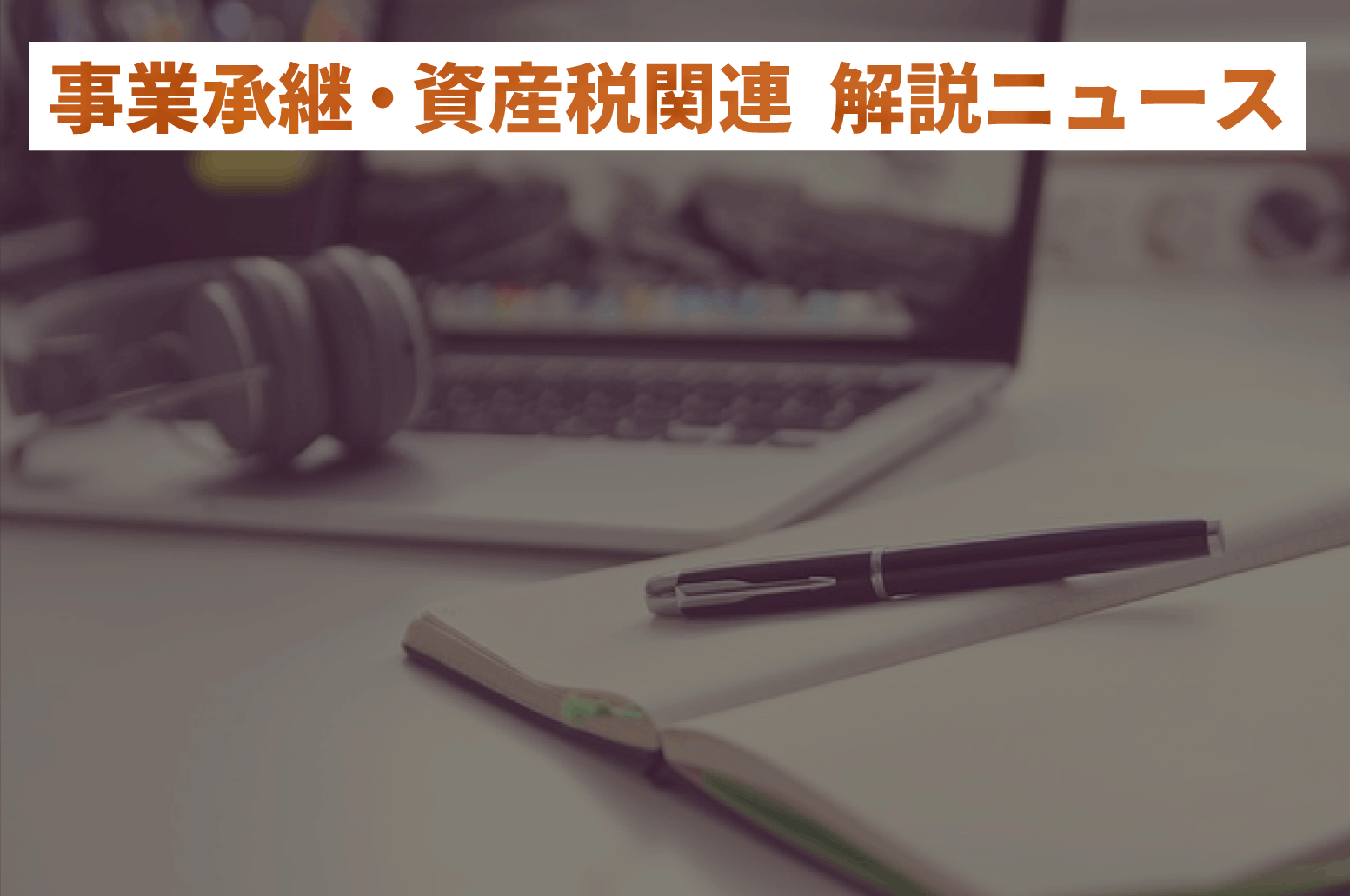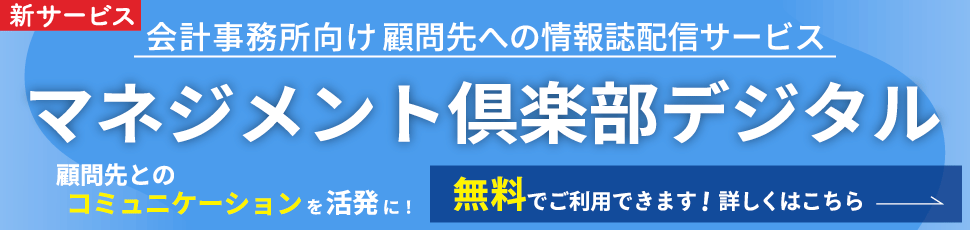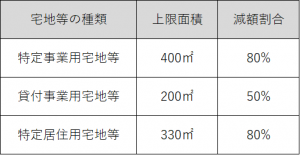[解説ニュース]
所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~適用判定時の基準所得金額の範囲
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
[関連解説]
【Q&A】土地賃貸借に際し無償返還届出を提出した場合の非上場株式の相続税評価(土地と株式の所有者が別の場合)
【Q&A】被相続人が相続開始12年前に取得した不動産を相続人が相続税の申告期限前に譲渡した場合の相続税評価
| 【問】
不動産賃貸業を営むAさんは、令和7年3月に平成15年から東京都品川区に所有していた貸ビルとその敷地を譲渡し、長期譲渡所得の金額9.9億円が生じました。Aさんの令和7年分の所得税の確定申告が必要な所得には、他に不動産所得の金額1,200万円、所得控除額200万円があります。また、B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で取得した上場株式等に係る配当所得の金額4,000万円については、申告不要制度を適用し、確定申告しないつもりです。 |
【回答】
1.結論
Aさんの場合、本特例の対象となる「基準所得金額」(下記2(2)参照)」には、申告不要制度を適用して確定申告から除外できる上場株式等に係る配当所得の金額が含まれるので、注意が必要です。
2.解説
(1)本特例の概要
令和7年分の所得税について、基準所得金額(下記(2)参照)が3.3億円を超える場合、①の算式で計算した金額から②の基準所得税額(下記(3)参照)を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます(租税特別措置法(措法)41条の19第1項)。
①(その年分の基準所得金額-3.3億円)×22.5%
②その年分の基準所得税額
(2)基準所得金額の意義
「基準所得金額」は、措法41条の19第2項に定める所得となりますが、具体的にはその年分の所得税につき申告不要制度を適用しないで計算した所得金額(源泉分離課税の対象となる利子所得の金額や、一定の非課税金額を除く。)の合計額をいいます。
この場合の「申告不要制度」とは、源泉徴収あり特定口座内で上場株式等の配当(配当所得)を取得した場合や上場株式等の譲渡による所得が生じた場合に、確定申告を不要とすることができる特例(措法8条の5、37条の11の5)をいい、これらの申告不要とできる所得についても基準所得金額に含まれます。
(3)基準所得税額の意義
「基準所得税額」は、本特例や外国税額控除等の適用がないものとして計算した所得税及び復興特別所得税の額(源泉分離課税に係るものを除く。)をいいます(措法41条の19第3項等)。申告不要制度の適用を受けようとする上場株式等に係る配当所得や譲渡所得の金額に対し、源泉徴収された所得税額や復興特別所得税額も、基準所得税額に含まれます。
(4)本特例の適用判定の例
Aさんの令和7年分の不動産所得の金額1,200万円、所得控除額200万円、土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額9.9億円、申告不要にできる上場株式等に係る配当所得の金額が4,000万円の場合、本特例の適用の有無を判定すると次の通りとなります。
①(1,200万円+9.9億円+4,000万円-3.3億円)×22.5%=160,200,000円
②不動産所得の金額1,200万円、所得控除の合計額200万円の場合の課税総所得金額に対する所得税額
(1,200万円-200万円)×33%-153.6万円= 1,764,000円
③土地・建物に係る長期譲渡所得の金額9.9億円に対する所得税額(税率15%) 148,500,000円
④②と③の合計額に係る復興特別所得税額
(②+③)×2.1%=3,155,544円
⑤申告不要制度の適用を受けようとする上場株式等に係る配当所得の金額4,000万円に対し、源泉徴収された所得税額(税率15%) 6,000,000円
⑥⑤に係る復興特別所得税額
⑤×2.1%=126,000円
⑦基準所得税額
②+③+④+⑤+⑥=159,545,544円
⑧①-⑦=654,456円 ∴本特例の適用あり。
この場合、654,456円が本特例の適用により追加で課される所得税額となります。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2026/02/09)より転載