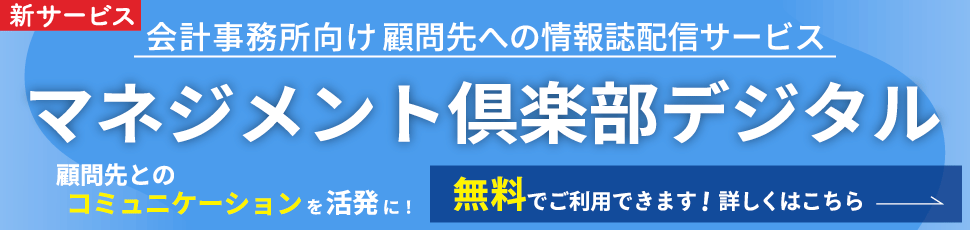不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例
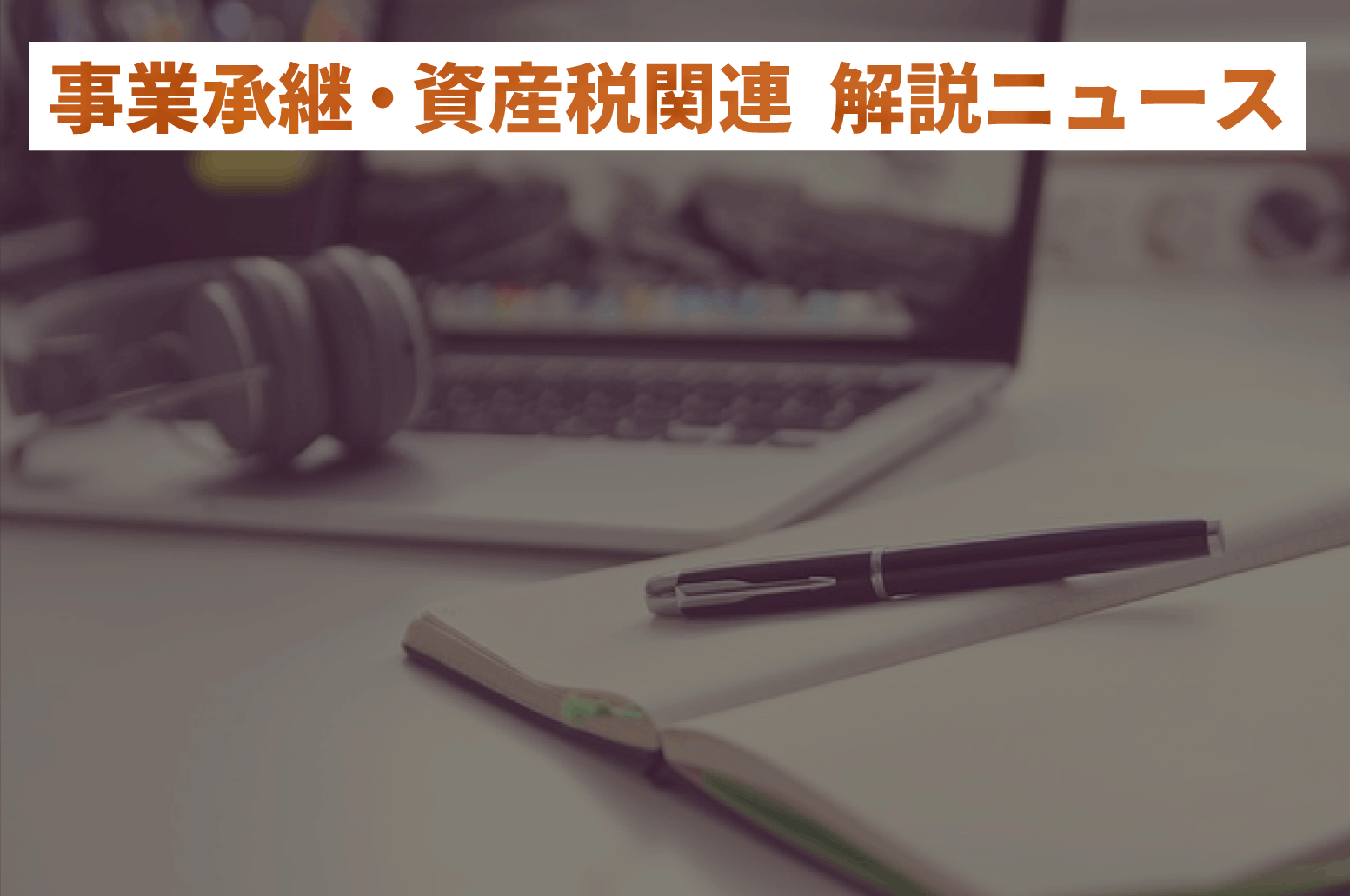
- ニュース/レポート
- 解説コラム
[解説ニュース]
不動産を持たせた会社の株式の贈与で、株価が評価通達6項で再評価された事例
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)
[関連解説]
■不動産を買った時の土地建物の価額按分が不合理と指摘された場合
■マンション建替え決議と、転入後売買の3000万円控除適用を巡る裁決事例
1.はじめに
相続税の計算では、相続財産の金銭的価値を見積もる「評価」が必要になります。国税庁は、簡便な見積もりの方法(評価方法)で、かつ公平性を保てるようルール(財産評価基本通達、以下、評価通達という。)を定めています。ただし、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情が認められる場合には、例外的に評価通達とは別の方法で評価することが評価通達の中で決められています。それが評価通達6項です。
この6項を巡っては令和4年4月19日に、最高裁がその適用にあたって考慮すべき上記事情の考え方を深め、新たな判決を下しました。以降、同6項発動件数が令和7年6月末までに19件と増加、相続税の節税動向を巡る状況が一変しています。
2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が
こうしたなか、資産家が設立した会社に不動産を持たせ、3年後にその株式を相続時精算課税方式で子に贈与したケースで、その株価に対し6項を適用して更正されて争いになった裁決事案が出てきました(国税不服審判所令和7年4月16日)。
事案の概要は次のとおりです。
(1)平成28年に、資産家が発起人となり不動産の所有、管理、賃貸等を目的とする法人をつくるため出資し、同社の設立時発行株式全てを取得。
(2)同時に事実上、同社に5年後一括返済の8億8千万円の借入をさせて出資金と併せ、15階建ての賃貸共同住宅を18億5千万円で買わせた。
(3)会社保有資産の評価額に時価縛り(評価通達185カッコ書き)がなくなり通達評価となる令和2年に、資産家の子に株の半数近くを相続時精算課税方式で贈与した。贈与時の会社の株式は借入が残っていたため、通常の評価通達に基づけば0円だった。
(4)所轄税務署は同社株式の価額について、共同住宅の鑑定評価額を14億円とした上で、株式の評価専門機関に評価を委託し、算定の結果、修正簿価純資産方式での評価額を贈与時の時価として、評価通達6項を適用して税務調査の結果を通知した。
(5)資産家の子は期限後申告することになり、その際、共同住宅の評価額を上記同様14億円とし、問題の株式の発行会社を取引相場のない株式評価上の区分を小会社に当たるとして純資産価額方式と類似業種比準方式を併用し1株19,380円とした。
(6)税務署は6項適用に基づく修正簿価純資産方式での評価額で更正処分した。
(7)資産家の子はこれに不服があるとして国税不服審判所(以下、審判所という。)に審査請求した。
3.審判所の判断
審判所は、令和4年の最高裁判決の基本的な判断基準を受け継ぎ、株価が問題になった会社については、次のとおり事実関係を認定・指摘しました。
①同社が贈与日において所有する有形固定資産は、この不動産のみであり、同不動産の取得後贈与日を含む各事業年度における本件会社の売上げは、同不動産の建物に係る賃料収入のみであった。
②同社は、贈与日において事業計画を策定しておらず、贈与日までに株式の譲渡がされた事実もなかった。また、同社が雇用する従業員はいない。
これを踏まえ審判所は、税務署の評価方法が合理的で、その評価額が贈与日の時価を上回るものではないと認められるか否かについて次のように検討しました。
[1]同社が贈与日において所有するのは不動産のみであり、かつ、その建物に係る賃料収入が唯一の売上げであることからすれば、その収益性を反映してこの不動産の時価を算定することにより、将来の収益獲得能力を反映した合理的な評価が可能となる。
[2]同社は、建物に係る賃料収人を唯一の売上げとし、事業の拡大や縮小等の具体的な見込みも認められないことから、同社の状況が成長基調又は衰退基調にあるとも認められず、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどからすれば時価純資産法(修正簿価純資産法)による評価が不適当となる事情も見当たらない。
こうして審判所は、企業価値評価ガイドラインに準拠した「ネットアセット・アプローチに属する時価純資産法(修正簿価純資産法)を単独で採用したことは、相当」と判断、税務署の評価した株価で更正した処分を支持しています。
なお、相続時精算課税制度で贈与した財産については、贈与時の価額がそのまま相続税の計算上も固定される面が強調されがちです。
しかし評価に問題が見つかれば後で修正されることがある点、注意したいところです。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/10/14)より転載