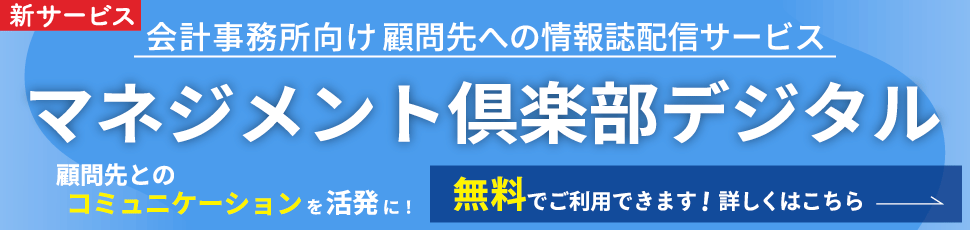相続直前に資産構成を変えた会社の株式への評価通達6項の適否めぐる裁判例

- ニュース/レポート
- 解説コラム
[解説ニュース]
相続直前に資産構成を変えた会社の株式への評価通達6項の適否めぐる裁判例
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(遠藤 純一)
[関連解説]
■使い勝手アップの相続時精算課税制度では、みなし贈与にご用心
■一団の宅地に用途の異なる建物がある時の小規模宅地等の特例の利用上の注意
1.はじめに
相続直前に大型出資を募って株式発行を実行、資産のうち一定の株式等の割合を引下げた会社の株式の相続税評価を巡って争われていた裁判の控訴審判決が令和7年6月19日、東京高裁でありました。東京高裁は、1審の東京地裁判決のうち納税者の主張を認めた部分を取消し、財産評価基本通達6項(以下、6項という。)に基づき株式を純資産価額方式で評価した税務署の更正処分等を支持する逆転判決を言い渡しました。
6項を適用して、税務当局が再評価した株価を財産評価基本通達(以下、評価通達という)に基づく評価額を上回る価額とすることが平等原則違反となるかどうかなどが争点とされました(6項についてはタクトニュースNo.933等を参照ください)。
2.不動産を持たせた会社の株式の生前贈与で6項が
この事案で問題になった行為は『臨時株主総会で決められた平成25年8月9日の新株発行と、この新株発行に対応した被相続人による出資、同年9月30日に行われた配当』です。
①被相続人創業の上場会社株を有する非公開同族会社A社に対して被相続人が行った約36億円に上る出資
②その出資に対する新株発行90万5440株(1株当たり3,976円)
③配当(普通株1株40円、総額1,836万円)
被相続人は、上記①に備え平成25年4月から5月にかけて、所有する上場株式等を売却し、約37億円を手にしていました。この出資の結果、A社は24年9月期の投資有価証券は13億円余りで、同社の貸借対照表の資産にしめる割合は89.2%でしたが、上記①出資後の25年9月期の資産約50億円に対する投資有価証券の割合は26.1%となりました。
相続開始後、相続人らは法定申告期限までに、上記株式につき、発行会社A社が評価通達178の評価上の区分が小会社に当たるため、類似業種比準価額と1株当たりの純資産価額を用いて評価する方式を選択し、同株式の価額を 1株当たり1,853円と評価しました。
この後、税務当局は最終的に平成30年9月に、上記株式に6項を適用して再評価して1株3,443円として追徴。税務当局では、新株発行等により上記株式を評価通達通りに評価した場合、相続税の負担が著しく軽減される結果となり、新株発行等はこれを期待して企図・実行されたものと見ていました。
というのも評価通達189の「特定の評価会社の株式」の評価について、評価会社が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社かどうかを判定する場合において、課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が株式等保有特定会社・土地保有特定会社に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする、とのなお書きがあったからです。
3.裁判所の判断
1審の東京地裁は、問題の株式の価額について、「評価通達の評価方法は、A社が小会社(評価通達178)に該当するため、更正の請求において請求人が選択した併用方式により評価することとなる(1株当たり1858円)。」としました。さらに東京地裁は、問題の株式の価額について、納税者が選択した「併用方式」により1株当たり1858円と評価したことに対し、新株発行等をしたことで相続税総額は約49%減少したけれど、仮に原告らが純資産価額方式を選択した場合、減少の程度は約2.8%にとどまっていたことを指摘、この減少は、「評価通達179(3)が小会社株式の価額の評価方法について、納税義務者による選択を認めていることに起因する」とし、税務署の6項を適用した評価は「租税法の一般原則である平等原則に違反するといわざるを得ない」と判断しました。
しかし東京高裁は、新株発行等により評価通達の定める方法で評価すると、課税価格の合計額は約17億885万4000円の軽減(軽減割合は約44.6%)。納付すべき相続税額の合計額は9億7872万4900円の軽減(軽減割合は約48.1%)となり、「軽減される相続税の額、割合等を総合的に考慮して判断すると、納税者らの相続税の負担は著しく軽減されることになる」と指摘。さらに相続開始の約3か月前に相続人が証券会社を訪れて相続税の節税対策を相談していたこと、株式保有特定会社等に該当しないための方策を含め、新株発行等を用いた相続税減税スキームなどを連日のように協議を重ねていたといった認定事実を踏まえ、相続人が「相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて新株発行等を行ったことは明らか」として、6項の適用を認める判決を下しています(本件は上告)。最高裁の判断の行方が注目されます。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/11/10)より転載