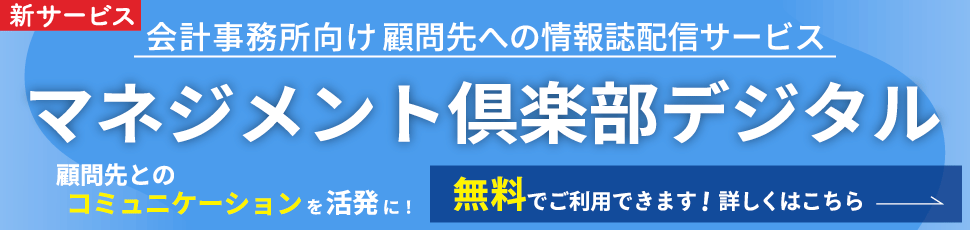非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例:複数の者から贈与を受ける場合の贈与の期限
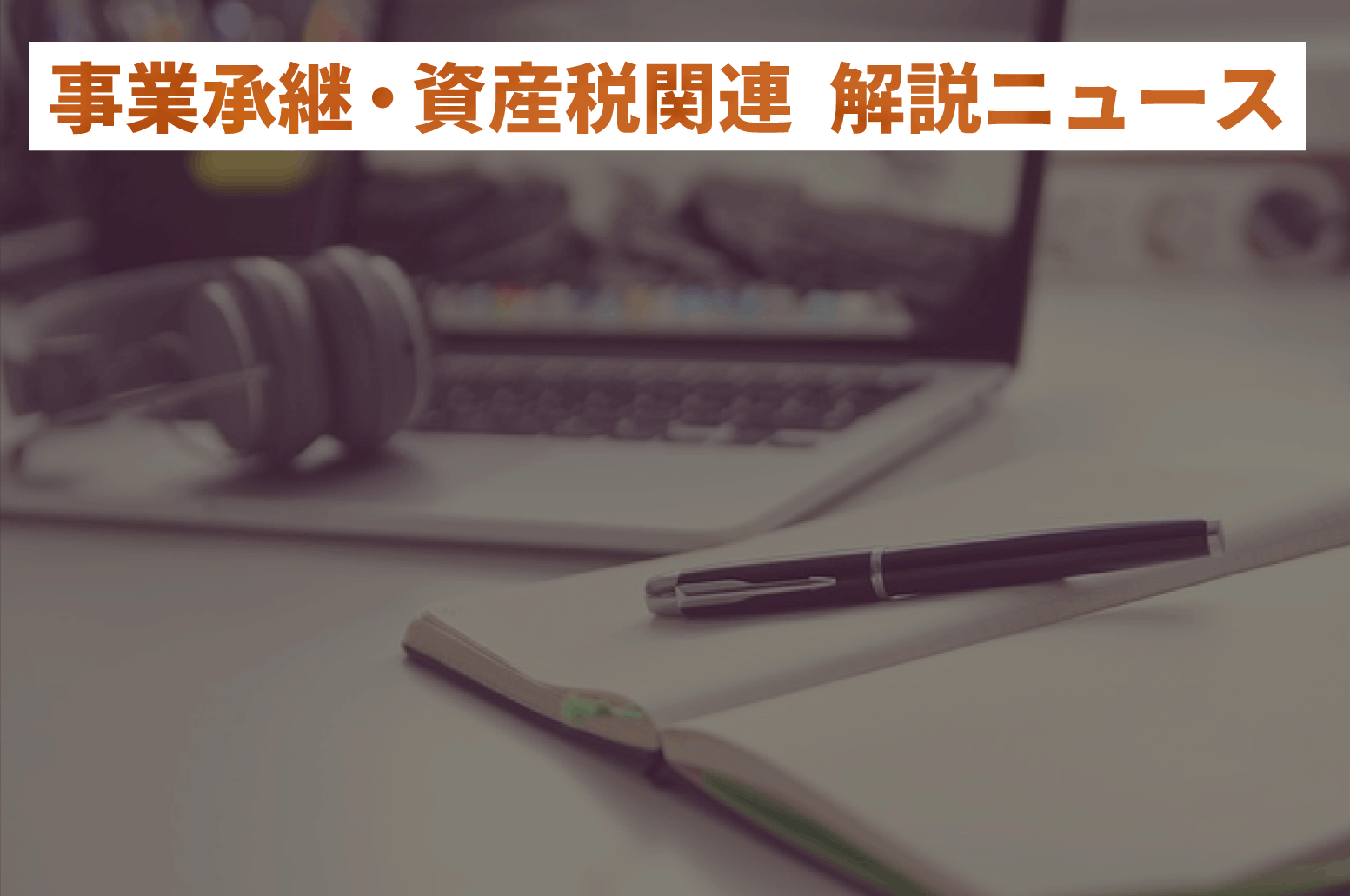
- ニュース/レポート
- 解説コラム
- 連載
[解説ニュース]
非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例:複数の者から贈与を受ける場合の贈与の期限
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
[関連解説]
■土地の譲渡契約を締結後、売主が物件の引渡前に死亡した場合の所得税の譲渡所得の取扱い
■所得税の特定の基準所得金額の課税の特例~極めて高い水準の所得に対する負担の適正化~
| 【問】
X株式会社(X社)は、発行済株式(すべて1株式1議決権)の90%相当を代表取締役のAさん、10%相当をAさんの叔母のBさんが保有しています。Aさんは、令和5年3月1日に当時X社の代表取締役であった父からX社株式の発行済株式の90%相当の贈与を受け、その贈与に係る贈与税について非上場株式に係る贈与税の納税猶予の特例(租税特別措置法(措法)70条の7の5・以下「贈与税の特例措置」)の適用を適法に受けています。
上記の場合において、Aさんが父の存命中にBさんの保有するX社株式の全部の贈与を受け、その贈与についても贈与税の特例措置の適用を受けようとするときには、AさんはBさんからいつまでにX社株式の贈与を受ける必要がありますか。 |
【回答】
1.結論
本問の場合、令和11年3月15日までの間に贈与税の申告期限が到来する贈与であることが特例措置の適用要件とされることから、令和10年12月31日までにX社株式の贈与を受ける必要があります。
2.解説
(1)特例措置の対象となる贈与の取得時期の要件
贈与税の特例措置の適用を受けるためには、次の①又は②のいずれかの贈与であることが要件とされます(措法70条の7の5第1項)。
①令和9年12月31日までの間の最初の贈与税の特例措置の適用に係る贈与
②上記①の贈与の日から(2)の「特例経営贈与承継期間」(措法70条の7の5第2項7号)の末日までの間に、贈与税の申告期限(措法又は国税通則法の規定により申告期限が延長された場合は延長前の期限)が到来する贈与
贈与税の特例措置は、令和9年12月31日までに行われた非上場株式の贈与が適用対象とされますが、これは①の「最初の贈与」(本問の場合は、令和5年3月1日にAさんが父から受けたX社株式の贈与が該当)について設けられている要件です。本問のAさんのように最初の贈与後に、その最初の贈与に係る非上場株式(X社株式)の贈与を追加で受ける場合は、上記②の贈与に該当することが贈与税の特例措置の適用要件となります(措法通達70の7の5-3なお書及びその逐条解説、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について(情報)」問2-17)。
(2)「特例経営贈与承継期間」の意義
(1)②の「特例経営贈与承継期間」とは、次の①の開始の日から②の終了の日までの期間をいいます(措法70条の7の5第2項7号)。
①開始の日
贈与税の特例措置の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日(通常は贈与の日を含む年の翌年3月16日)。
②終了の日
Aさんのように、父から受けたX社株式の最初の贈与について贈与税の特例措置の適用を受けている場合、その贈与後の次の贈与に係る特例贈与承継期間の終了の日は、【その特例経営承継受贈者の最初の贈与税の特例措置の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日(通常は最初の贈与税の特例措置の適用に係る贈与の日を含む年の翌年3月16日)以後5年を経過する日】となります。
ただし、上記下線部の日よりも先に特例経営承継受贈者(本問ではAさん)又はその者に係る特例贈与者(本問ではAさんの父)が死亡した場合は、これらの者の死亡の日のうちいずれか早い日が「終了の日」となります。
(3)本問へのあてはめ
Aさんは父から贈与により取得したX社株式については既に贈与税の特例措置の適用を受けています。したがってAさんが、父の存命中にBさんからX社株式を贈与により取得し、贈与税の特例措置の適用を受けようとする場合には、その贈与は、父よりX社株式の贈与を受けた日(令和5年3月1日)から、その贈与税の特例措置に係る特例贈与承継期間の末日(上記(2)②より、「(父からの)贈与の日を含む年の翌年3月16日以後5年を経過する日」、つまり令和11年3月15日)までの間に贈与税の申告期限が到来するものであることが必要です。このためAさんは、令和10年12月31日までに、BさんからX社株式の贈与を受ける必要があります。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2025/7/28)より転載