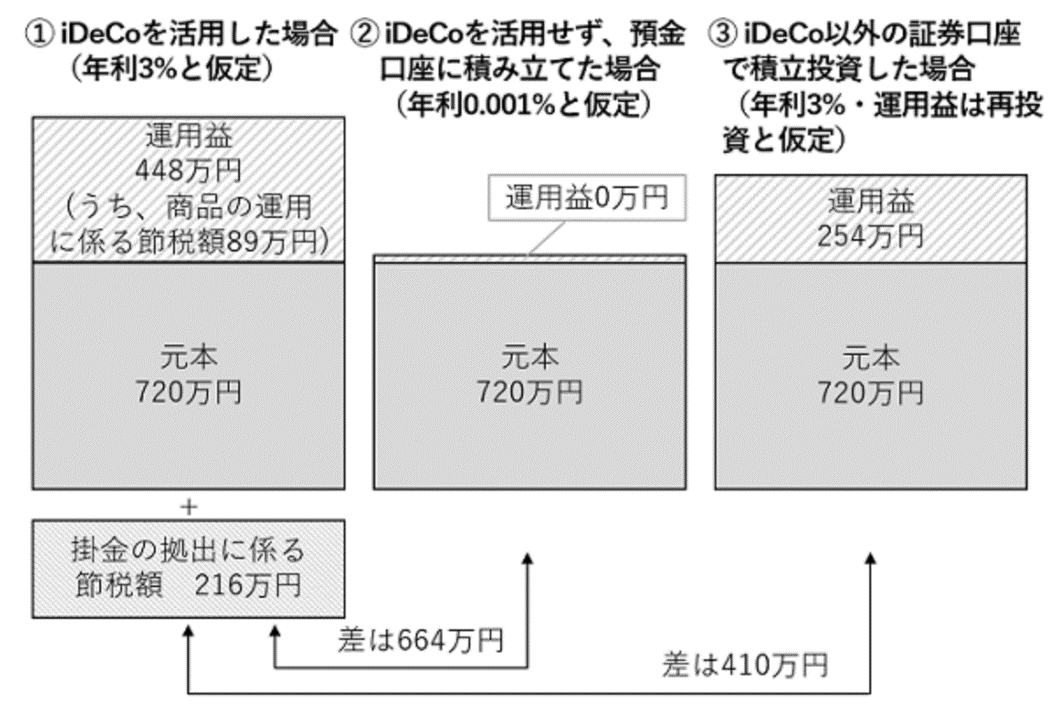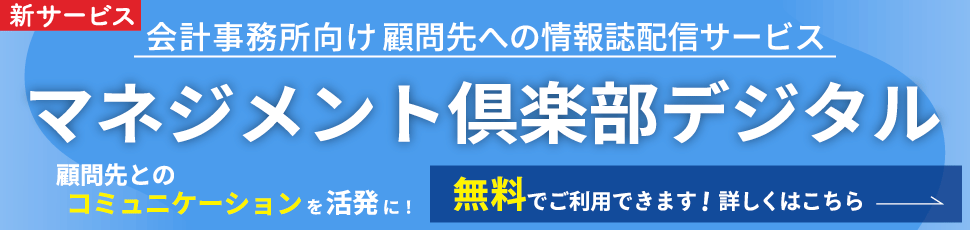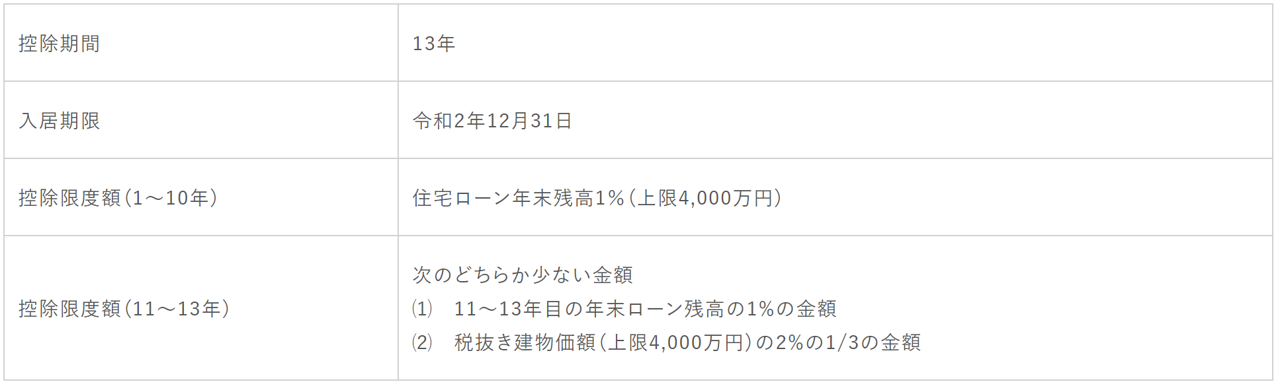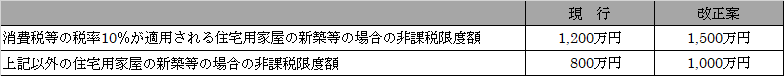[解説ニュース]
貸家と敷地を所有する親が子に貸家を贈与し、敷地を使用貸借で貸付け後に死亡した場合の敷地の相続税評価
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
[関連解説]
■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い①
1.貸家建付地の相続税法上の評価
土地付き建物の所有者が建物を他に貸付けている場合、その建物の敷地を「貸家建付地」といいます。貸家の借家人には建物敷地の利用権があり、所有者もその敷地の処分や利用が制限されます。よって貸家建付地を相続により取得した場合は、相続税計算上、土地所有者の自己使用地(自用地)としての評価額から借家人の有する敷地利用権相当額(=自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)を控除して評価をします(財産評価基本通達通26)。
2.使用貸借により土地を貸していた個人に相続が発生した場合の、その土地の相続税法上の評価の原則
使用貸借に係る土地を相続により取得した場合、その土地に係る相続税法上の評価額は、自用地としての価額となります(使用貸借通達3)。
建物の所有を目的として使用貸借により土地を借受けた場合の借主の使用権は、借地借家法が適用されず、借主には賃貸借による賃借権などの借地権とは違い、強い法的保護がなく、貸主は、その求めにより、いつでも無償で土地の返還を受けられます。よって、使用貸借に係る土地の使用権の経済的価値は極めて低いと考えられ、その相続税評価額はゼロとされます。つまり、使用貸借に係る土地の貸主側のその土地の相続税法上の評価は、【自用地の価額-使用貸借の使用権の価額(=0)】により、自用地としての評価となります。
3.貸家とその敷地を所有する親が、子に貸家を贈与し、その敷地を使用貸借により貸し付け後に親が死亡した場合の敷地の相続税評価
(1)原則的な考え方
貸家とその貸家の敷地を所有する親が、貸家のみを子に贈与し、その敷地を子に使用貸借により貸付けている場合、貸家贈与後のその貸家敷地の相続税法上の評価の原則的な考え方は、前述2と同様に、自用地評価となります。自用地として評価する理由につき、使用貸借通達3の取扱いを解説した「令和2年11月改訂版相続税法基本通達逐条解説」(以下「逐条解説」)867頁は次のように述べています。「…すなわち、一般に、使用貸借により借り受けた土地の上に建物が建築され、その建物が賃貸借により貸し付けられている場合における、その建物賃借人の敷地利用権は、建物所有者(土地使用借権者)の敷地利用権から独立したものではなく、建物所有者の敷地利用権に従属し、その範囲内において行使されるにすぎないものと解されている。したがって、土地の使用借権者である建物の所有者敷地利用権の価額をゼロとして取り扱うこととした以上、その建物賃借人の有する敷地利用権についてもゼロとして取り扱うことは当然であり、また、その土地自体の価額も自用であるとした場合の価額によるべきと考えられるからである。」
(2)貸家に係る賃貸借契約が贈与前に既に締結されており、贈与後から敷地の相続による取得の時までその契約が継続している場合の貸家の敷地の評価
表題の場合、その貸家の敷地の相続税法上の評価は、次の理由により貸家建付地としての評価とされます(参考:「逐条解説」867頁~868頁)。
貸家の贈与前は、貸家の所有者である親がその敷地の所有者でもあり、貸家の所有者である親と貸家の借家人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸家の借家人は貸家を通じてその敷地利用権を有しています。その敷地利用権は敷地の所有権に対するものであり、判例(最判昭和38年2月21日民集17巻1号219頁、最判昭和41年5月19日民集20巻・989頁参照)において、貸家借家人の有する敷地利用権は、貸家が第三者に譲渡された場合でも侵害されないとしています。つまり、借家人の権利の保護の観点から、その貸家の譲渡(贈与や相続による所有権の移転も含むと解されます)により、貸家自体の土地に対する利用権が使用貸借となっても、借家人の従前の敷地の所有権に対する敷地利用権が、敷地の使用貸借による利用権(ゼロ評価)に対する敷地利用権に変わることはないということです。
表題の場合の貸家の借家人は、相続で新たにその貸家の敷地の所有者が変わっても、それより前の贈与の前に取得している貸家の敷地に対する利用権は侵害されることなく有しているため、その敷地は、相続で誰に取得されても、引き続きその処分や利用が、その利用権により直接制限されるため、表題の場合の貸家敷地の評価額は、自用地としての評価額から貸家建付地と同等の減額を行うのが当然といえます。以上により、表題の場合の貸家の敷地の相続税法上の評価は、前述 (1)にかかわらず、貸家建付地としての評価とされます。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2021/07/26)より転載