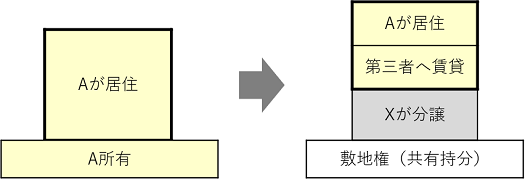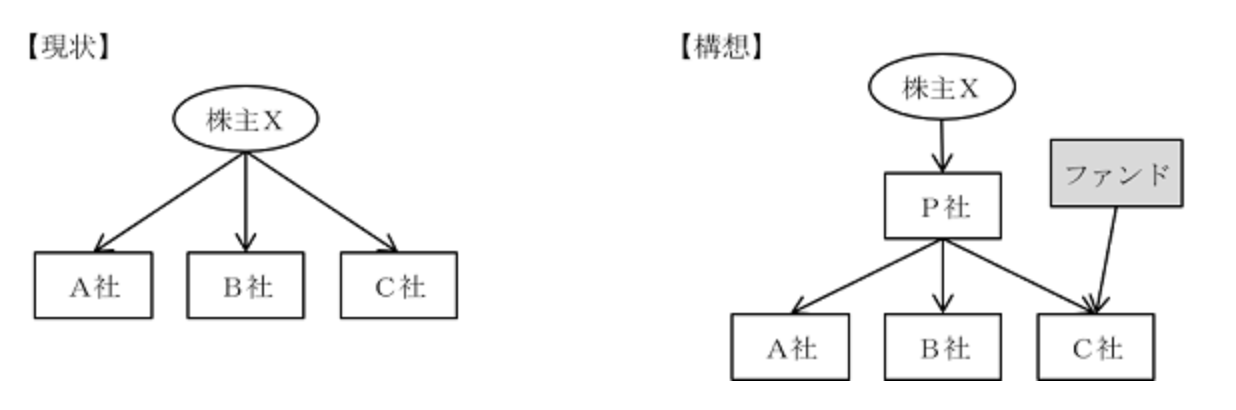[解説ニュース]
特定生産緑地制度の税務上の留意点について
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(猪狩 祐介/税理士)
【問】私は東京都A市に農地を所有し、農業を営んでいます。私の父は所有していた農地の全部について、A市より平成4年(1992年)11月に生産緑地の指定を受けており、私は父から平成10年にその生産緑地の全部を相続し、農業相続人として農地等に係る相続税の納税猶予(措法70の6)の適用を受けています。
生産緑地の指定を継続する場合には、その指定の告示から30年経過する前に、A市による「特定生産緑地(生緑法10の2)の指定(10年継続)」を受ける必要があると聞きました。生産緑地の指定から30年を経過する2022年において、特定生産緑地の指定を受ける場合と受けない場合とで、私の相続税の納税猶予や固定資産税の課税にどのような影響がありますか。 |
【回答】
1.特定生産緑地制度の概要
①特定生産緑地制度とは
特定生産緑地制度とは、市町村が、生産緑地指定から30年を経過する日(申出基準日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地整備の状況など勘案して、申出基準日以後もその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することをいいます(生緑法10の2)。いわば再指定され た生産緑地を特定生産緑地といいます。
②特定生産緑地の指定を受ける場合
特定生産緑地の指定を受けると、10年間の営農義務が課されますが、固定資産税は、従来通り農地課税(低い金額)になります。相続税の納税猶予も営農している限り継続されることになります(措法70の6)。また、特定生産緑地の指定を受けた後でも、生産緑地の所有者である主たる従事者が死亡した等の場合は、相続人が相続税の納税猶予の適用を受けることや、買取りの申出をして生産緑地の指定の解除をすることができます(生緑法10)。
③特定生産緑地の指定を受けない場合
特定生産緑地の指定を受けない場合、農地に対する固定資産税は5年をかけて段階的に宅地並み課税になります。現在受けている相続税の納税猶予については、当代に限り継続されますが、次の世代では、生産緑地の指定を受けていないことから、新たに相続税の納税猶予を受けることができません。
2.農業相続人の有無別の特定生産緑地の指定と税務上の留意点
特定生産緑地の指定をめぐる税務上の取扱いは、あなたの相続時に相続人となる人のなかに、農業の後継者(農業相続人)がいるかどうかにより、次の通りに区分されます。
①農業相続人がいる場合
相続税の納税猶予の適用を受けている場合には、猶予を継続するため、終身営農が必要となります。特定生産緑地の指定を受けなかった場合でも、営農している限り、あなたの納税猶予は打ち切りになりませんが、あなたの親族に農業の後継者がいる場合であっても、あなたの相続において相続税の納税猶予の適用を受けることができず、固定資産税も宅地並み課税となるため、特定生産緑地の指定を受けておくことが望ましいと考えられます。
②農業相続人がいない場合
次の世代に農業相続人となる人がいない場合
(イ)特定生産緑地の指定を受け10年間営農を継続する(10年毎に継続の可否を判断)
(ロ)30年経過前に買取りの申出を行い、生産緑地の指定を解除し、土地の有効活用を行う。
(ハ)特定生産緑地の指定を受けず、買取りの申出も行わず、いつでも買取りの申出ができる状態で営農を継続する。
の3つから選択することになります。
引き続き税制上のメリット(固定資産税の農地課税、相続税の納税猶予)を受けるためには、上記(イ)を選択することとなります。対して、宅地に転用して活用するのであれば(ロ)(ハ)を選択することになります。ただし、買取りの申出を行うと、納税猶予が打ち切りとなり、あなたは相続税額と利子税を一括で納付することになります。
将来農地をどのように維持するかは、税制面からも重要な問題です。特定生産緑地の指定を受けるかどうかについては、農地税制に詳しい税理士に相談しながら検討してください。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2020/09/23)より転載