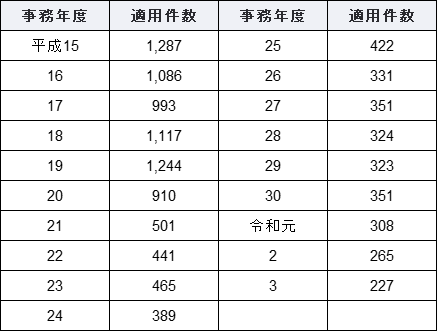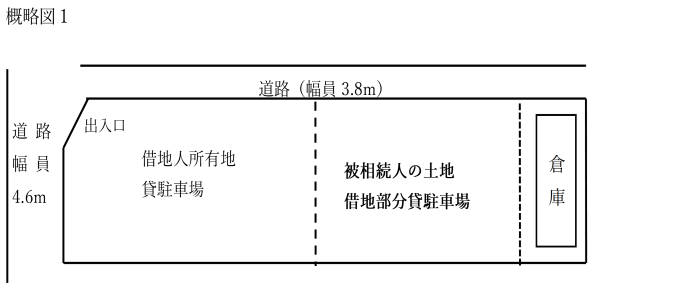[解説ニュース]
令和5年度税制改正:所得税の特定の事業用資産の買換え特例(3号)の見直し
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
[関連解説]
■貸家と敷地を所有する親が子に貸家を贈与し、敷地を使用貸借で貸付け後に死亡した場合の敷地の相続税評価
■自宅家屋を取壊して敷地を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の取扱い①
1.特定の事業用資産の買換え特例(3号)の概要
所得税の特定の事業用資産の買換え特例は、個人が特定の地域内にある事業用資産を譲渡して、一定期間内に特定の資産を取得し、かつ1年以内に事業の用に供する等の所定の要件を満たした場合、譲渡益の一定割合(課税繰延割合)に相当する金額の課税が繰延べられるという税制です(租税特別措置法(措法)37条。法人税でも措法65条の7で同様の税制が設けられています)。この特例のうち利用されることが多いのが、措法37条1項3号の買換え(以下「3号買換え」)です。
この3号買換えでは、国内にある土地等、建物又は構築物で譲渡日を含む年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの(譲渡資産)を譲渡し、国内のある一定の土地等、建物等又は構築物(買換資産)を取得した場合に、適用を受けることができます。
2.改正のポイント
令和5年度税制改正により、3号買換えにつき次の見直しが行われた上、適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されました(改正法附則32条6項、7項)。
(1)課税繰延割合の変更
①概要
令和5年4月1日以後の譲渡より、東京都の特別区の区域から地域再生法の「集中地域」*以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税繰延割合が90%(改正前80%)に引き上げられ、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税繰延割合が60%(改正前70%)に引き下げられました(措法37条10項)。
*「集中地域」とは、東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、横浜市、川崎市、大阪市等の、法令が定める一定の地域をいいます(地域再生法 5条4項5号イ、同政令5条)。
②課税繰延割合の変更の趣旨
集中地域の外から内への買換えは、地域再生法における企業の地方拠点強化の促進と両立しないため、改正前から圧縮割合が原則の80%から70%に引き下げられていました。今回の改正では、集中地域の外から東京都の特別区への本店の移転を伴う買換えについて、さらに圧縮割合が60%に引き下げられました。一方、企業の地方拠点強化につながると考えられる東京都の特別区から集中地域の外への本店の移転を伴う買換えについては、圧縮割合が90%に引き上げられました(参考:財務省「令和5年度税制改正の解説」(以下「解説」)398頁)。
(2)届出要件の追加
①概要
令和6年4月1日以後、同一年に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をした場合には、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日を含む「3月期間」の末日の翌日以後2ヶ月以内に、この特例の適用を受ける旨、及び取得見込資産又は譲渡見込資産の種類等を記載した届出書を税務署長に提出することが必要になります(措法37条1項)。
なお、この要件は、同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合の特例の適用要件であるため、譲渡資産の譲渡の前年中に買換資産を先行取得する場合(措置法37条3項)や、譲渡資産の譲渡の翌年以降に買換資産を取得する見込みの場合(同条4項)等には、この届出は不要とされます。
②「3月期間」の意義
「3月期間」とは、1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、10月1日~12月31日の各期間をいいます(措法施行令25条3項)。
③届出要件の追加の趣旨
3号買換えは、土地政策又は国土政策の観点から、特定地域からの追い出し促進や土地の有効利用促進等を目的に設けられた特例です。しかし、複数の土地等の売買取引を行う際に、申告時にその売買取引を並べた上で特例の要件に合致する譲渡資産と買換資産の組み合わせを事後的に作成し、適用を受ける事例が見受けられ、問題視されていました。今回3号買換えの適用期限を延長するに当たり、このような問題点を是正し、税制として適切に機能させるため、譲渡(又は取得)後一定期間内に本制度の適用及び適用を受ける買換え(譲渡資産と買換資産の組み合わせ)に関する事項の届出が、要件として追加されることになりました(参考:「解説」402頁)。
(注)法人税の3号買換えについても、上記2とほぼ同様の改正が行われます。ただし法人税の3号買換えの改正では、2(2)①の「同一年」が「同一事業年度」、②の「3月期間」の意義が「事業年度をその開始の日以後3ヶ月ごとに区分した各期間」となります(措法65条の7第1項)。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/7/24)より転載