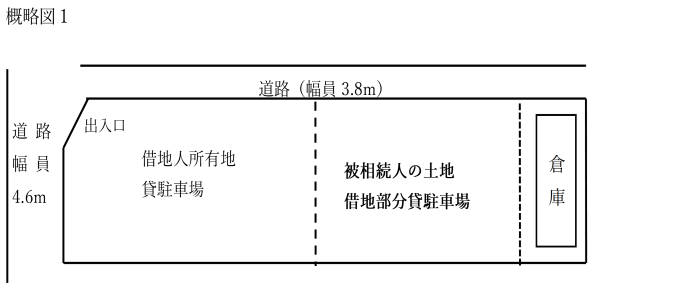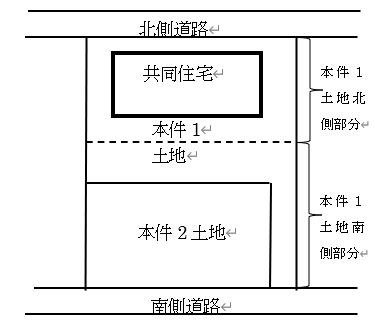[解説ニュース]
令和5年度税制改正:相続開始前に被相続人から暦年課税に係る贈与があった場合の相続税
〈解説〉
税理士法人タクトコンサルティング(山崎 信義/税理士)
[関連解説]
■交換差金等の支払いを受けた場合の所得税の固定資産の交換特例の取扱い
■【Q&A】先代経営者からの贈与による取得前に相続により取得した株式に係る事業承継税制の適用
1.暦年課税のあらまし
(1)贈与税の計算方法
暦年課税の贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の価額を合計し、その合計額から基礎控除額110万円を控除します。その控除後の金額に超過累進税率をかけて税額を計算します(相続税法(相法)21条、21条の2、21条の7、租税特別措置法70条の2の4等)。
(2)相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の相続税計算への加算
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(被相続人の死亡による死亡保険金の取得等、相続又は遺贈により財産を取得したものとみなされる人も含む。)が、その被相続人から相続開始前 3 年以内に贈与を受けた財産がある場合は、被相続人に係る相続税の課税価格の計算上、その贈与を受けた財産の額(贈与時の価額)が加算され、加算された人の相続税の計算上、その贈与財産の価額に対応する贈与税額を控除します(相法19条1項、3条1項等)。
2.相続開始前に贈与があった場合の相続税計算への加算期間等の見直し
(1)改正の趣旨
贈与税の暦年課税は、生前贈与による相続税の回避を防止する観点から、相続税に比べて取得した財産に対して適用する税率が高くなる構造となっています。例えば、相続する財産が4,000万円の場合、相続税の税率は20%ですが、その財産を1,000万円に4分割して子に贈与しても贈与税の税率は30%となり、相続税よりも高い税率が適用されます。
その一方で、相続財産が多いため多額の相続税がかかることが見込まれる人にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が低いことから、財産を分割して贈与を繰り返す方法を採ることで、贈与税の計算上は、相続税よりも低い税率を適用することが可能です。例えば、相続する財産が6億円超の場合、相続税の税率は55%ですが、その財産を4,500万円以下に分割して贈与すると、贈与税の税率は相続税よりも低い税率(55%以下)が適用されます。
以上のような問題点を改善し、若年世代への財産の移転に関して生前贈与でも相続でも最終的な税負担を一定にする、「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築することを目的として、次の(2)~(5)の改正が行われました。
(2)加算期間の延長
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けた財産がある場合には、原則、その贈与により取得した財産(加算対象贈与財産)の価額(贈与時の価額)が、被相続人に係る相続税の課税価格の計算上加算され、加算された人の相続税の計算上、加算された贈与財産の価額に対応する贈与税額を控除されます(改正後の相法19条1項)。
なお被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった人が被相続人から贈与を受けた財産の価額は、被相続人に係る相続税の課税価格には加算されないので、加算期間の延長の対象にはなりません。
(3)加算対象贈与財産の100万円控除
過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、加算対象贈与財産のうちその相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の合計額から100万円が控除されます(改正後の相法19条1項かっこ書)。例えば令和13年1月1日に相続が開始した場合、令和6年1月1日から9年12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額から100万円が控除されます。
(4)適用時期
(2)と(3)の改正は、原則、令和6年1月以後に受けた贈与より適用されます(令和5年改正法附則(以下「附則」)19条1項)。
(5)加算期間の延長の経過措置
(2)の延長には経過措置があり、令和9年1月以後に開始した相続より、改正前の3年から順次延長されます。令和9年1月1日から12年12月31日までに開始した相続については、令和6年1月から相続開始日までに受けた贈与財産の額が加算対象とされ、令和13年1月1日後に開始した相続から加算期間が7年となります(附則19条2項、3項)。
例えば令和8年7月1日に相続が開始した場合、令和5年7月1日以降に受けた贈与が加算対象となります。令和10年1月1日に相続が開始した場合には、令和6年1月1日以降に受けた贈与が加算対象となります。令和13年7月1日に相続が開始した場合には、令和6年7月1日以降に受けた贈与が加算対象となります。
税理士法人タクトコンサルティング 「TACTニュース」(2023/6/12)より転載