【ZEIKEN LINKS(ゼイケン リンクス)よりおすすめ動画解説(Webセミナー)のお知らせ】
ライブ講座でも好評の宮田房枝先生(税理士法人タクトコンサルティング)の講座がZEIKEN LINKSにて全編公開中です。
事業承継対策としても活用が期待される”信託”について、基本から理解したいと考えている方に最適な講座です。具体的な事例を用いて解説いたします。

「信託を活用した相続・事業承継対策」
講師:宮田房枝(税理士)
【全5回】
【講義内容】
信託法の大改正から約10年が経過しました。
信託は我々にとって身近な制度となり、これまでは対策が難しいなと思っていたような場面でも、信託を活用すれば簡単に解決できるという場面もあることから、事業承継や相続対策に関するアドバイスを行う上で、これからは「信託」の知識が必要不可欠になると考えられます。
本講座では、この信託の概要と活用事例を紹介します。
1.概要(➀信託とは ②税務上の取扱い)
2.事例紹介
① 認知症に備えた活用法
② 遺言書としての活用法~いわゆる「遺言代用信託」~
③ 高齢者の土地活用としての活用法
④ 共同相続によるトラブルを防止するための活用法
⑤ 浪費癖のある子供の無駄遣い防止のための活用法~いわゆる「遺言信託」~
⑥ 非上場会社の事業承継における活用法~議決権を維持しつつ生前贈与する方法~
⑦ 株主としての活用法
【関連コンテンツ】
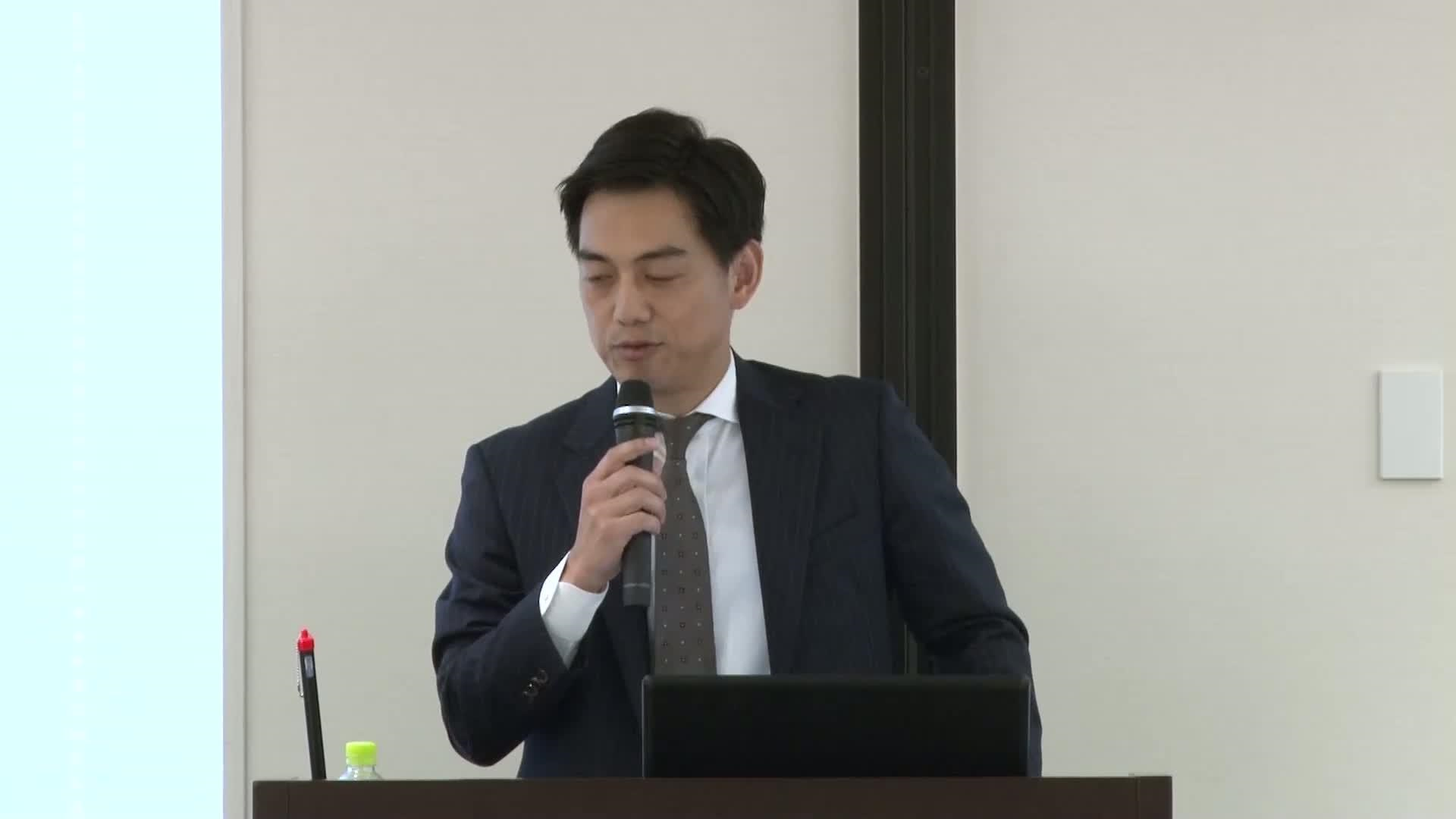
2.png)
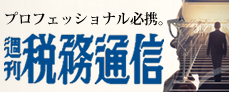
1.png)
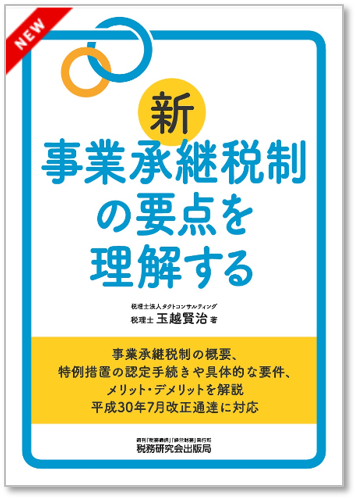
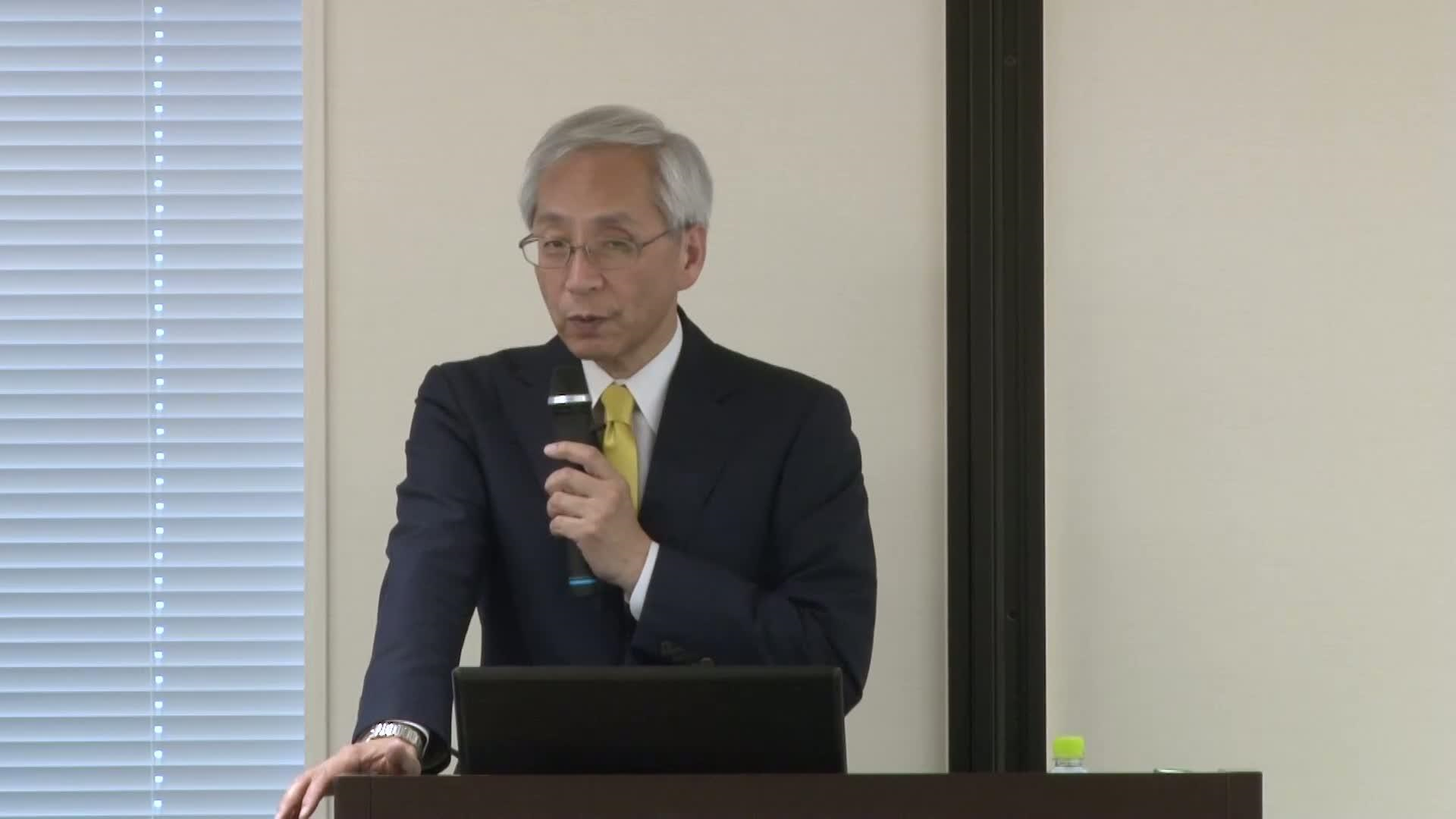
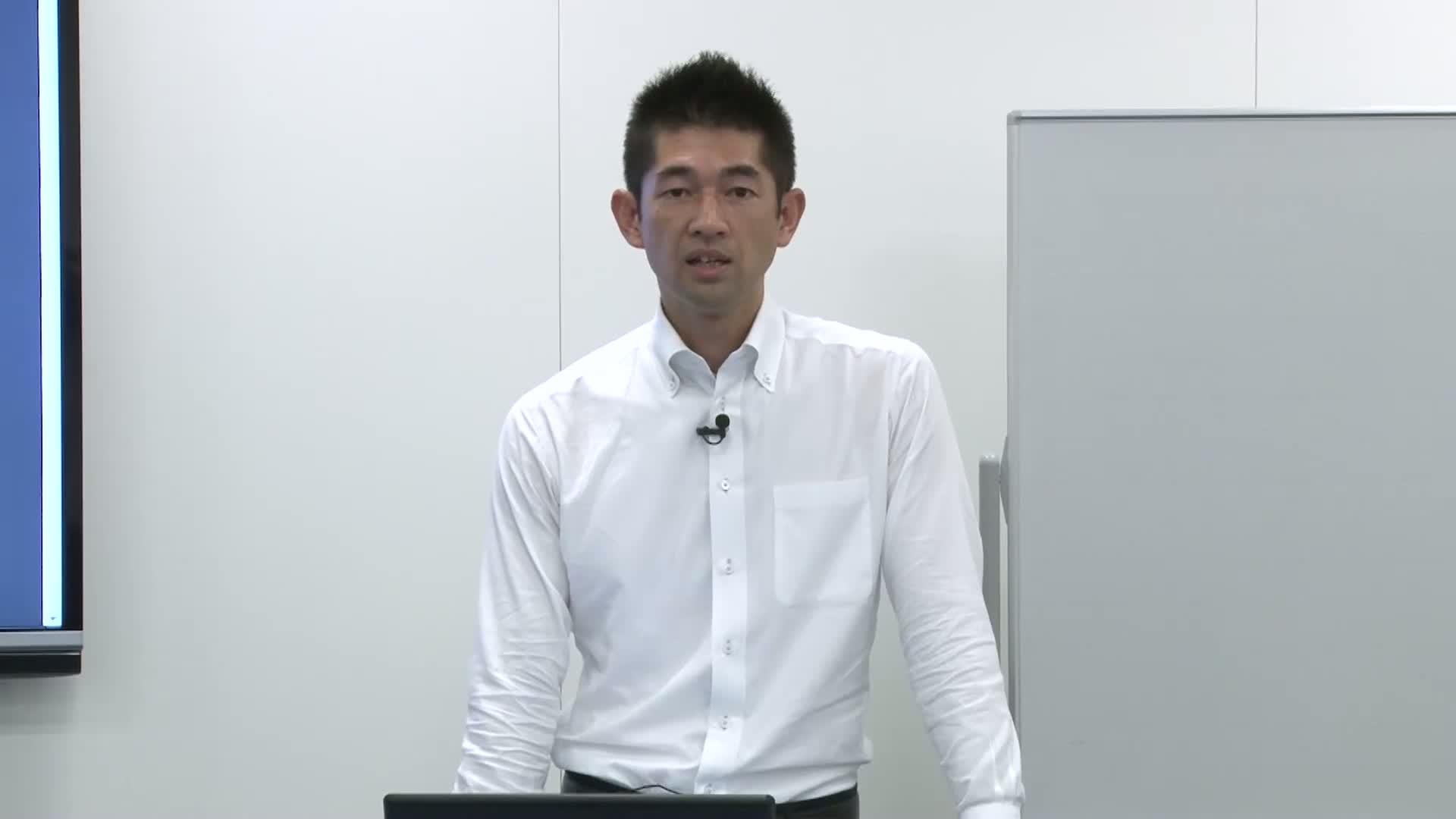
1.png)
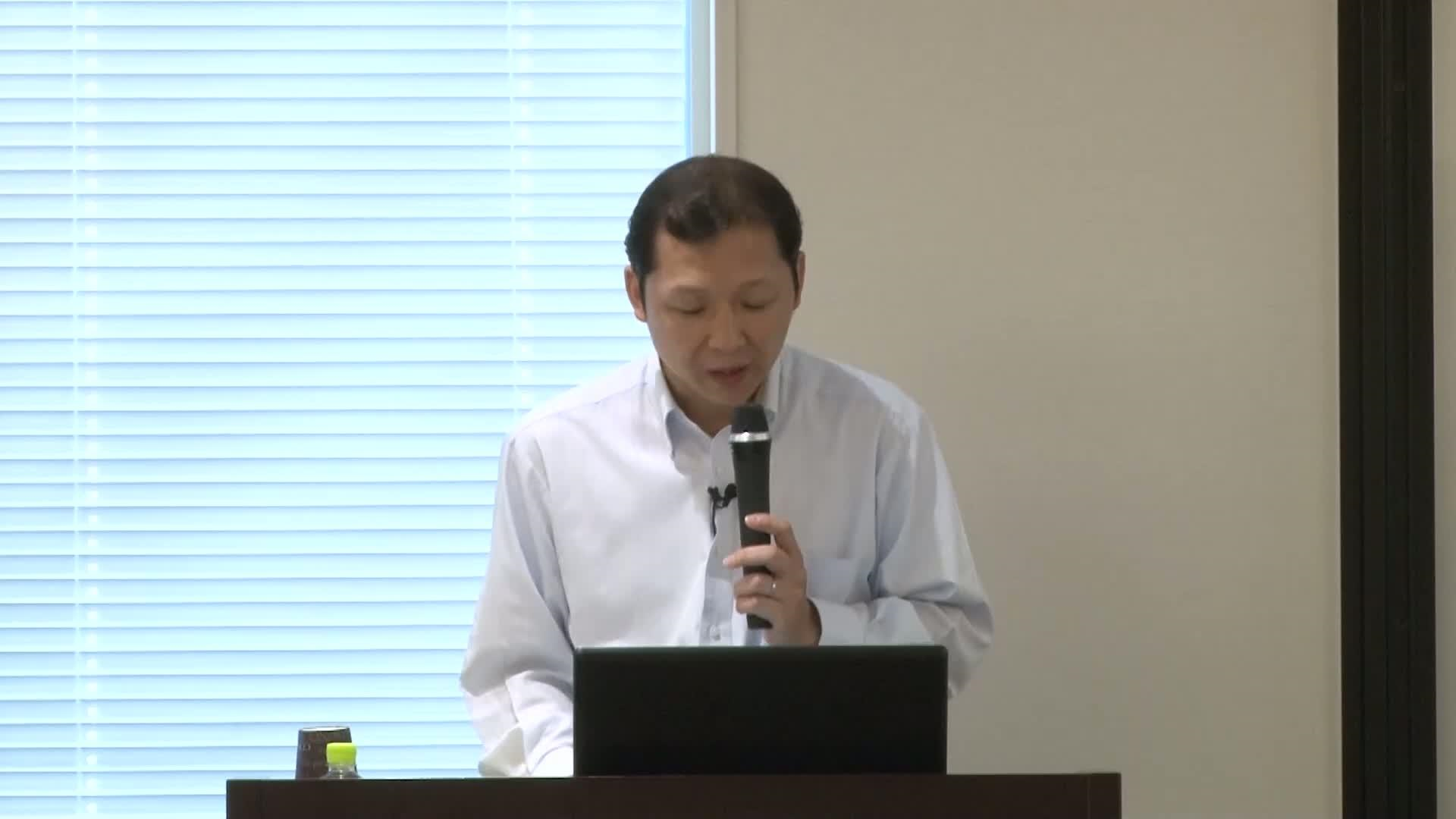
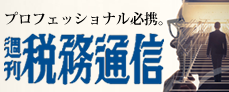
-210x300.png)
-212x300.png)

